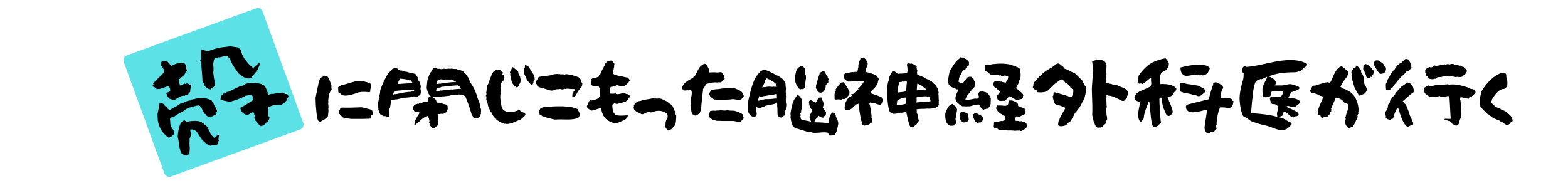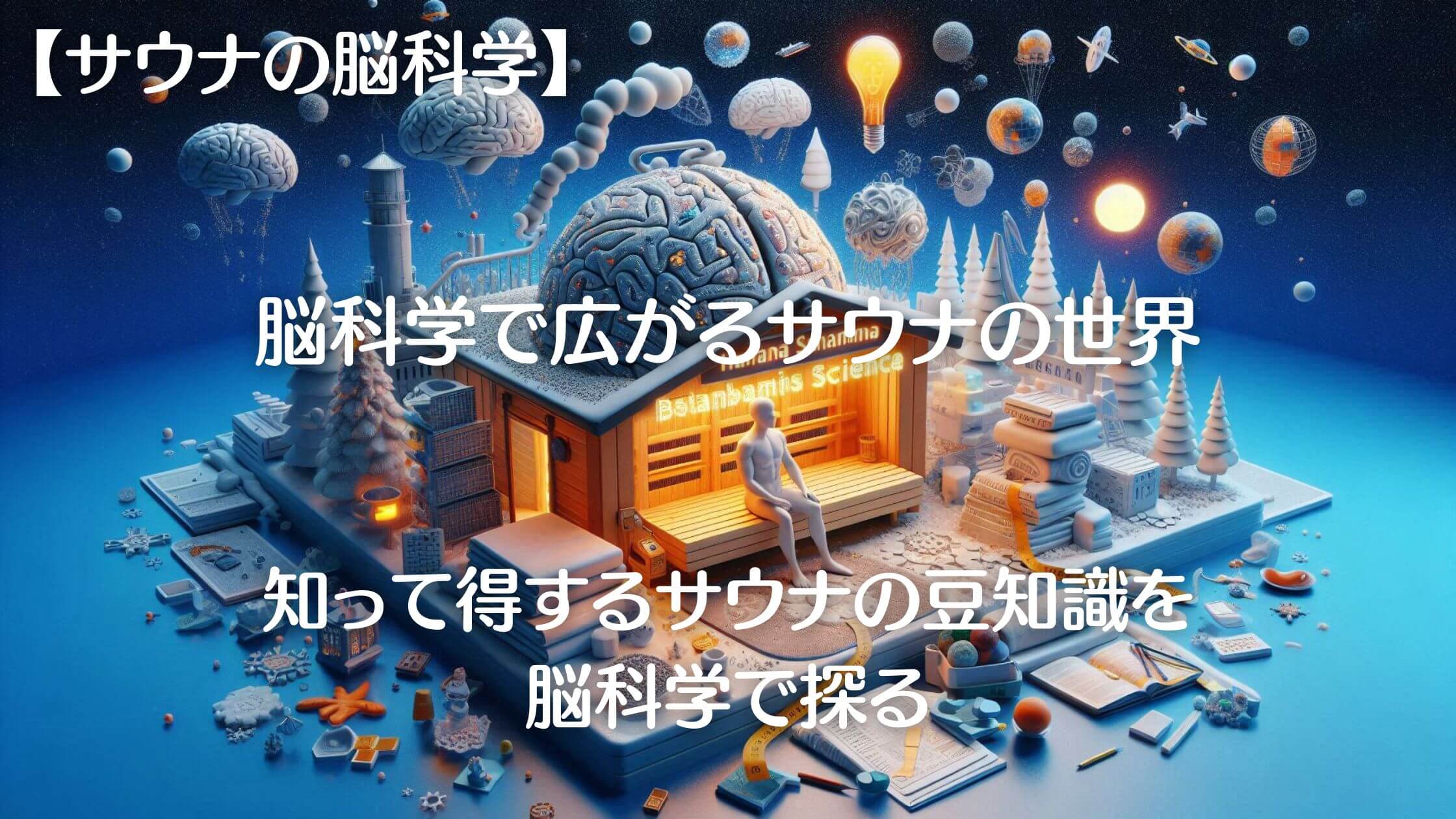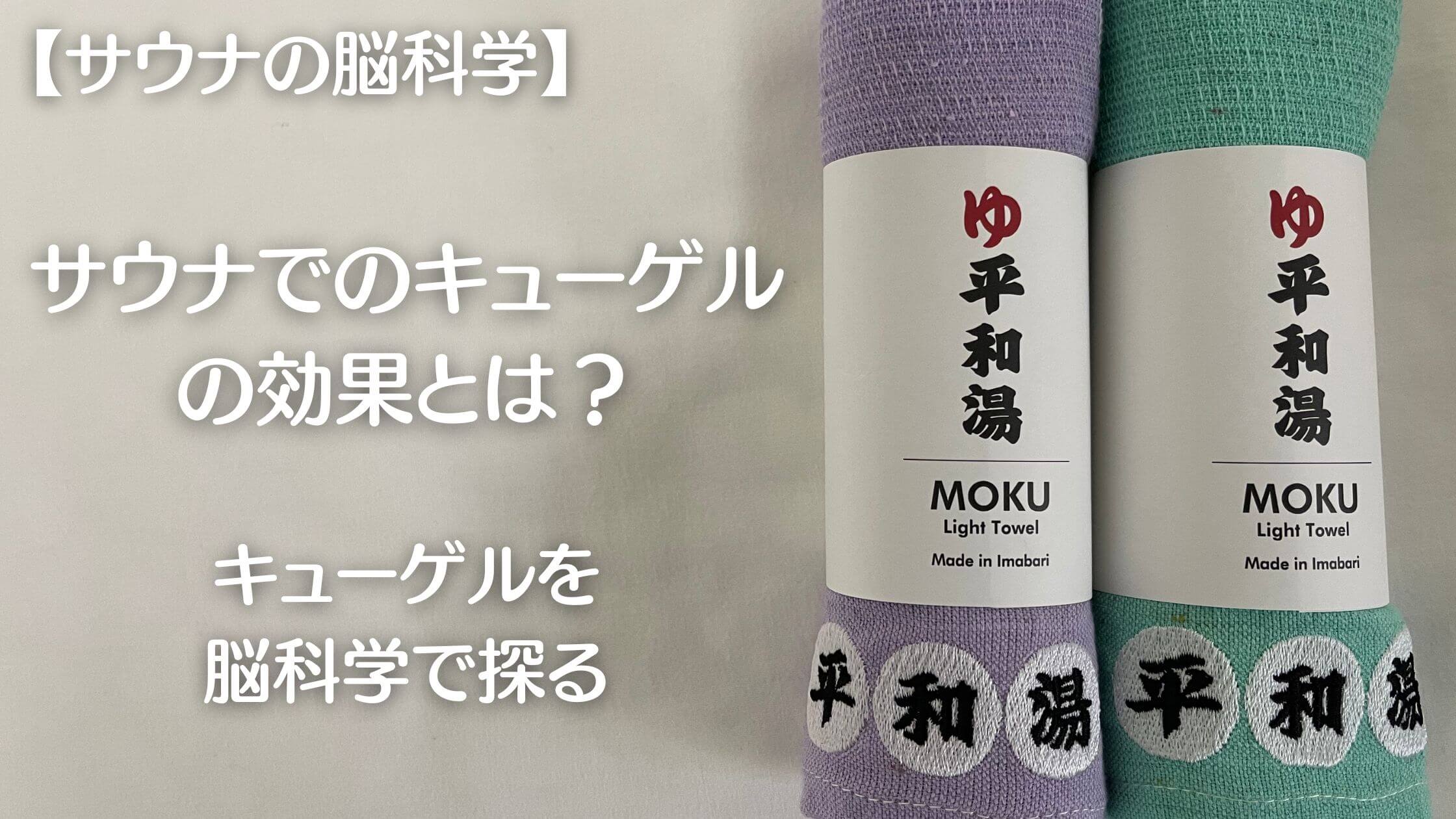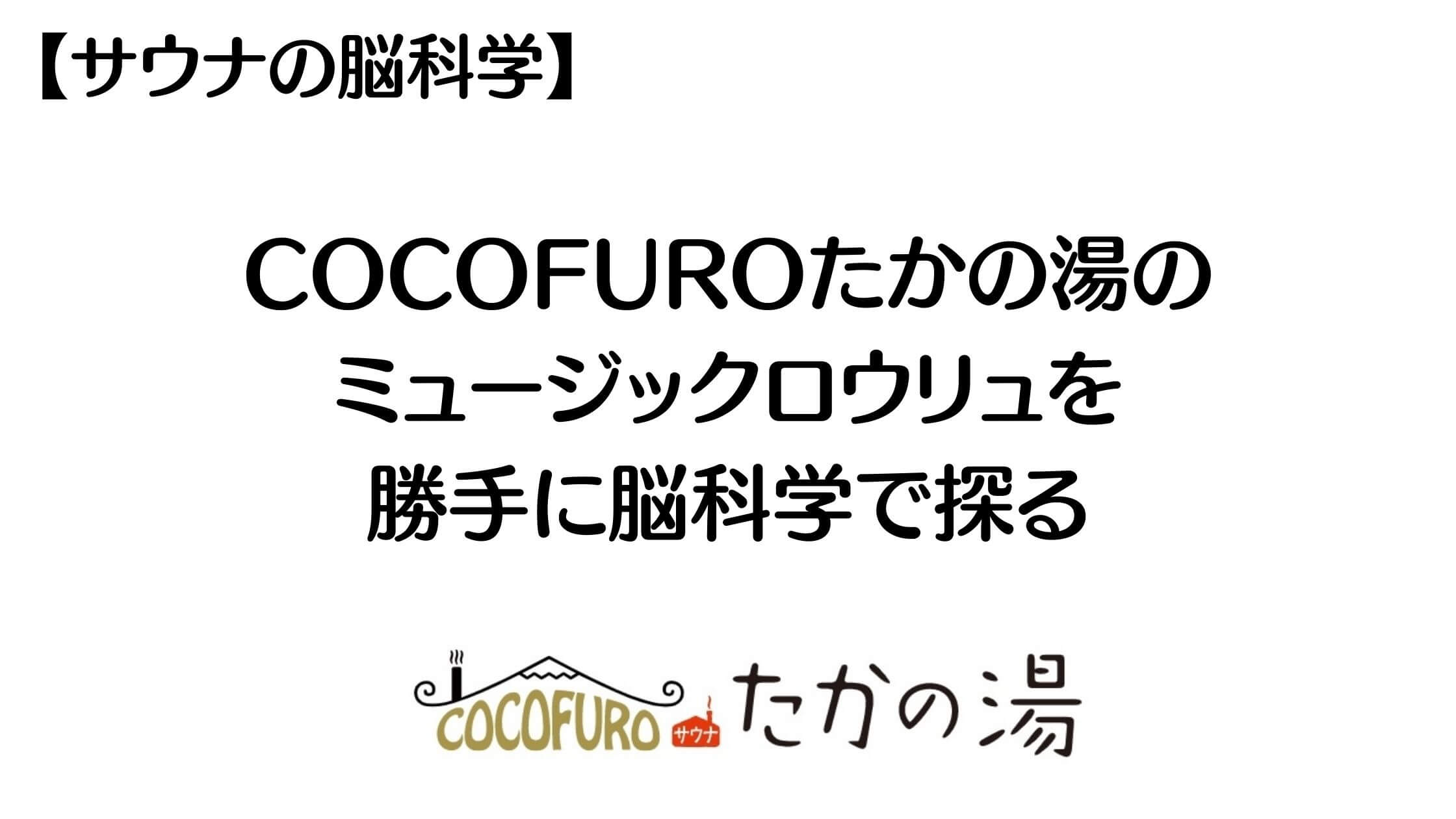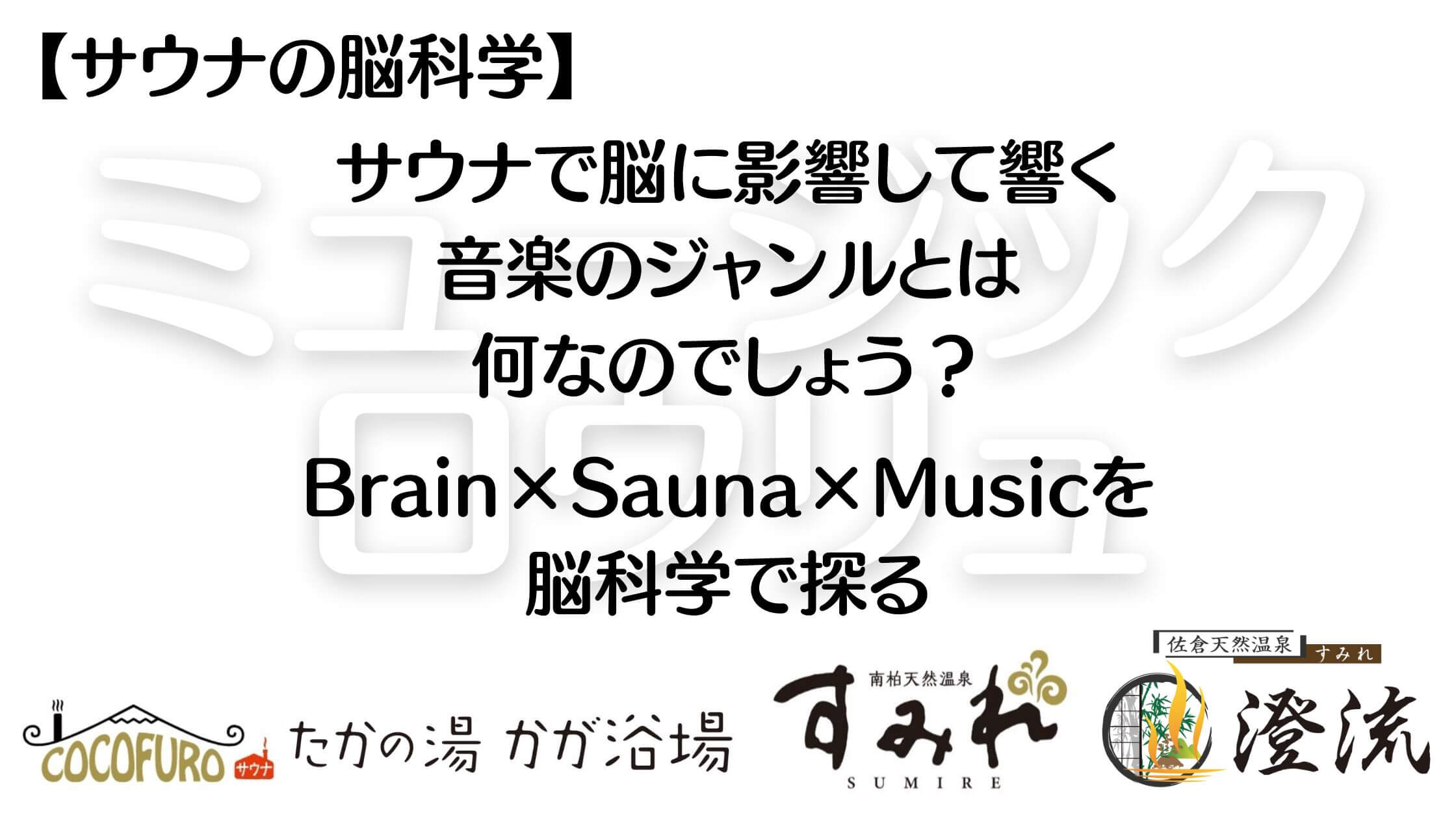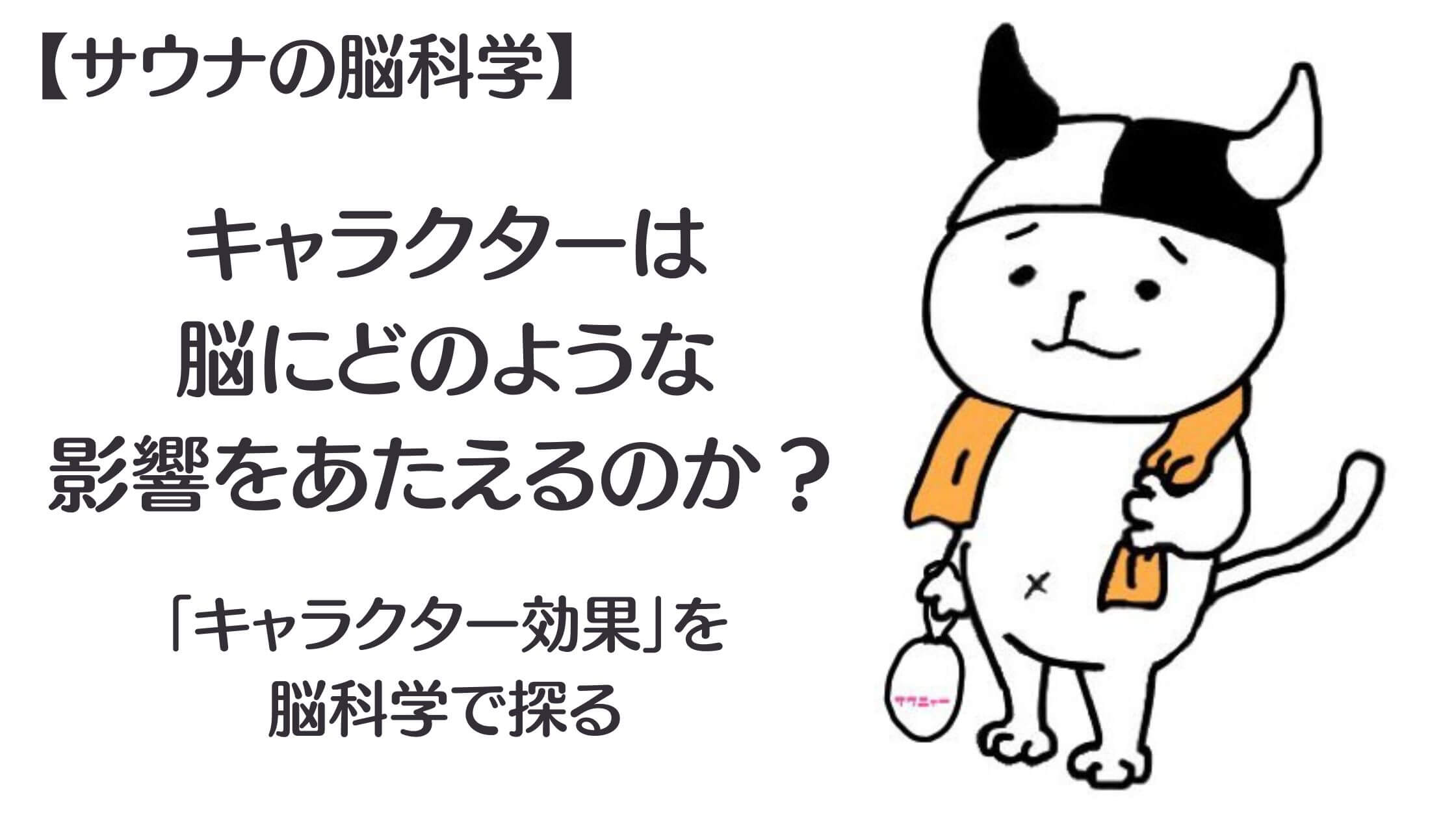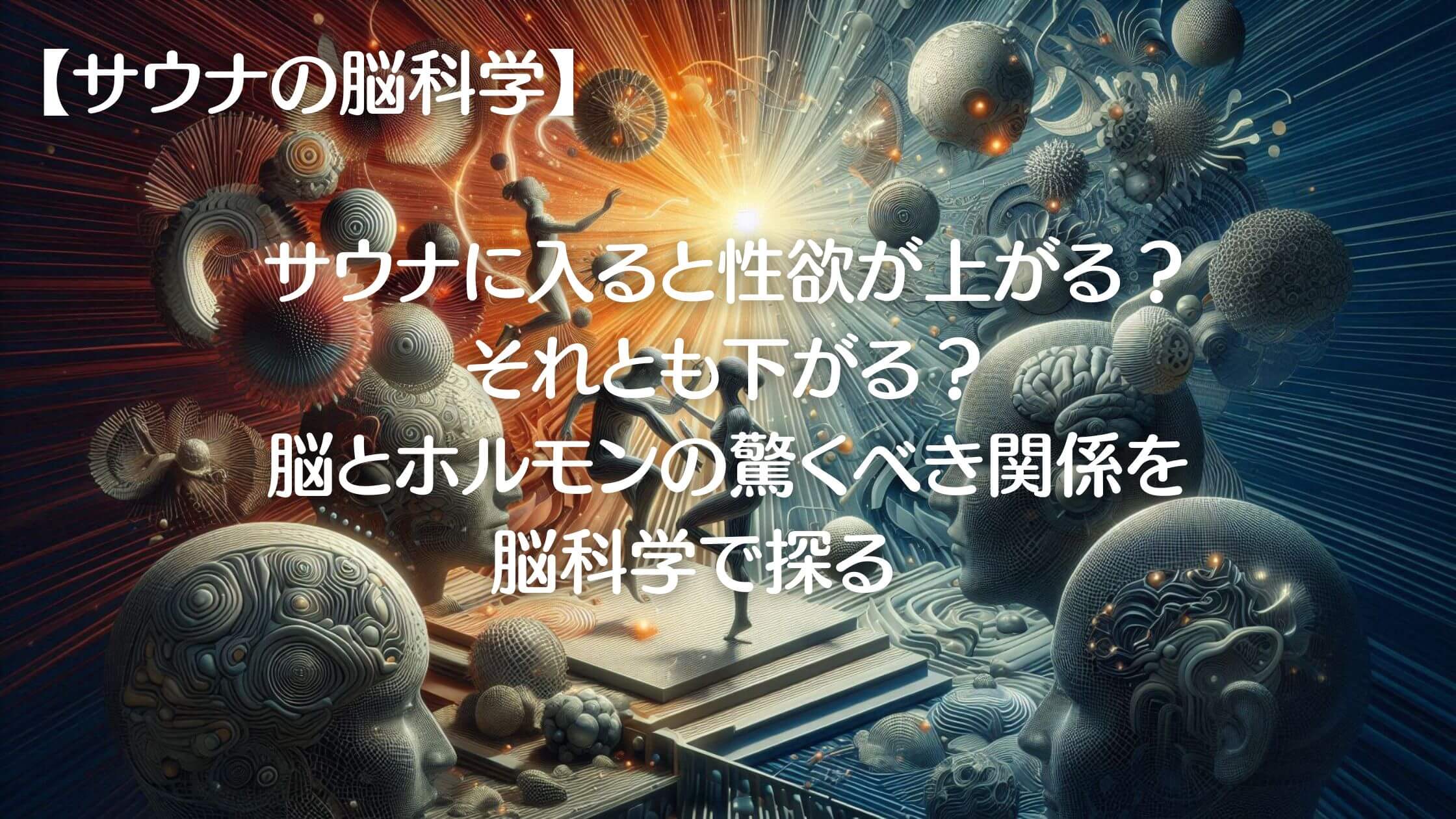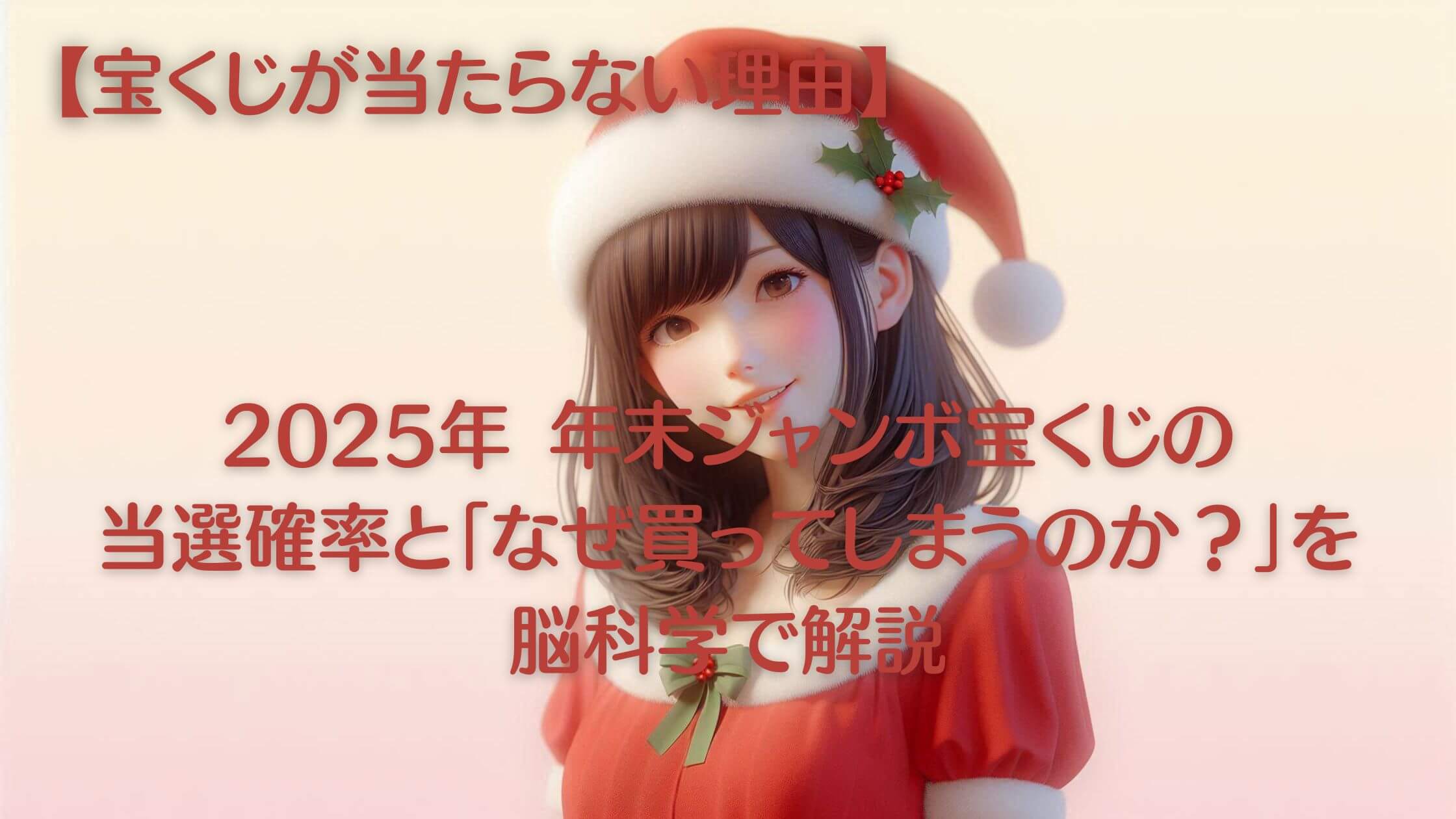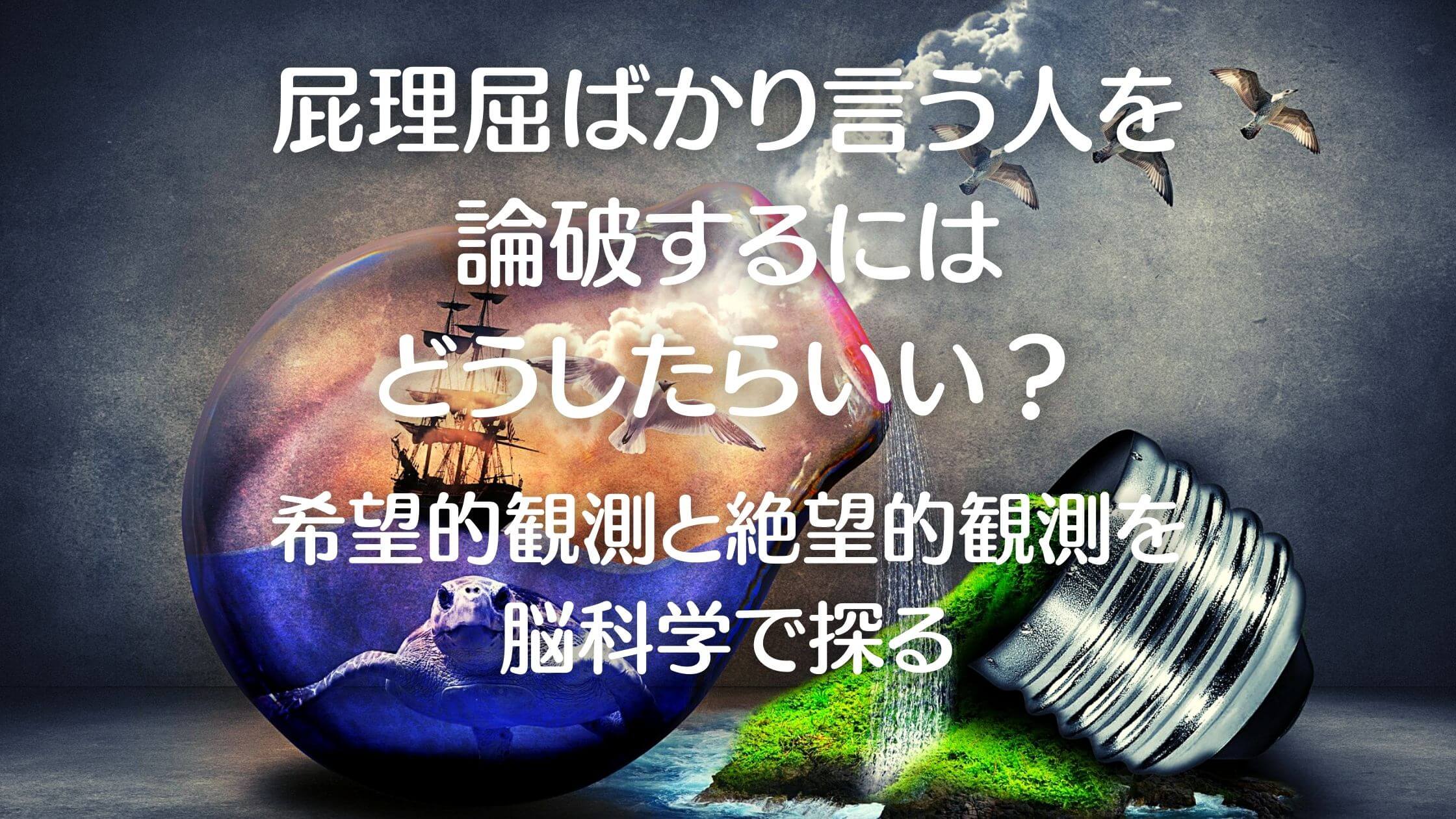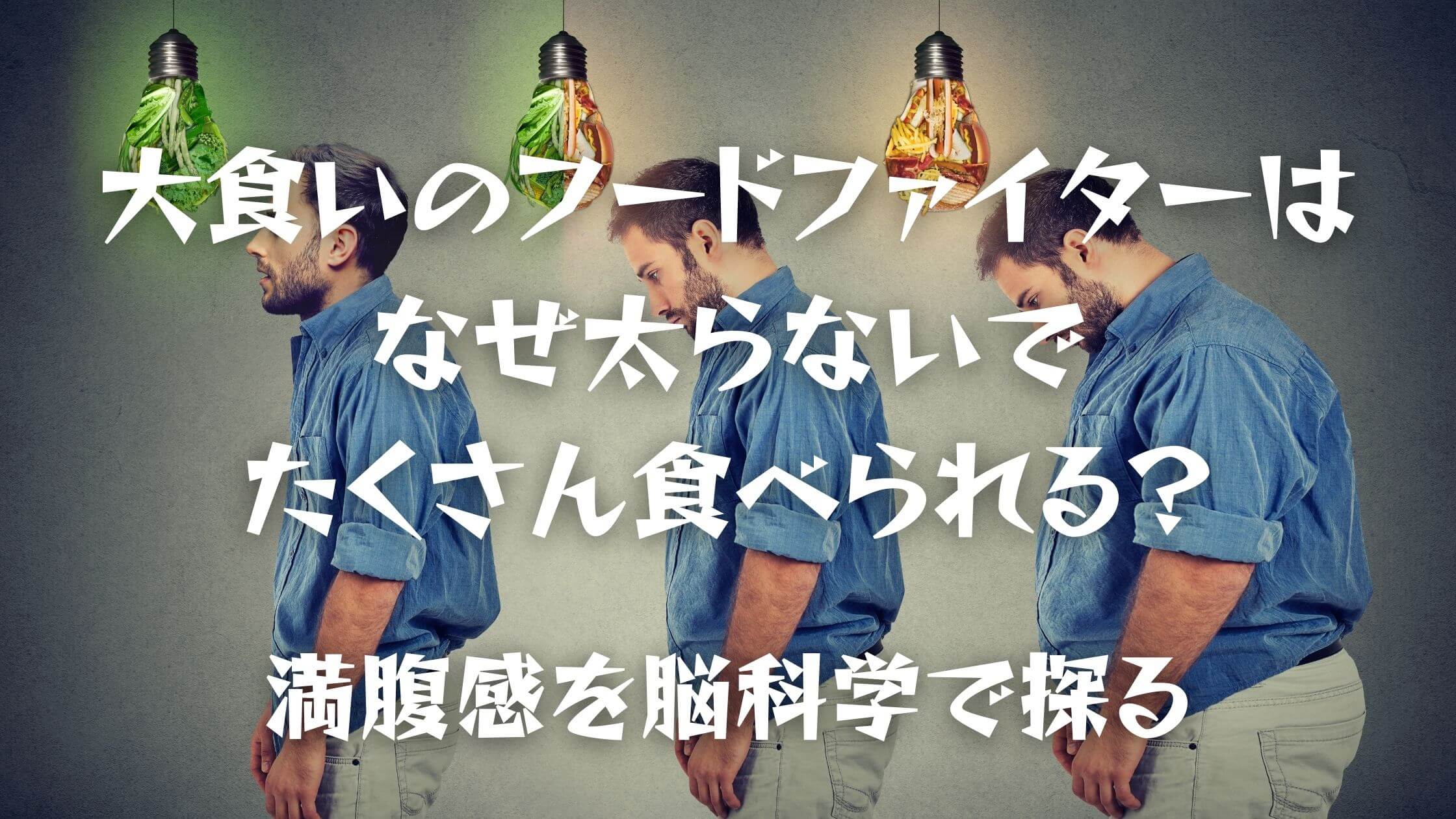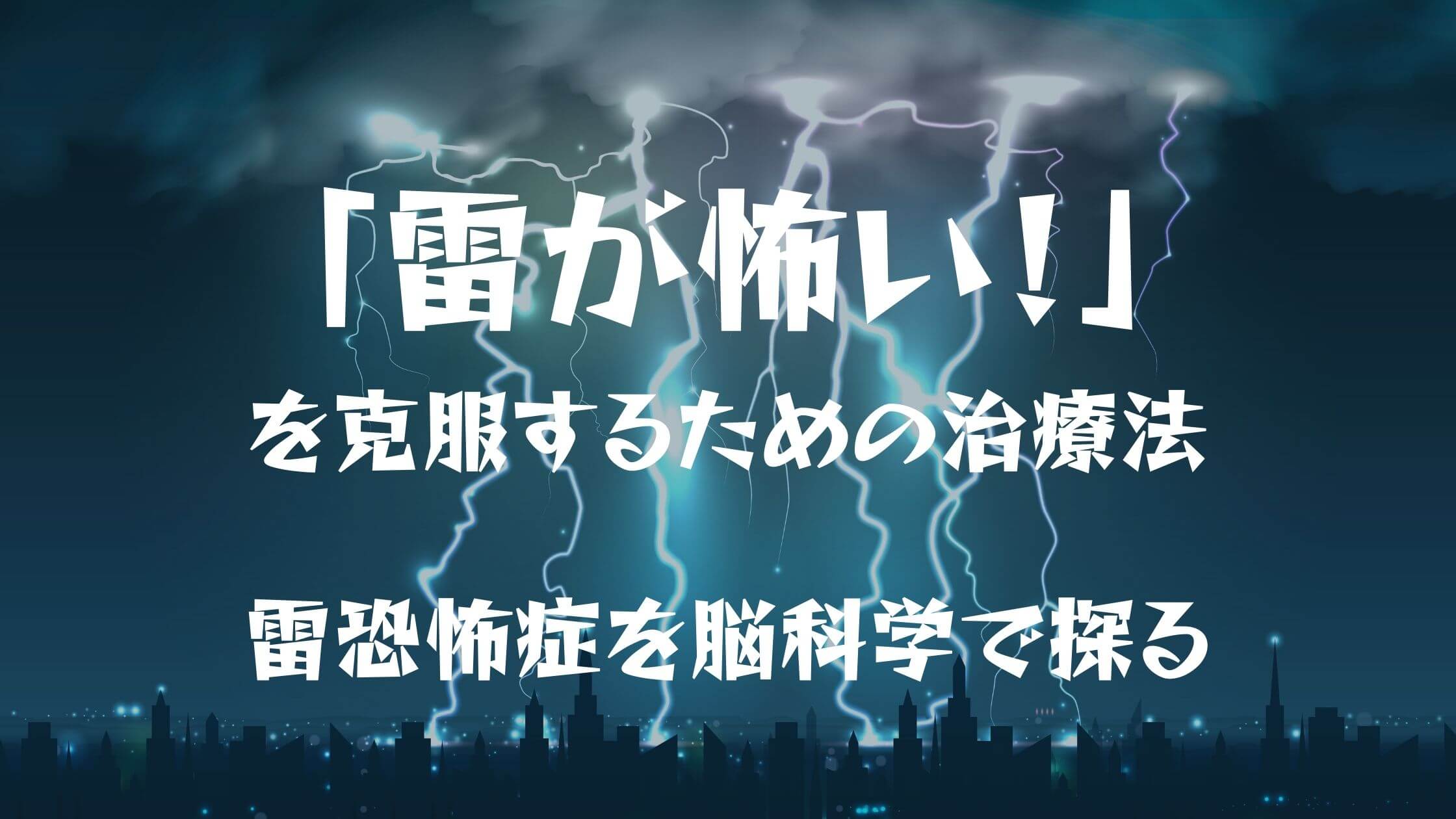なぜサウナ施設は、わざわざレディースデーを開催するのでしょうか?
レディースデーの日、女性の心と脳の中では何が起きているのでしょうか?
レディースデーは本当に儲かるのでしょうか、それとも“サウナ愛”だけでやっているのでしょうか?
女性限定サウナはなぜ人気で、脳にどんな影響があるのでしょうか?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。
この記事を読んでわかることはコレ!
銭湯・サウナ施設のレディースデーを脳科学で説き明かします。
第3次サウナブームと「ととのう文化」

銭湯・サウナ施設のレディースデーの脳科学
- 第3次サウナブームの流れの中で、「男性専用サウナに女性も入りたい」というニーズからレディースデー文化が生まれ、2010年代後半〜2020年代にかけて一気に広がりました。
- レディースデーは、女性が“ガチサウナ”の設備を安心して体験できる入口であり、施設側にとっては新規女性客の獲得や長期的なファン育成、ブランド力アップにつながります。
- 一方で、売上リスクやオペレーション負荷、アメニティ・清掃・マナー・健康面の対応など、現場には確かなデメリットや苦労も存在します。
- 心理学的には、レディースデーによって「心理的安全性」が高まり、仲間と一緒に行く安心感や“自分へのご褒美感”が生まれ、サウナ体験そのもののハードルが下がります。
- 脳科学的には、扁桃体の警戒レベルが下がって副交感神経が働きやすくなり、期待感でドーパミンが、共感とおしゃべりでオキシトシンが分泌され、“ととのう”体験が一段と心地よいものになります。
- レディースデーは、サウナを「おじさんの城」から「みんなの居場所」へとアップデートし、サウナ文化そのものを広げていくための“脳にも文化にもやさしい仕組み”として、これからも重要な役割を果たしていくと考えられます。
現代の日本では第3次サウナブームによって多くの施設がにぎわっています。
“サウナブームの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-

参考【サウナの脳科学】なぜ今サウナは人気なのか?サウナブームを脳科学で探る
なぜ今サウナはこれほどまでに人気でブームを巻き起こしているのでしょうか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20 ...
続きを見る
サウナの醍醐味(だいごみ)は何と言っても、サウナトランス=「サウナでととのう」でしょう。
温かいサウナと冷たい水風呂、休息タイムを繰り返す温冷交代浴では徐々に体の感覚が鋭敏になってトランスしたような状態になっていきます。
トランス状態になると、頭からつま先までがジーンとしびれてきてディープリラックスの状態になり、得も言われぬ多幸感が訪れます。
これがいわゆるサウナトランスであり、そして「サウナでととのう」の状態です。
”サウナでととのうの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
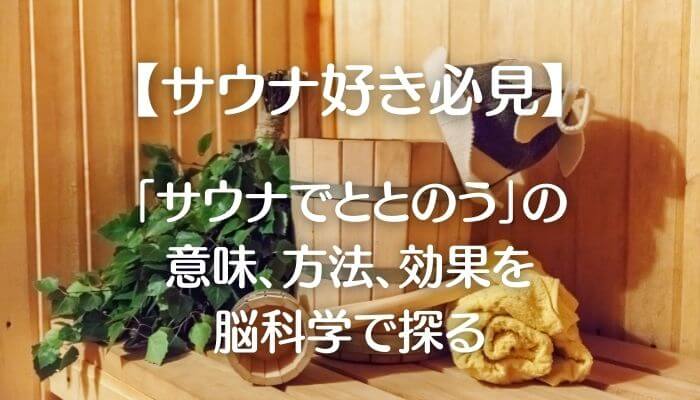
参考【サウナ好き必見】「サウナでととのう」の意味、方法、効果を脳科学で探る
「サウナでととのう」とは脳科学的にどのような意味や方法や効果があるのでしょうか?? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医 ...
続きを見る
…さて、そんな「ととのう」文化が広がるなかで、最近とくに熱いキーワードがあります。
それが 「レディースデー」 です。
男性専用のガチサウナが、ある日だけ突然“女子校”のようになる。
X(旧Twitter)やインスタでは、「レディースデー当たった!」「抽選ハズれた…」と悲喜こもごもの投稿が並び、人気施設では数分〜数時間で予約が埋まることも珍しくありません。
しかし、一歩引いて考えてみると、ここには疑問がたくさん隠れています。
「そんなに手間とリスクをかけてまで、なぜレディースデーをやるのか?」
「女性の心と脳の中では、いったい何が起きているのか?」
今回はその「レディースデー」を、脳科学と心理学の視点からじっくり掘り下げてみましょう。
「おじさんの城」から「みんなの居場所」へ

第3次サウナブームがレディースデーを生んだ背景
日本のサウナの歴史をざっくり振り返ると、昭和の“とにかく熱くて我慢”スタイルから始まり、健康ランドやスーパー銭湯での家族団らん時代を経て、今の第3次サウナブームに突入しました。
第3次ブームの特徴は、「ととのう」という主観的な体験が主役になったことです。
汗をかくだけの場所から、「仕事や人間関係で疲れ切った脳をリセットする場所」へと、サウナの意味づけが静かにアップデートされました。
その広がりの中で、若い世代や女性がサウナに入り始めます。
サウナ付きホテルに女子旅プラン、カップルでの個室サウナ、“サ旅”という言葉まで生まれ、サウナは「おじさんの嗜好品」から「おしゃれなウェルビーイングツール」へとイメチェンしていきました。
…とはいえ、現実のサウナ事情を見渡すと、都市部には今も「男性専用」「ほぼ男性しかいない」ガチサウナが数多く残っています。
ドアを開けると、仕事帰りのスーツ男子と出張中のビジネスマンがずらり。
サウナ好きの女性からすると、外観だけで心が折れてしまうことも少なくありません。

こういう“行きたいのに行けないジレンマ”が、女性サウナー側にじわじわと蓄積していきます。

普段は男性専用のサウナを、月に数日だけ女性に全開放してしまうという発想。
女性のニーズに応えると同時に、施設としても新しい客層を試せる、なかなか頭のいい一手です。
レディースデーはいつ頃から始まったのか?
では、このレディースデー文化はいつ頃から本格的に広がってきたのでしょうか。
もちろん「女性サウナ」という発想自体は昔からあり、1970年代にはすでに「サウナは男だけのものではない」という記事が出ていた記録もあります。
ただ、いま私たちがイメージするような、「男性専用サウナが、ある日だけ女性に解放される」「予約制・抽選制で争奪戦になる」という“レディースデー文化”が盛り上がり始めたのは、2010年代後半〜2020年代にかけてです。
たとえば東京・笹塚の「マルシンスパ」は、もともと男性専用の“天空のアジト”として有名でしたが、2017年前後から不定期で女性向けレディースデーを開催し、大きな話題になりました。
その後、上野の「サウナ・カプセル 北欧」、錦糸町「ニューウイング」、サウナセンターなどでもレディースデーが企画され、抽選倍率10倍クラスの“戦場”になっていきます。
銭湯サウナの世界にも波は広がり、たとえば品川区の老舗銭湯・富士見湯では、2022年に男湯側に本格サウナ「SAUNA FUJIMI」を増設したのをきっかけに、月1回・第2月曜のレディースデーをスタートさせています。
かるまる池袋のような“サウナテーマパーク系”でも、2022年ごろから定期的なレディースデーが組まれ、2024年には年間スケジュールとして月1ペースで女性開放日がアナウンスされるようになりました。
男性専用サウナ「PARADISE(三田)」のように、オープン当初から「毎月レディースデーをやる」ことを前提に設計している施設も出てきています。
つまり、「男性専用・男性比率の高いサウナが。第3次サウナブームで女性人気も高まったタイミングで2010年代後半〜2020年代にかけて、不定期→定期開催のレディースデーを導入し始めた」というのが、大まかな流れです。
レディースデーは、いきなり全国で始まったわけではなく、東京の人気サウナや“攻めている銭湯”が火をつけ、それを見た他の施設が「うちもやってみるか」と追随していった結果、今のような広がりになった――
そんな“草の根的ムーブメント”と言えるかもしれません。
サウナ施設がレディースデーをやる本当の理由

集客・話題づくり・ファン育成としてのレディースデー

まず、一番分かりやすいのは新しいお客さんとの出会いです。
男性専用サウナや男性比率が極端に高い銭湯では、女性にとって入店のハードルがかなり高めに設定されています。
そこでレディースデーを設けて、「この日は女性だけですよ。安心してどうぞ」と扉を開いてみる。
すると、SNSで名前だけ知っていた“憧れのサウナ”に、女性たちが一斉に流れ込んできます。
そこで味わうのは、普段の温浴施設ではなかなか出会えないレベルのサウナ環境です。
高温でしっかり熱いサウナ室、深くてキレのある水風呂、外気浴スペースのととのい椅子の数と配置。
ここで一度「本気のととのい」を経験してしまうと、脳はしっかりそれを覚えます。
その後どうなるかというと、男女利用可能な時間帯にも来てくれるようになり、系列店やサウナ付きホテルを選んでくれるようになり、ついでにSNSやブログで「推しサウナ」として布教してくれる。
レディースデーは、女性にとってのお試し体験であると同時に、施設にとっては中長期のファン育成プログラムでもあるのです。
さらに、レディースデーはやたらと話題になります。
「○○サウナ、レディースデーやるってよ」という情報はすぐ拡散し、抽選だの先着だのとなれば、Xやインスタのタイムラインは一気に賑やかになります。
これは、広告費をかけなくても、「女性に開かれたサウナ」というブランドイメージをつくる絶好のチャンスです。
そして、もっと現実的なことを言えば、「平日日中などの“デッドタイム”を女性客で埋められる」というメリットもあります。
もともとガラガラだった時間帯に、予約がきちんと入るようになれば、売上の“ムラ”も小さくなり、経営上の安定感が増します。
面白いのは、男性側にも意外とメリットがあることです。
レディースデーのおかげで施設の知名度が上がれば、結果的にサウナ自体が長く続いてくれる可能性が高まります。
なかには、「女性にもととのってほしいから、レディースデー賛成」という“サウナ紳士”もいて、サウナ愛は案外ジェンダーレスなんだな、と感じさせてくれます。
レディースデーのマイナス面と、あえてそれでも続ける理由

売上・手間・マナー問題…現場は楽じゃない
ここまで読むと、「レディースデー最高じゃん」と思えるかもしれませんが、現場のスタッフ目線に切り替えると、なかなか大変なことも多いです。
まず、シンプルに売上の問題があります。
普段から男性でぎっしりの時間帯を、そのまま女性専用に切り替えてしまうと、常連男性サウナーからは「その日は行けないのか…」という悲鳴も上がります。
さらに、レディースデーだからといって料金を割り引けば、一人あたりの単価も下がります。
超人気メンズサウナであればあるほど、「正直、短期的な売上だけ考えるとやらない方が得だよね…」という本音も見え隠れします。
次に、アメニティと清掃の問題があります。
女性が増えると、ドライヤー、鏡、コンセントの争奪戦が起きやすくなり、化粧水やクレンジング、コットンといった備品の減り方も加速します。
ヘアオイルやトリートメントの使用量が増えれば、排水のぬめりや床の汚れもそれに比例して増えていきます。
さらに生理用品の廃棄対応など、「普段あまり気にしなくてよかったポイント」が一気に増えます。
そして、どの施設でも頭を悩ませるのがマナー問題です。
“サウでのマナーの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-

参考【サウナの脳科学】脱衣所・浴室で“ついスマホ”してしまうのはなぜ?——サウナと脳科学で読み解くデジタル衝動の正体
なぜ人は「スマホ禁止」の表示を見ているのに、通知の震えに反射的に手が伸びてしまうのでしょうか。 なぜ“ととのい”の入り口で、現実よりも画面の向こうに心が引っ張られてしまうのでしょうか。 たった数十秒の ...
続きを見る
-
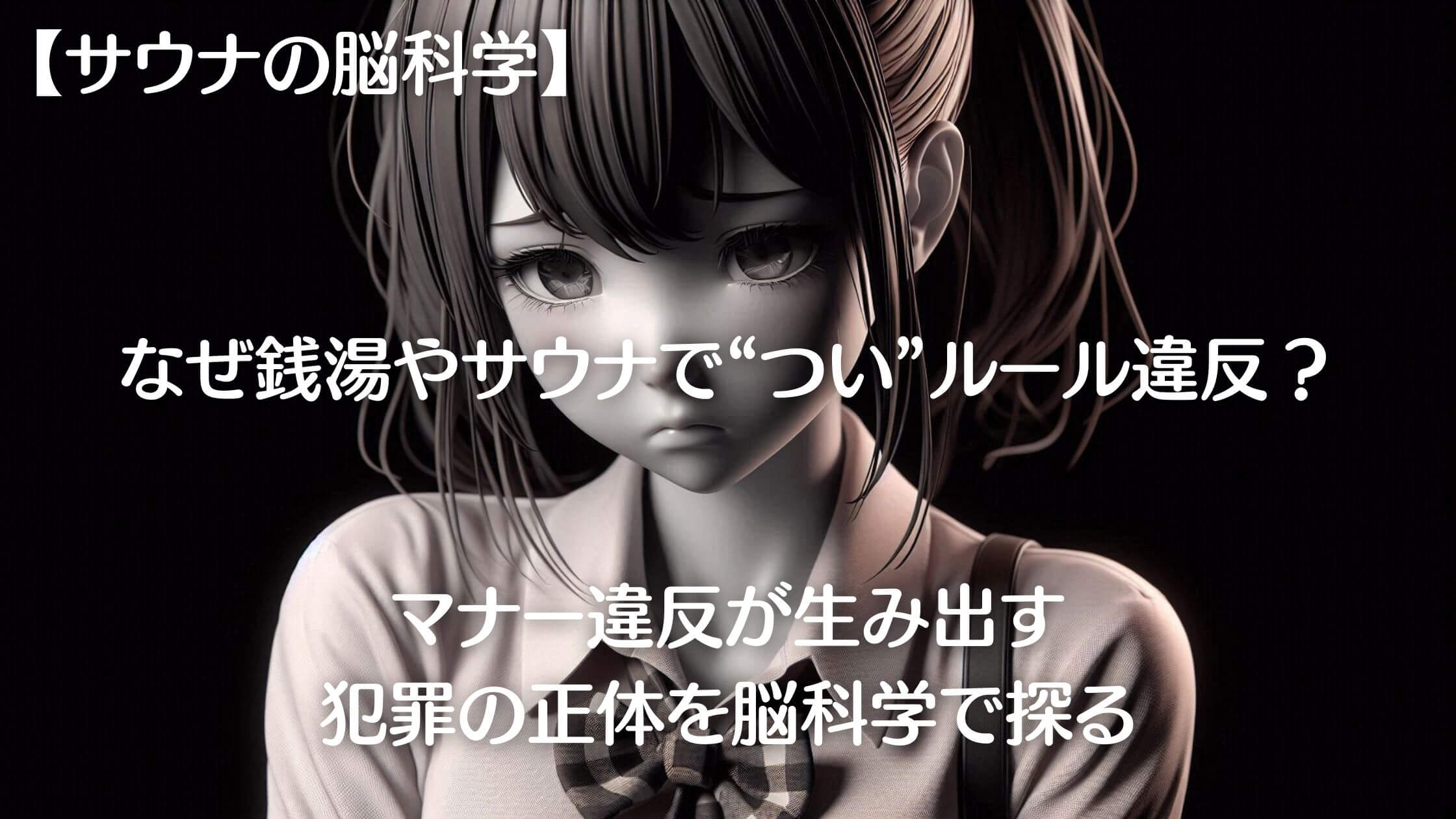
参考【サウナの脳科学】なぜ銭湯やサウナで“つい”ルール違反?~マナー違反が生み出す犯罪の正体を脳科学で探る
銭湯やサウナで“つい”ルール違反を犯してしまうのはなぜなのでしょう? 銭湯やサウナではどのような行為が犯罪にあたるのでしょう? マナー違反によって犯罪をおかしてしまう心理的、あるいは脳科学的要因はどこ ...
続きを見る
女子会ノリでおしゃべりが盛り上がりすぎると、静かに入りたい人のストレスが上がります。
写真や動画撮影はちょっとした写り込みがトラブルのもとになりますし、子連れ利用では水風呂が一瞬で「子どもプール」に変身することもあります。
レディースデーは「女性だけだから安全」という油断が逆にトラブルを呼び込むこともある、なかなか繊細なイベントです。
それでも、多くの施設がレディースデーをやめず、むしろ増やしているのはなぜか。
そこには、「サウナ文化の未来」に対する、少し長い目線があります。
女性サウナーという新しい仲間を増やすことで、サウナが“特殊な趣味”から“みんなのライフスタイル”へと変わっていく。
その変化を後押しするためのコストと考えれば、多少の赤字や手間は、将来への投資として許容しよう――。
レディースデーには、そんなサウナ側の“覚悟と優しさ”も含まれているのかもしれません。
レディースデーで女性の心に起きていること

心理的安全性、ご褒美感、仲間と一緒の安心感

まず大きいのが、「心理的安全性」がグッと高まることです。
知らない男性がたくさんいる空間だと、どうしても少し身構えます。
体型、肌、メイク、汗…頭の片隅でいろいろ気になってしまって、リラックスしきれない人も多いはずです。
レディースデーでは、周りは同じ目的の女性だけ。
スタッフも女性中心で、「今日は女子だけです」という空気がはっきりしています。
すると、「ここにいてもいいんだ」とか「多少お腹が出ていても、みんなお互いさまだよね」という感覚が生まれ、心のガードが一枚スッと下がります。
もうひとつのポイントは、「みんなで行くからこわくない」という仲間効果です。
レディースデーは、一人で行く方も大きいますが、友だちや同僚、母娘など、誰かと一緒に行くケースが多くなります。
心理的には、新しい場所や慣れない体験は一人だと不安が強くなりがちですが、仲間と一緒だと不安が半分くらいに薄まります。
「サウナ初心者だけど、友だちも初心者だし、まあなんとかなるでしょ」という、ちょっとした“連帯感のお守り”が働いてくれるのです。
さらに、レディースデー特有の「限定感」も、心に火をつけます。
月に数回だけ、予約が取れた人だけ、抽選に当たった人だけ。こうした条件が入ると、それはもはや単なる入浴ではなく、「自分へのご褒美イベント」に格上げされます。
仕事や家事、育児や介護など、日々いろいろなタスクを抱えている人ほど、この“セルフご褒美サウナ”の意味は大きくなっていきます。
レディースデーの脳科学

副交感神経、ドーパミン、オキシトシンで読み解く“ととのい”

レディースデーに参加した女性の脳と自律神経の中では、いったいどんなことが起きているのでしょうか。
まず注目したいのが、自律神経のバランスです。
自律神経には、戦う・逃げるモードの「交感神経」と、休む・回復するモードの「副交感神経」があります。
見知らぬ男性が多い空間や、視線が気になる環境では、どうしても交感神経寄りになりやすく、脳の中では「扁桃体」という不安や恐怖をチェックするセンサーが少しピリッと働いています。
レディースデーでは、その扁桃体の「警戒レベル」を下げる条件が整っています。
周りは女性だけ、ルールも明確、スタッフも優しくフォローしてくれる。
「ここは安心して汗をかいていい場所だ」と脳が認識すると、自律神経は少しずつ副交感神経優位へと傾いていきます。
その結果、心拍数が落ち着き、呼吸はゆっくりになり、筋肉のこわばりもゆるみやすくなります。
つまり、ととのうための身体の下地が自然に整っていくのです。
次に、ドーパミンの存在も見逃せません。
レディースデーは、行く前からちょっとしたイベントです。
予約開始の時間を狙ったり、抽選に申し込んだり、「サウナ飯どうする?」「どのロウリュ受ける?」と友だちと作戦会議をしたり。
こうした「もうすぐ楽しいことが起きそうだ」という予感は、脳内でドーパミンをじわっと上げていきます。
ドーパミンは、“やる気”と“ワクワク感”を司る代表的な神経伝達物質です。
このドーパミンがほどよく高まった状態で、熱いサウナ、冷たい水風呂、心地よい外気浴というジェットコースターのような身体体験をすると、脳の報酬系が気持ちよく揺さぶられ、あの「はぁ〜…生きててよかった…」という多幸感が生まれます。
さらに、レディースデーは“身体イメージの書き換え”にも関わっています。
普段の生活では、「汗だく」「すっぴん」「髪がぺたんこ」は、できれば避けたい状態かもしれません。
しかしレディースデーでは、それがデフォルトになります。
みんな同じように汗だくで、メイクを落とし、タオルを頭に乗せてフラフラととのい椅子に沈んでいる。
この「汗をかいている自分」を、恥ずかしいものではなく、「頑張った証拠」「気持ちよさの結果」と再解釈できると、身体に対するネガティブな感情が少しずつ和らぎ、自己肯定感がそっと底上げされていきます。
最後にもうひとつ、大事なホルモンがあります。
それがオキシトシンです。
サウナの後、休憩スペースやサ飯のテーブルで、「さっきのロウリュやばかったね」「水風呂何秒いけた?」「外気浴のあの椅子、もはや玉座だったね」と、どうでもいいけれど最高に楽しい会話が始まります。
こういう“体験の共有”や“共感のやりとり”は、オキシトシンの分泌を促し、ストレスを和らげ、「またこの人たちと一緒に来たいな」という気持ちを育てます。
レディースデーは、ただの入浴イベントではなく、脳内オキシトシンがゆるやかに増えていく、ちょっとした「心の回復セッション」でもあるのです。


まとめ:レディースデーはサウナ文化をアップデートする“脳にやさしい仕組み”
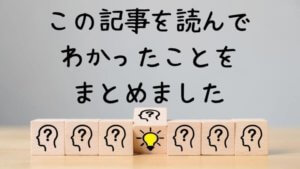
ここまで見てきたように、レディースデーは決して楽なイベントではありません。
売上のリスクがあり、清掃やアメニティの手間が増え、マナーや健康面での配慮も欠かせません。
現場スタッフからすれば、「普通営業のほうがよっぽどラクです…」という本音もあると思います。
それでもなお、銭湯やサウナ施設がレディースデーに挑戦し続けるのは、そこに「サウナの未来」への期待が込められているからです。
女性サウナーという新しい仲間を迎え入れることで、サウナは“おじさんの城”から“誰にとっても開かれた居場所”へと姿を変えていきます。
心理的には、不安や恥ずかしさをやわらげ、「ここにいていいんだ」と感じられる場を提供し、脳科学的には、副交感神経、ドーパミン、オキシトシンがうまく連携して、心と身体を同時に「ととのえ」ていきます。
レディースデーは、サウナが単なる「汗を流す場所」から、人と人、人と自分自身の関係を優しくつなぎ直す「脳にやさしい文化」へと進化していくための、大切な一歩なのかもしれません。
今回のまとめ
- 第3次サウナブームの流れの中で、「男性専用サウナに女性も入りたい」というニーズからレディースデー文化が生まれ、2010年代後半〜2020年代にかけて一気に広がりました。
- レディースデーは、女性が“ガチサウナ”の設備を安心して体験できる入口であり、施設側にとっては新規女性客の獲得や長期的なファン育成、ブランド力アップにつながります。
- 一方で、売上リスクやオペレーション負荷、アメニティ・清掃・マナー・健康面の対応など、現場には確かなデメリットや苦労も存在します。
- 心理学的には、レディースデーによって「心理的安全性」が高まり、仲間と一緒に行く安心感や“自分へのご褒美感”が生まれ、サウナ体験そのもののハードルが下がります。
- 脳科学的には、扁桃体の警戒レベルが下がって副交感神経が働きやすくなり、期待感でドーパミンが、共感とおしゃべりでオキシトシンが分泌され、“ととのう”体験が一段と心地よいものになります。
- レディースデーは、サウナを「おじさんの城」から「みんなの居場所」へとアップデートし、サウナ文化そのものを広げていくための“脳にも文化にもやさしい仕組み”として、これからも重要な役割を果たしていくと考えられます。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
最後にポチっとよろしくお願いします。