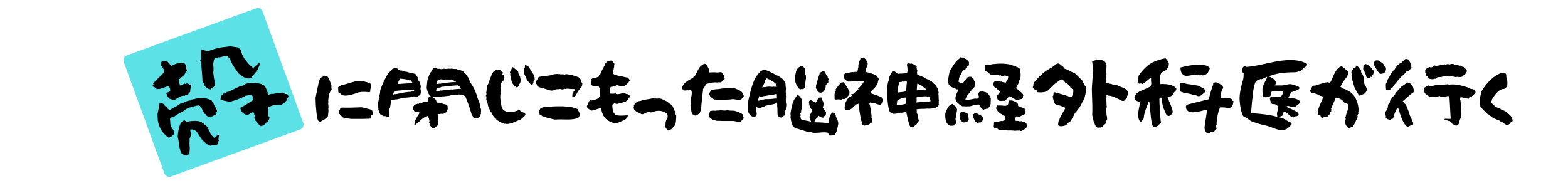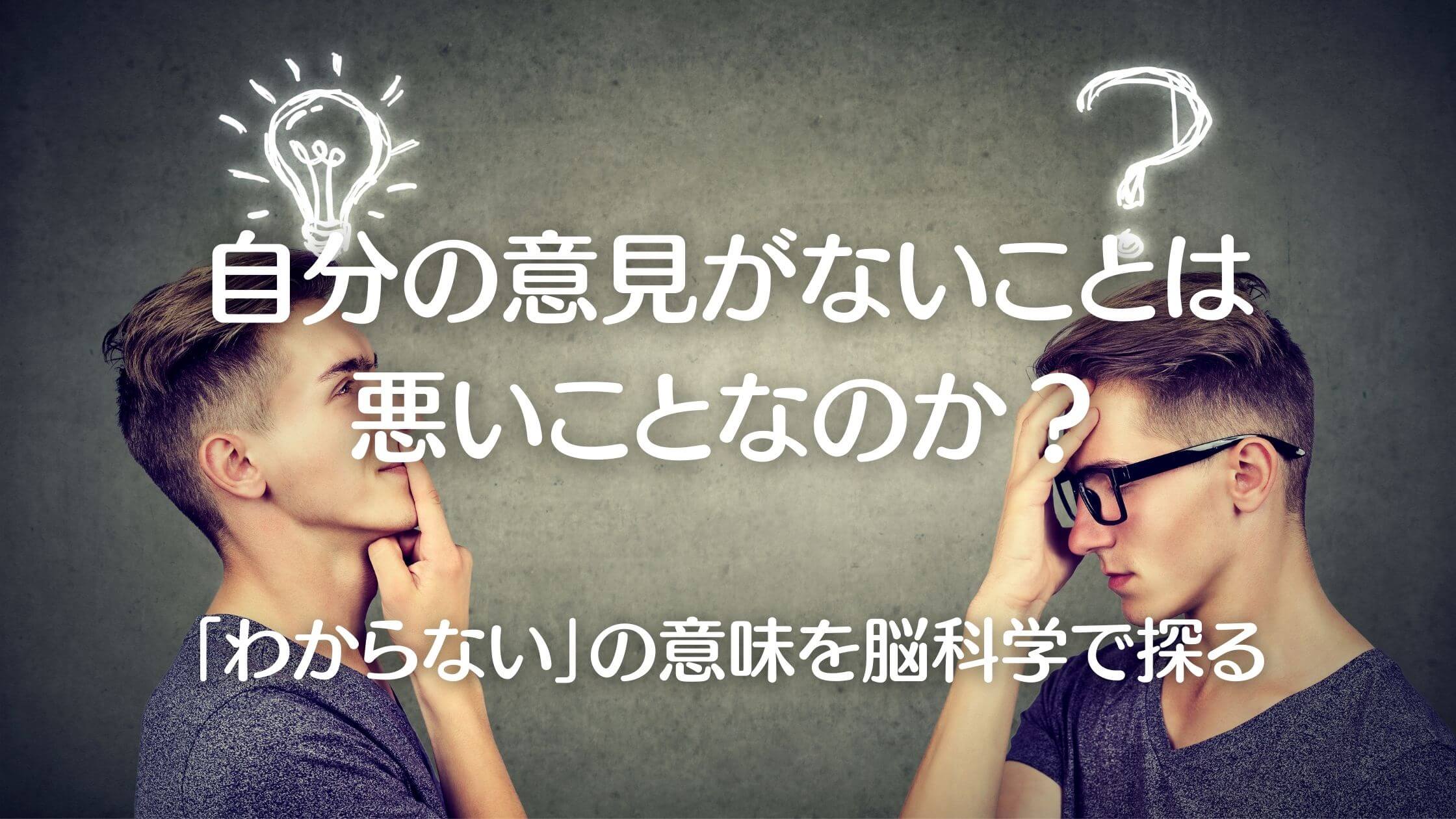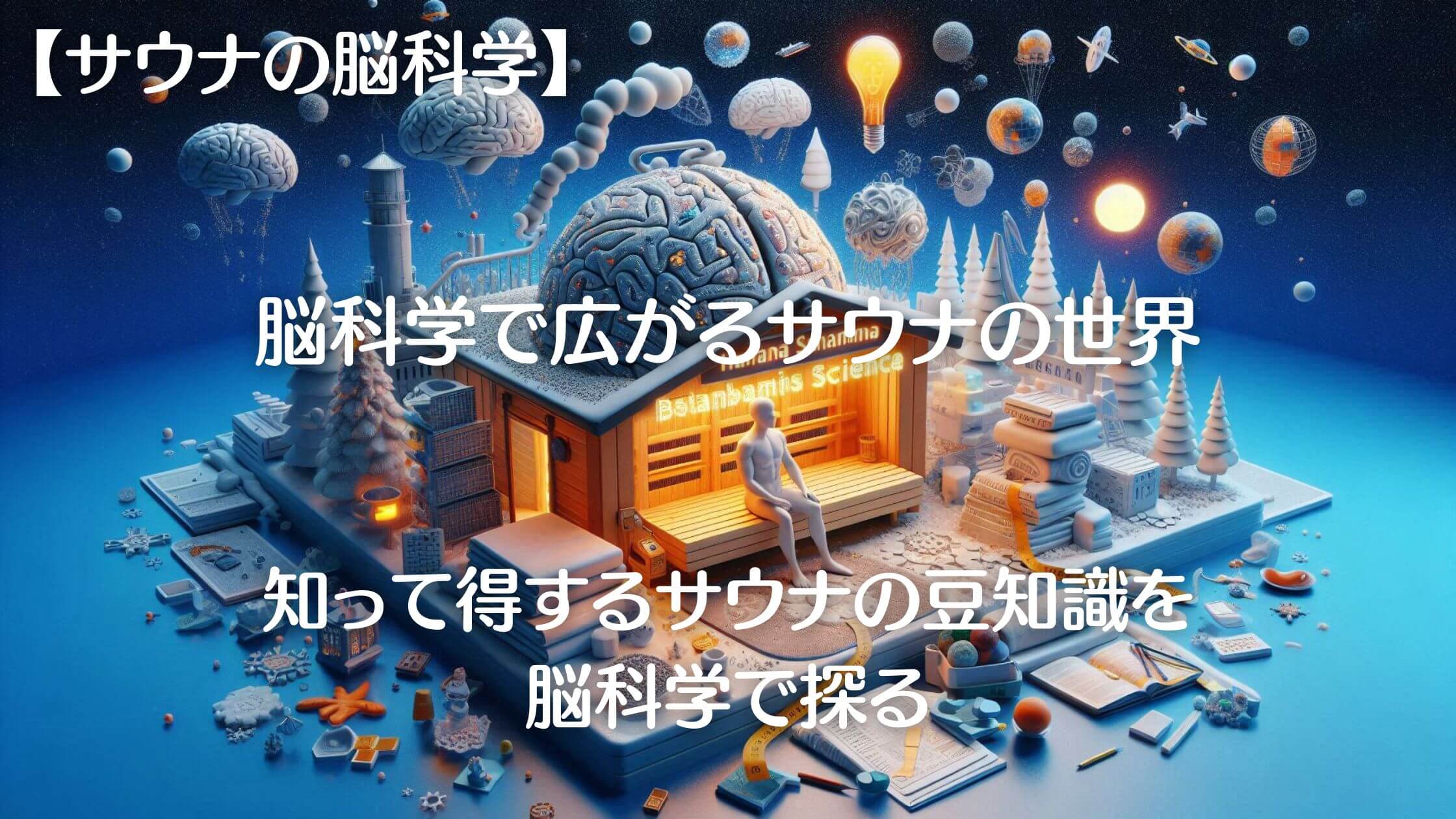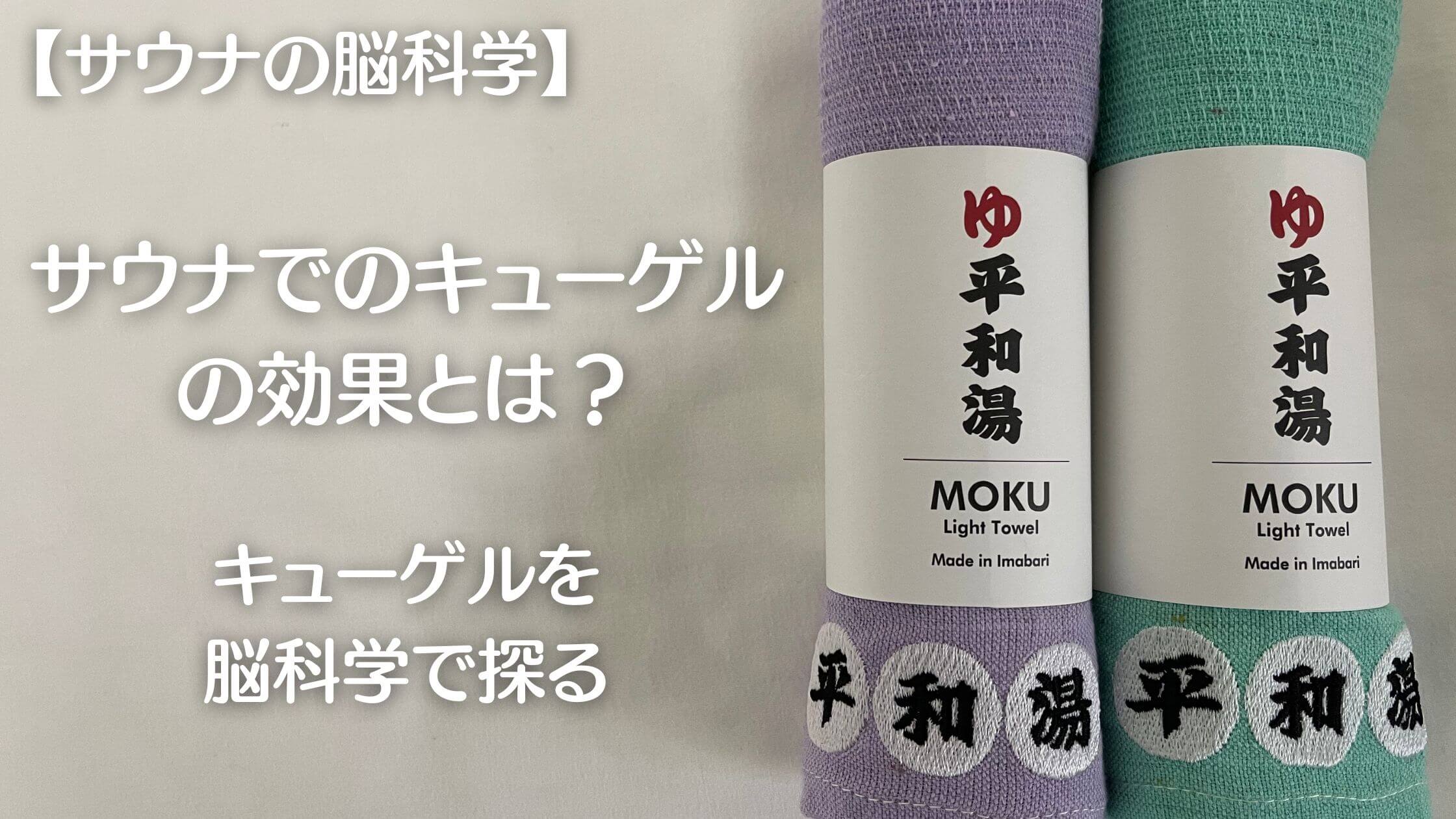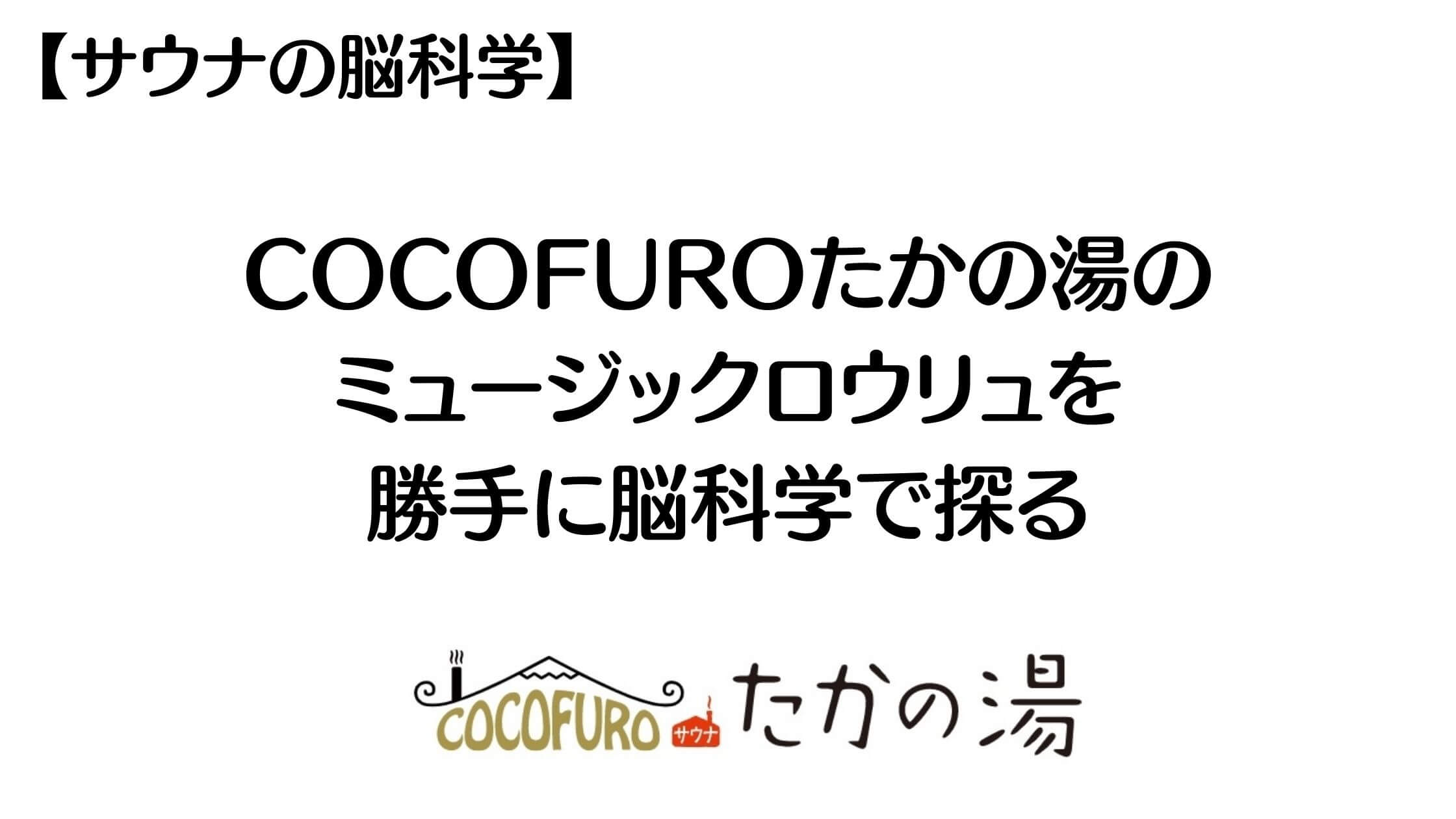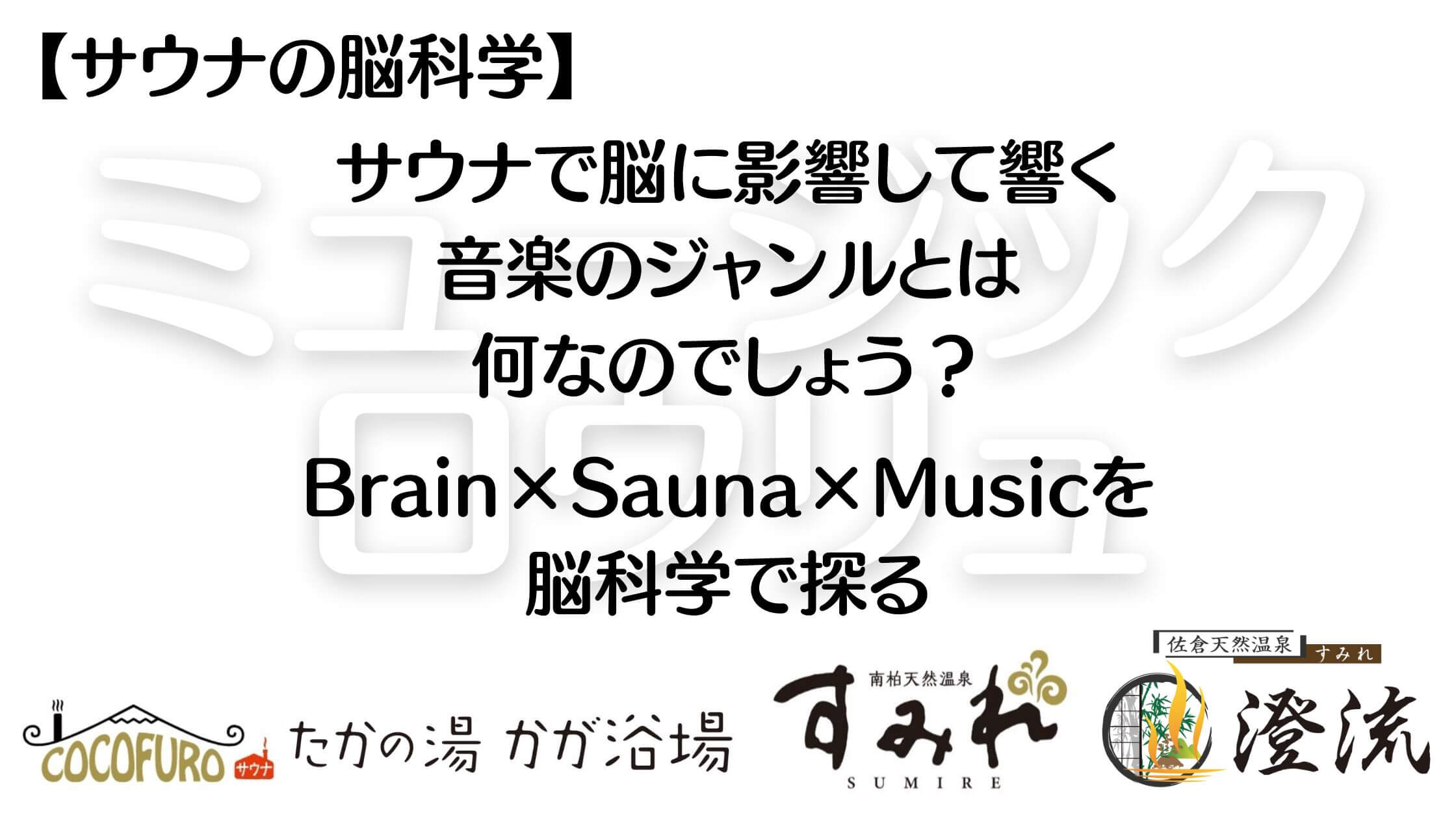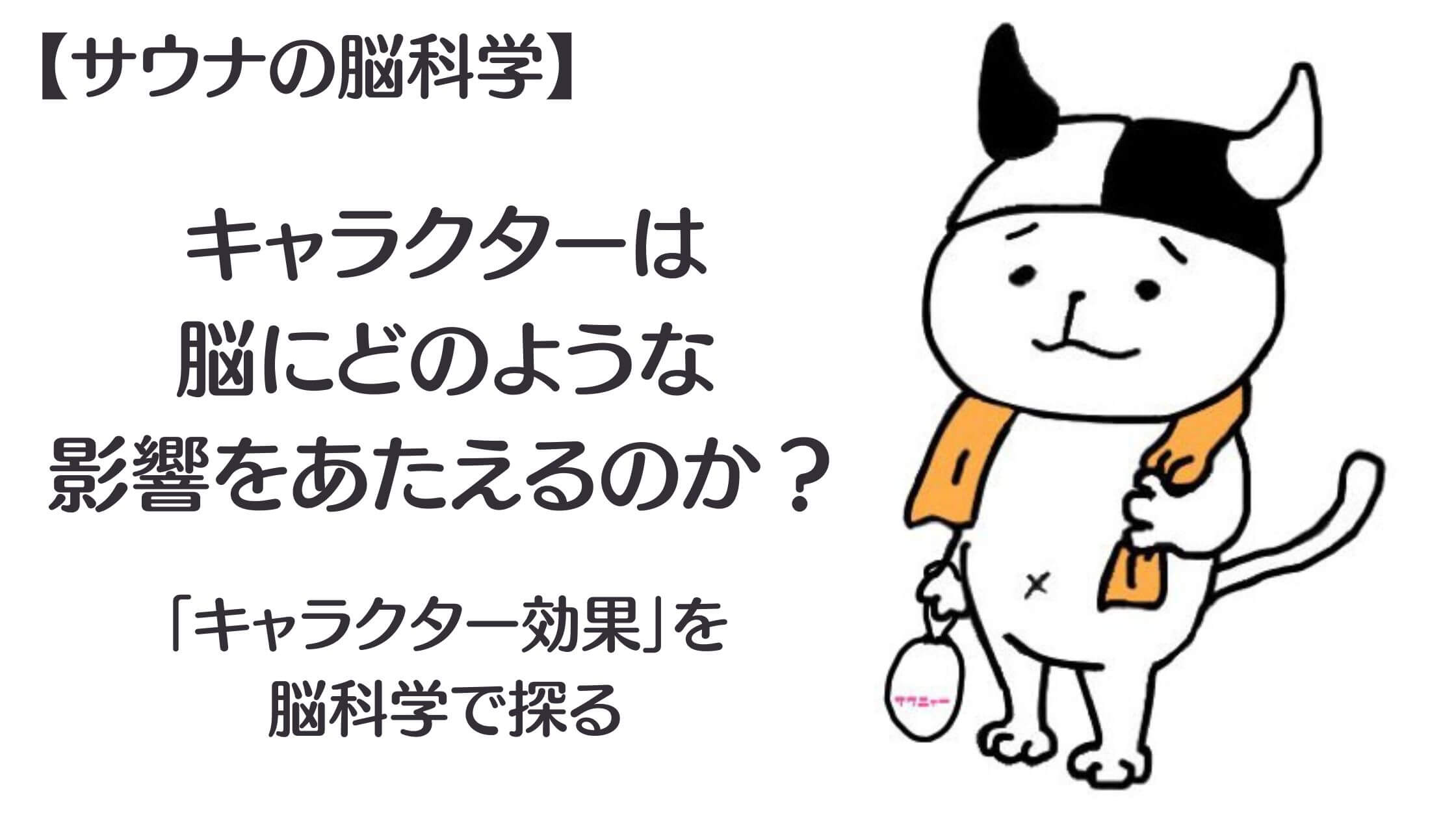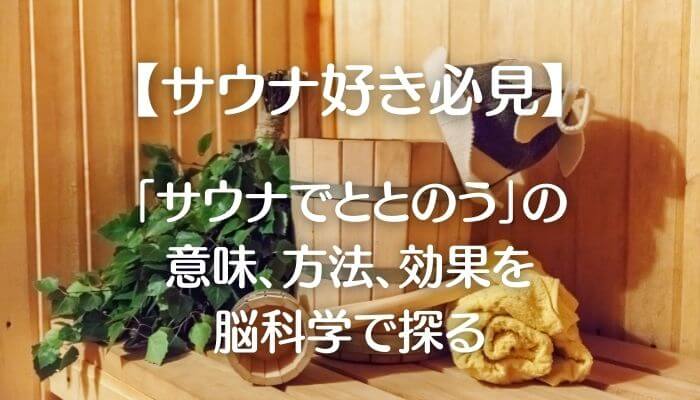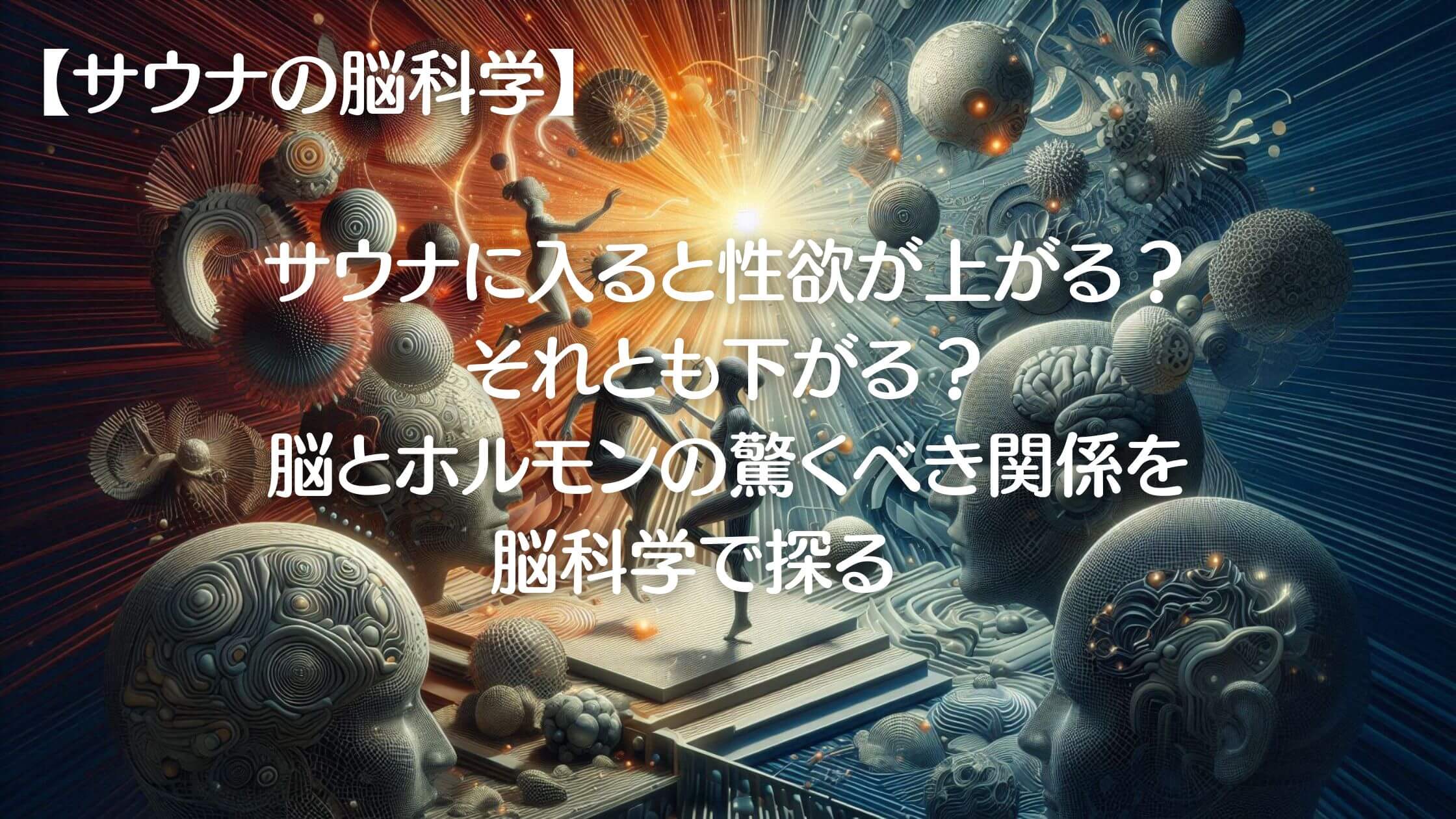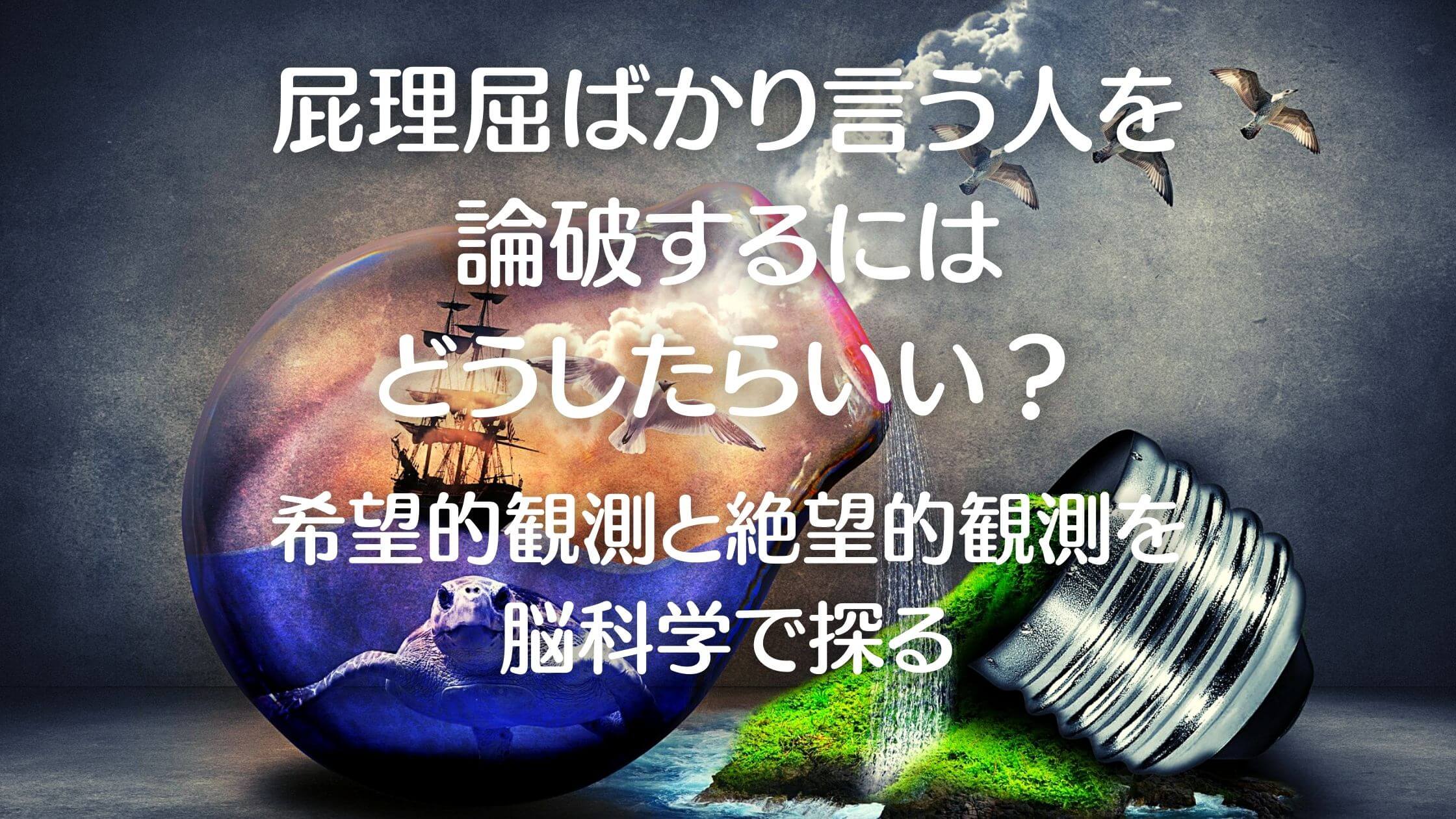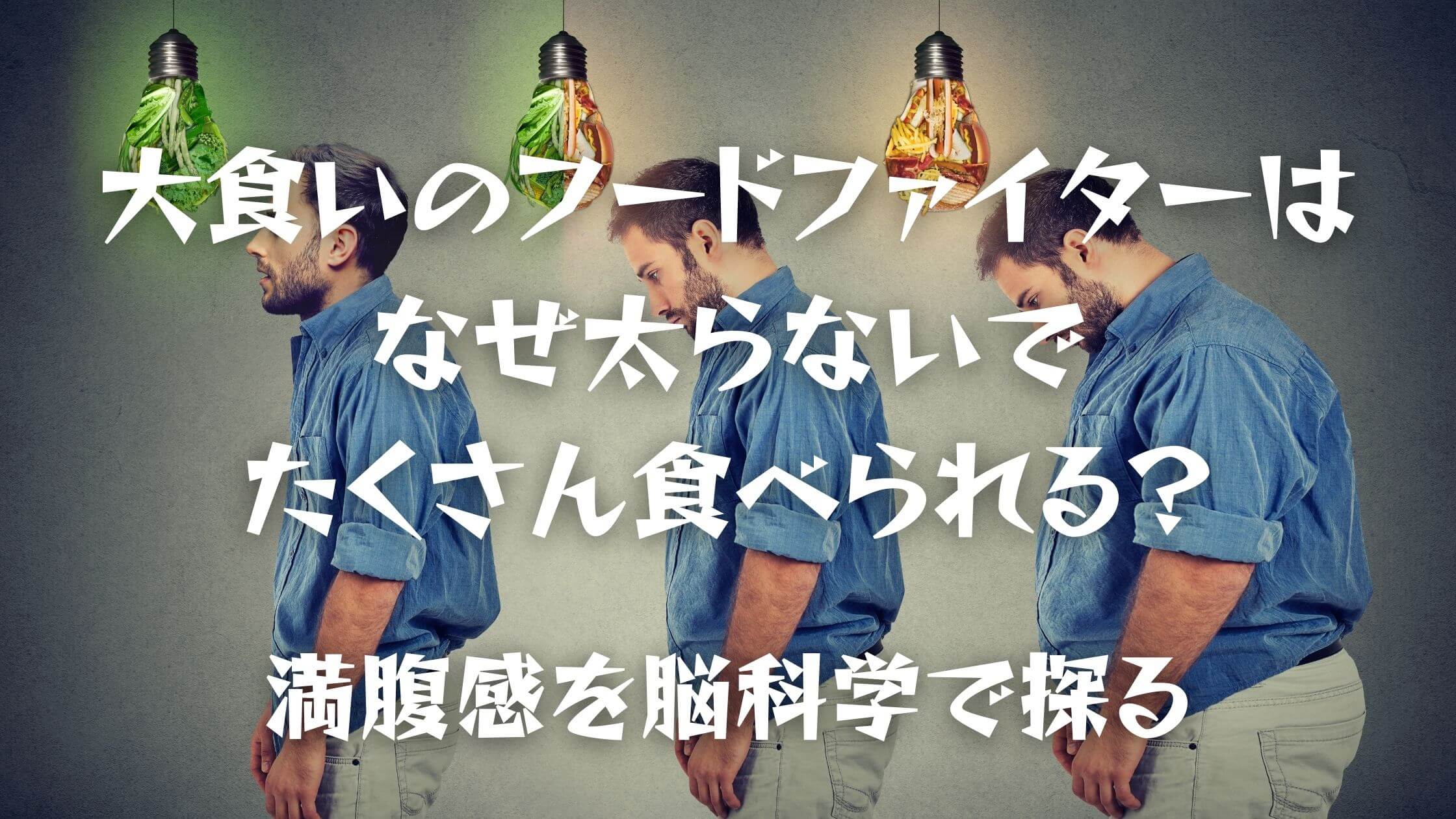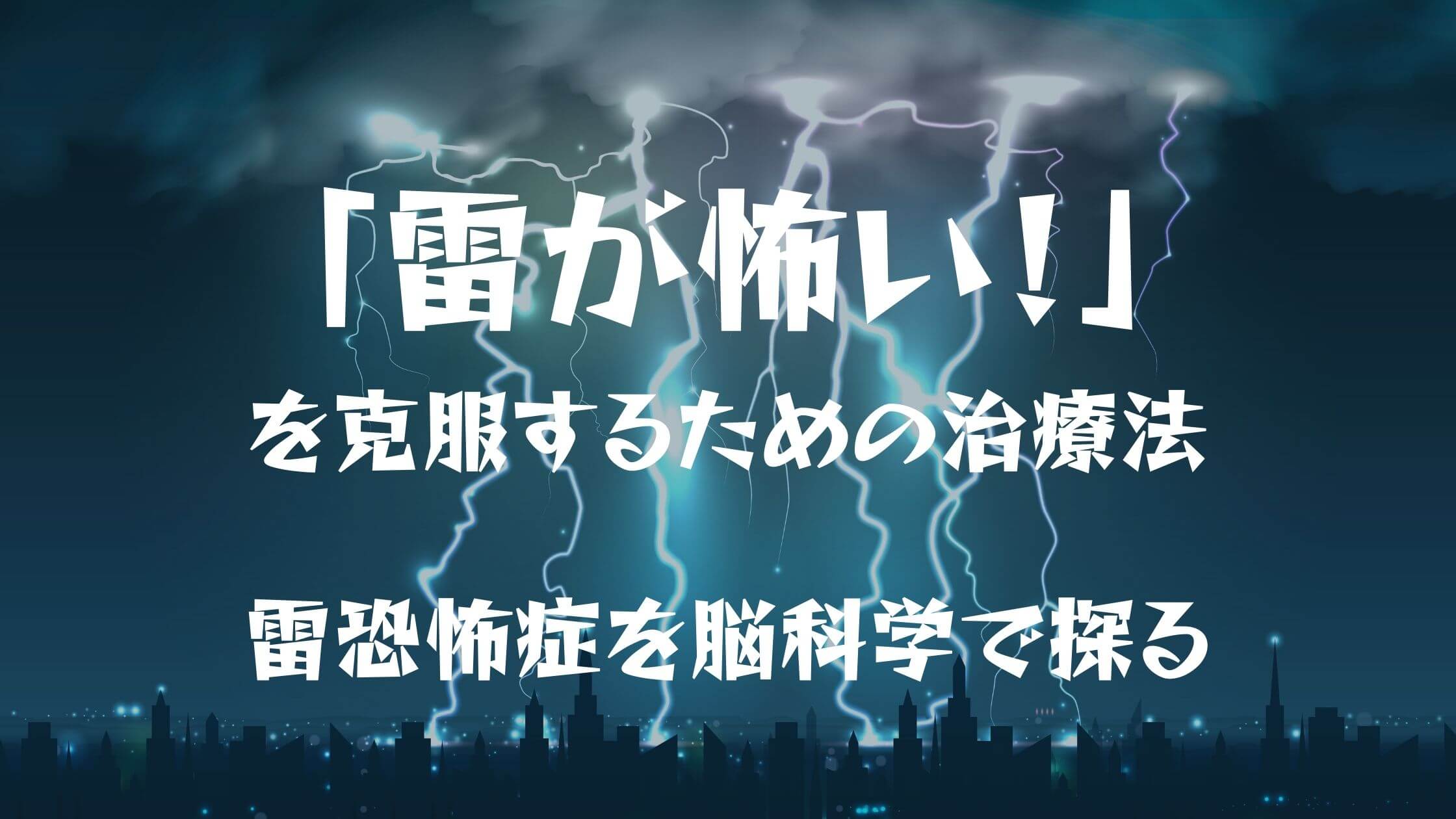自分の意見がないことは悪いことなのでしょうか?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。
この記事を読んでわかることはコレ!
- 自分の意見がなく「わからない」と答えてしまうことの意味をわかりやすく脳科学で説き明かします。
自分の意見がない人はダメな人?

わからない」の脳科学
- 自分の意見がなく「わからない」と答えることは、決して悪いことではありません。
- 脳の直感に頼ってその場しのぎの「自分の意見」を言ったところで何の意味もありません。
- 自分が自信をもって意見を発信できないような問題には、まずは「わからない」と答えましょう。
- 「わからない」の後に、時間をかけて落ち着いて確実な「自分の意見」を作り上げてから発信すればよいのです。


「自分の意見がない」と聞くと、多くの人はきっとネガティブな感情を抱くのではないでしょうか?
自分の意見がない人は、
自分に自信がないので意見を言って否定されたくない
他人の意見に合わせて嫌われないようにしている
恥ずかしがって自分の意見を言えない
そのように思われがちです。
そして最終的には、「自分の意見がない人はダメな人」といった印象を持たれてしまいます。


たとえば、
人類が地球温暖化を引き起こしたという説は真実なのだろうか?
遺伝子組み換え食品は本当に安全なのだろうか?
最低賃金はもっと引き上げられるべきなのだろうか?

専門家ならまだしも、普通の人にはとても複雑で難解な問題ばかりです。
専門家でもちゃんとした答えが出せるかは微妙でしょう。
“専門家の予測の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
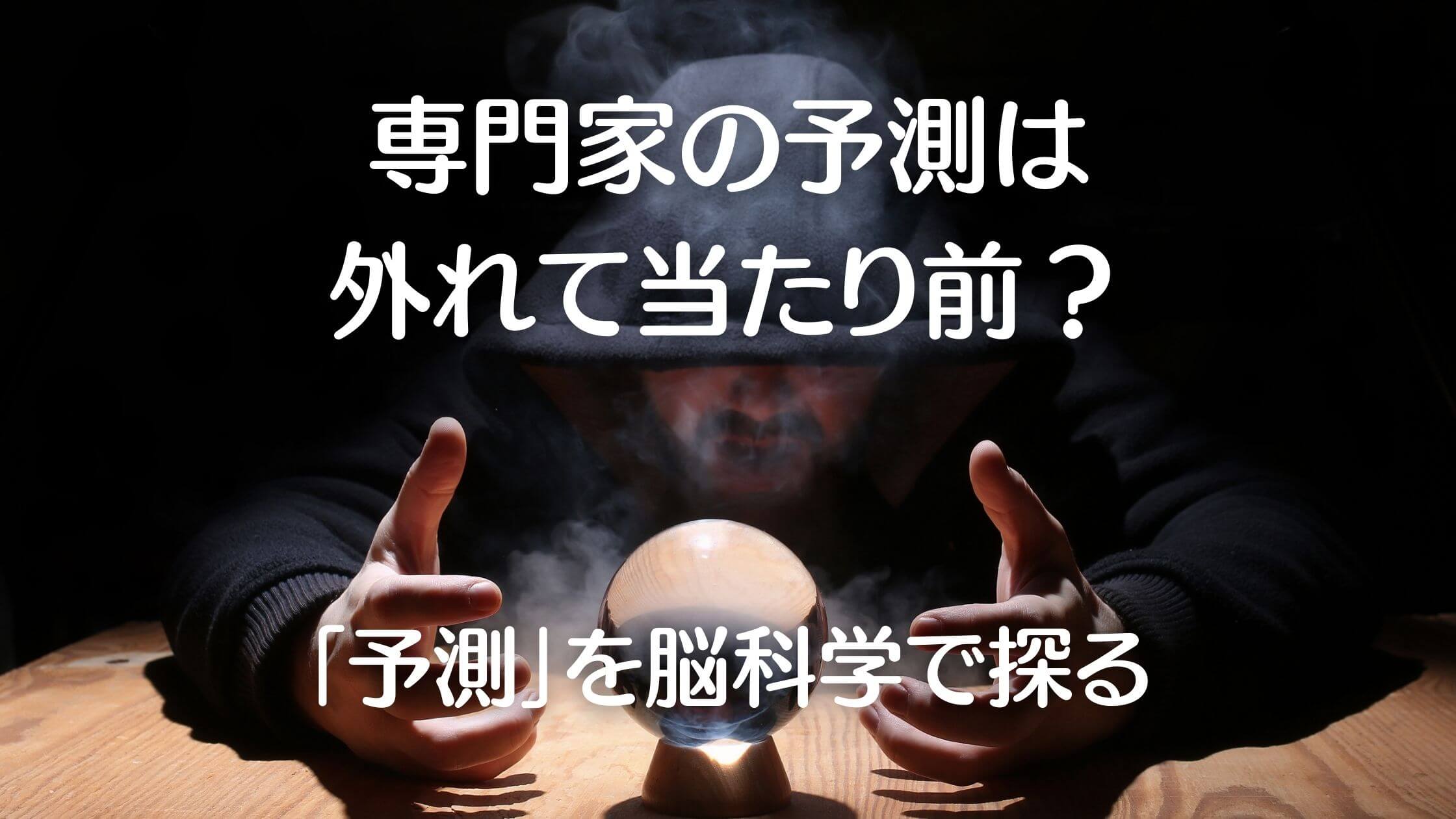
参考専門家の予測は外れて当たり前?「予測」を脳科学で探る
専門家の予測はなぜ外れてばかりで当たらないのでしょう? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病 ...
続きを見る
しかし、このような質問に対しても何かしらの自分なりの意見を発信する人がいます。
投げかけられた質問に対して、それが自分に関連があろうがなかろうが、複雑だろうが単純だろうが、そんなことは関係なく、個人的な見解を発信します。
一方で、「わからない」と答える人もいます。
「わからない」と答えるのは、とても勇気のいることです。
「わからない」と答えると、「自分の意見がない」と思われてしまうからです。
しかし無理やりにでも答えを出す方が本当に正しいのでしょうか?
「わからない」と答えるような、「自分の意見がない人」はダメな人なのでしょうか?

「自分の意見」を発信する時におちいりがちなワナ

脳は何か質問を投げかけられると何も反応しないということはほとんどありません。
脳の中ではひっきりなしに、何かに対する「自分の意見」を生み出しています。
きっとみなさんも無意識のうちに、
疲れた、だから休みたい。
あの人に声をかけたい、しかし何と声をかけたらいいかわからない。
あふれ出すように「自分の意見」が作り上げられています。

黙っていれば、「自分の意見がない人」ということになってしまいます。
「自分の意見がない人」になりたくない人は、無理やりにでも「自分の意見」を発信しようとします。

自分が興味のないテーマについて意見を発信してしまう
スポーツの世界についてまわるのがドーピング問題です。
オリンピックのような大きな国際大会が開かれると毎回この話題が登場します。
そして多くの人がドーピング問題に激しい怒りを感じているかのような意見を口にします。
テレビのニュースでは連日コメンテーターたちが怒りを爆発させます。
当然、その中にはスポーツに対して興味がないような人もたくさん混ざっています。
自分が興味のないことに対しては、ちょっとしたきっかけさえあれば思いもよらない意見が噴出しやすくなります。
そしてその意見のほとんどは無責任な発言です。
時にはその無責任な発言が他人を傷つけることさえあります。

自分が答えられない質問について意見してしまう
宇宙はいくつも存在するのか?
来年の夏の天気はどうなるのか?
そのような質問には誰も答えられません。
専門家でも無理な質問です。
“専門家の予想の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
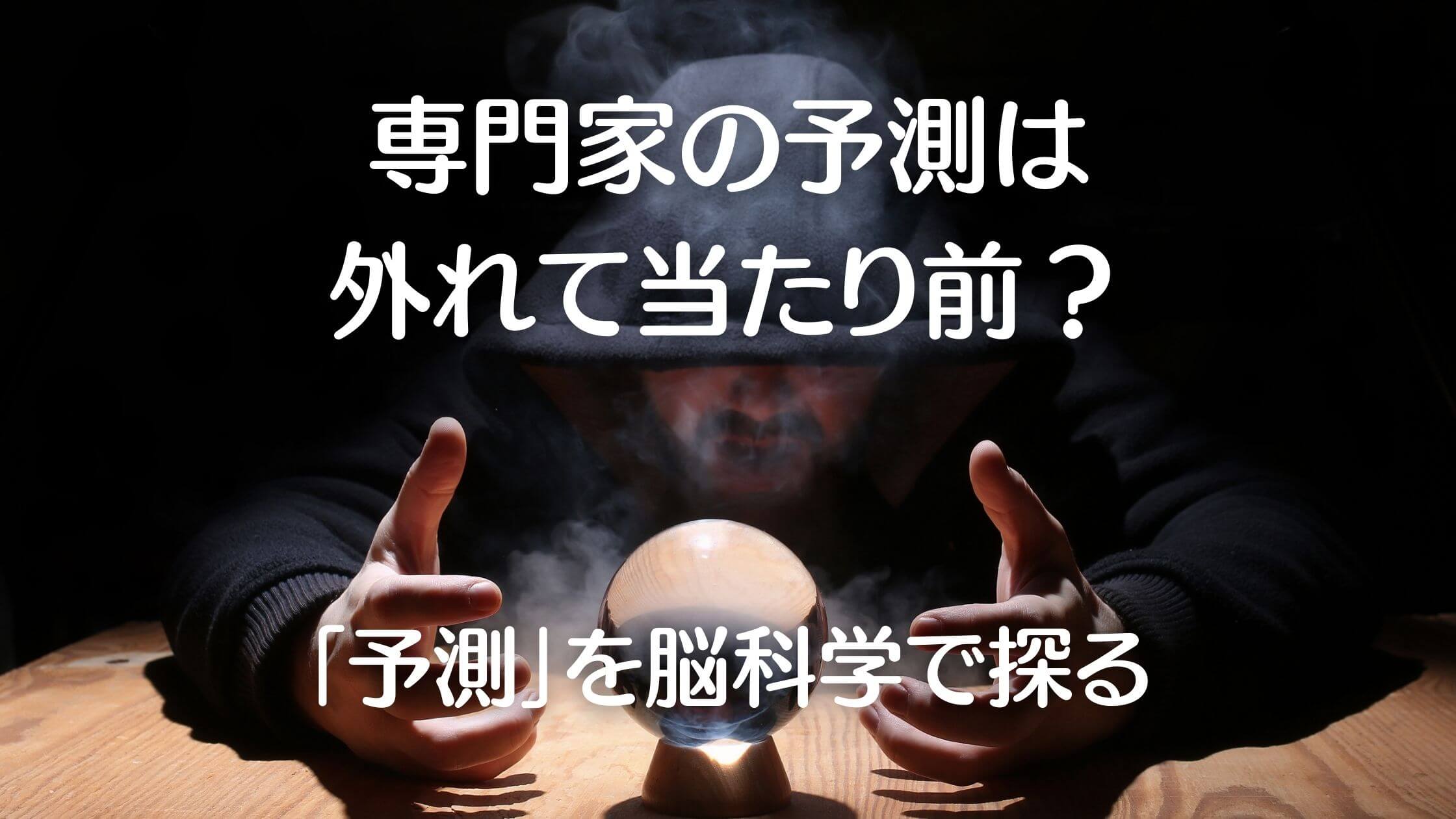
参考専門家の予測は外れて当たり前?「予測」を脳科学で探る
専門家の予測はなぜ外れてばかりで当たらないのでしょう? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病 ...
続きを見る
しかしそのような質問に得意げになって自分の意見を発信する人がいます。
そしてそれを信じる人がいます。
こうしてフェイクニュースは生み出されます。
“フェイクニュースの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
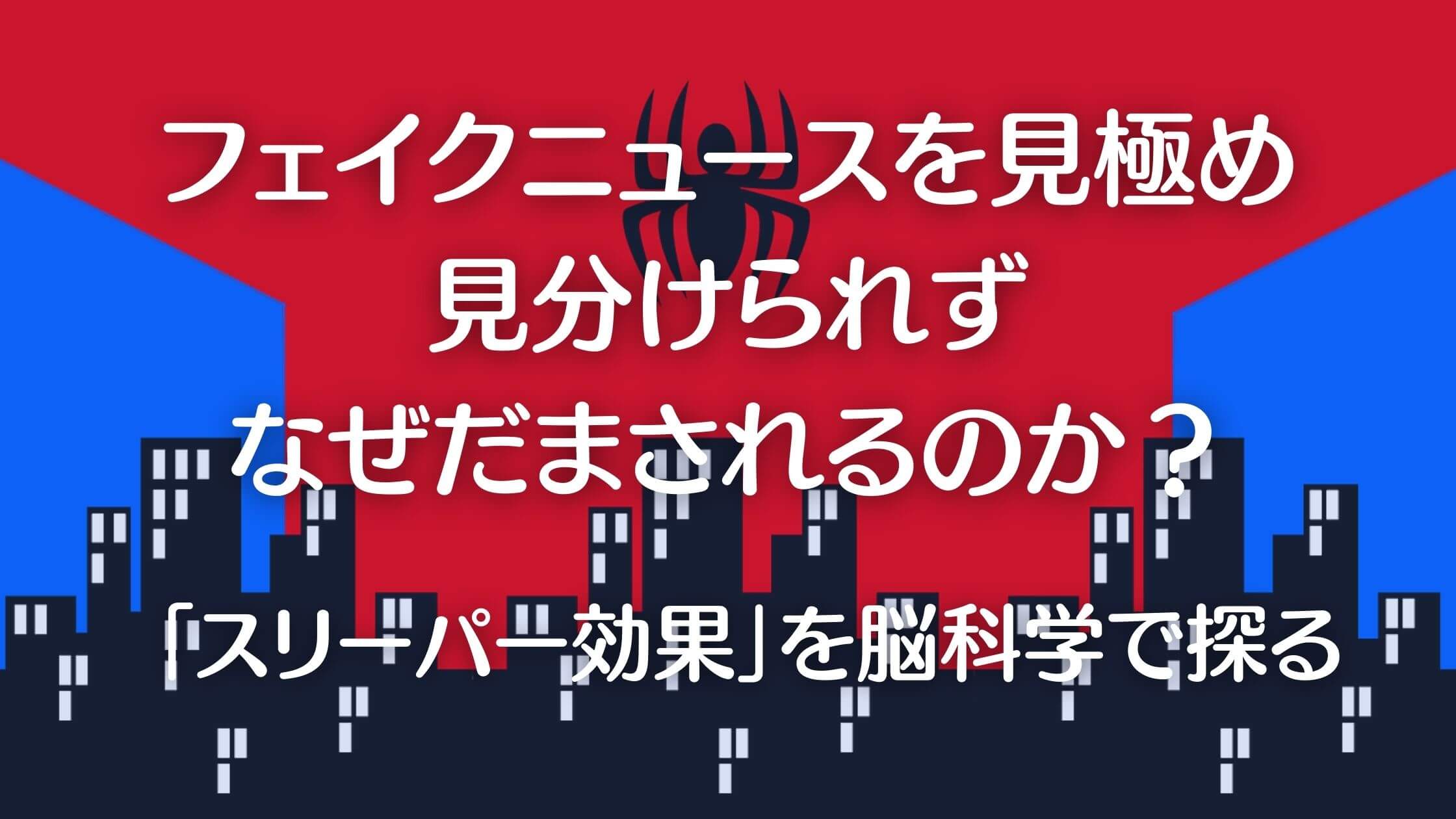
参考フェイクニュースを見極め見分けられずなぜだまされるのか?「スリーパー効果」を脳科学で探る
なぜフェイクニュースを見極め見分けることができずにだまされてしまうのでしょうか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医と ...
続きを見る

複雑な質問に急いで意見してしまう
最初にお話ししたような、
人類が地球温暖化を引き起こしたという説は真実なのだろうか?
遺伝子組み換え食品は本当に安全なのだろうか?
最低賃金はもっと引き上げられるべきなのだろうか?
専門家ならまだしも、普通の人にはとても複雑で難解な問題に対しても、脳は性急に意見を返そうとします。

しかしこれこそが「自分の意見」を発信する時におちいりがちな3つのワナの中でもっとも深刻なのです。

直感で意見を発信するのはやめよう
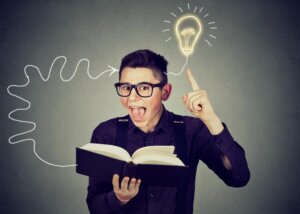
さきほどお話ししたように、専門家ならまだしも、普通の人にはとても複雑で難解な問題に対しても、脳は性急に意見を発信しようとします。
いわば直感で意見を発信し、そのあとで理性的に考え、自分の立場を裏付ける理由を探し始めます。

「ヒューリスティックス」とは、簡単に言えば自分の経験則や先入観に基づく手法です。
“ヒューリスティックの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-

参考知らないと損をする「ヒューリスティック」とは~経験則を脳科学で探る
経験則って正しいの? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた ...
続きを見る
直感に頼った意見の発信は実に素早く単純です。
一面的で「ポジティブ」か「」ネガティブ」、あるいは「好き」か「嫌い」の2択しかありません。
たとえば、ニュースで殺人事件の犯人の顔を見たとします。
すると脳は直感的に「この顔は嫌い」と判断します。
そして「嫌い」ということが前提で、自分の意見がどんどん湧き上がってきます。
週末の天気予報は晴れのようです。
すると脳は直感的に「ポジティブ」な意見を湧き上がらせます。
このような直感に頼った意見はほとんどの場合正しい意見です。
しかしそれは質問が単純明快であった場合のみです。
複雑で難解な質問に対しては、直感的に頼った意見に正しいものはほとんどありません。
それでも、わたしたちはそれを「正しい意見」と勘違いしてしまうのです。
さらに直感があっという間に出した意見をどうにか正当化しようと、脳をフル回転させて裏付けとなる理由を探し始めます。
すでに自分の意見は発信してしまっているので、いまさら取り消すことはできません。
なんとか「正しい意見」であることを証明しなくてはなりません。
複雑で難解な問題の答えを出すにしてはずいぶんお粗末に思えるかもしれませんが、これが現実なのです。
「直感で意見を発信するのはやめよう」とみなさんにお伝えしたいのは、このように早とちりして間違えた意見を発信してしまうことが最大の理由ですが、実ばもうひとつ理由があります。
それは、もし常に自分の意見を発信しなければならないという呪縛(じゅばく)がなければ、精神的にリラックスして、平静な気持ちで、よりよい自分の意見を生み出せることです。
「精神的な落ち着き」はよい人生を送るための大事な条件のひとつです。
では「直感で意見を発信する」ことをやめるにはどうしたらよいのでしょう?
それは「直感で意見を発信してはいけない問題用のバケツ」を脳の中に持っておくことです。
「自分が興味のないテーマ」や「自分が答えられない質問」や「複雑で難解な問題」に直面したら、性急に意見を発信するのではなく、とりあえずそのバケツに放り投げてみてください。
バケツの中の問題は、時間がある時に落ち着いてじっくり考えてから自分の意見を見つけ出せばよいのです。
もし自分の意見が見つからなくてもまったく問題はありません。
これらの問題はあくまでも「自分の意見」を発信する時におちいりがちなワナであり、あえてそのワナにはまり込むことはないからです。
自分の意見がなく「わからない」と答えて何が悪い!

「自分が興味のないテーマ」や「自分が答えられない質問」や「複雑で難解な問題」を投げかけられて、あなたの意見を求められたらどうしますか?
このような問題には「直感で意見を発信する」のはよくないことと説明しました。
ではどうしたらよいのでしょう?
答えは簡単です。
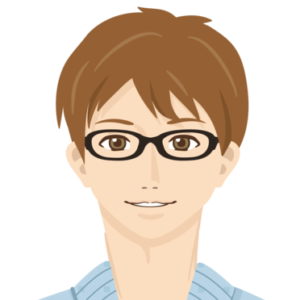
そのように答えればよいのです。
きっと相手は、




そうつめ寄ってくるかもしれません。
しかし相手の調子に合わせる必要などありません。
「自分が興味のないテーマ」や「自分が答えられない質問」や「複雑で難解な問題」に対して「わからない」と答えることは、何も恥ずかしいことではありません。
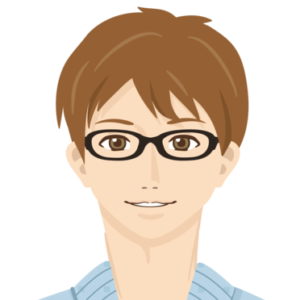
そのように思う人もいるかもしれません。
しかし「わからない」と答えることは「知能の低さ」の表れではなく、逆に「知性の高さ」の表れです。
現代社会が抱える問題は、情報の過多ではなく、意見の過多と言えるでしょう。
ありとあらゆることに意見を発信しなければならない世界は生きづらく窮屈(きゅうくつ)なものです。
脳の中のバケツに入れられた問題に対して、無理やり自分の意見を発信したところで、そのほとんどは間違えているわけで、しかも間違えた意見を正当化しようとすることなど時間の無駄以外なにものでもありません。

あなたが「わからない」と答えても、世界はちゃんと回り続けます。
そしてきっと今まで感じたことのない解放感を得られるはずです。
「わからない」の先にこそ「自分の意見」がある

「自分が興味のないテーマ」や「自分が答えられない質問」や「複雑で難解な問題」に対して「わからない」と答えることは何も問題はありません。
しかしなんでもかんでも脳の中のバケツに放り込んで、自分の意見を発信することを放棄していては、自分が失われてしまいます。
“自己中心の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
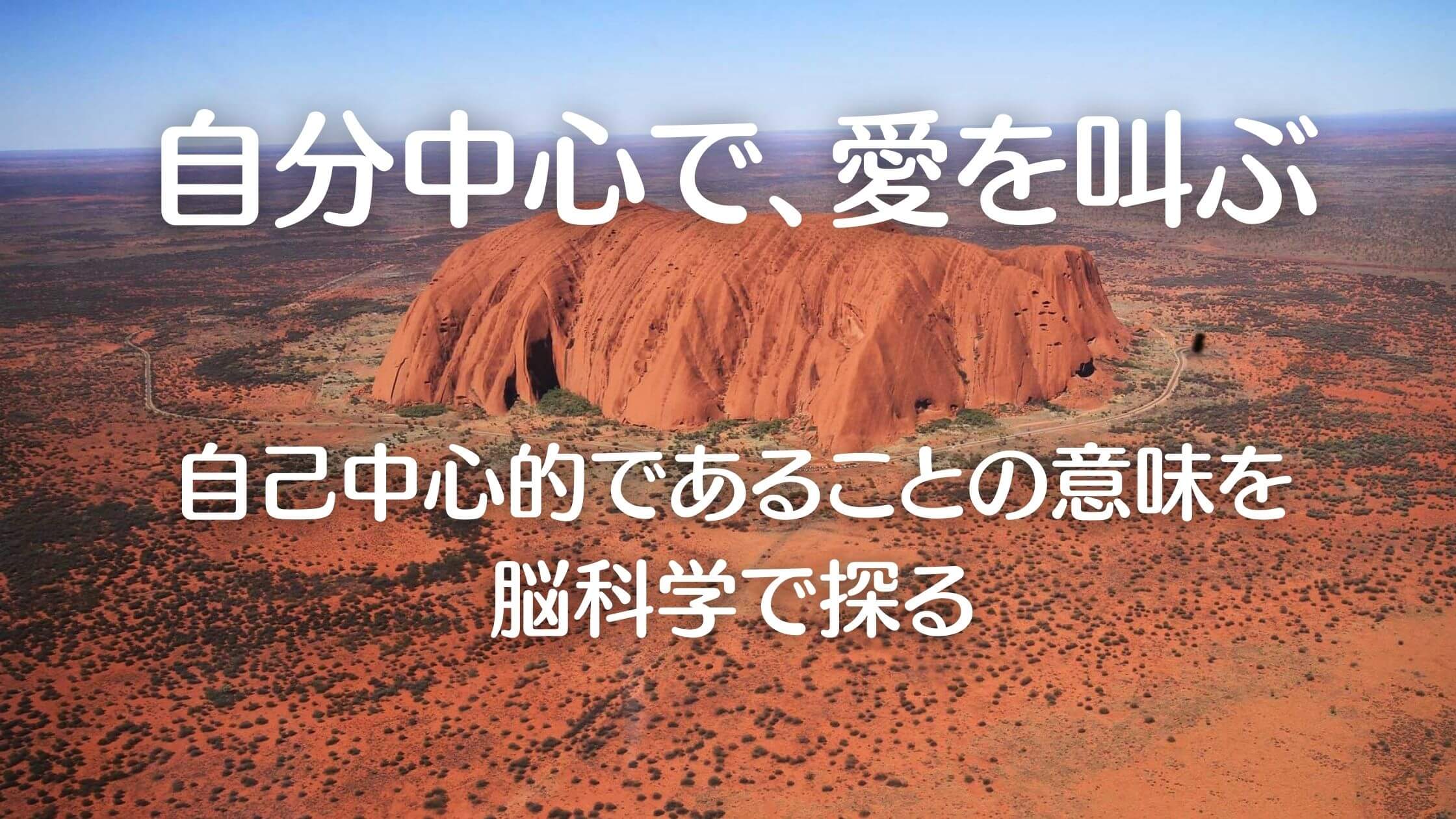
参考自分中心で、愛を叫ぶ~自己中心的であることの意味を脳科学で探る
自己中心的な人ってどんな人? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年…多くの脳の病気と向き合い勤務医として働い ...
続きを見る
本当に「自分の意見」を作り上げるべき時は、まずは「わからない」と答えたとしても、そのあとで時間をかけて落ち着いて「自分の意見」を発信すべきです。

「書く」という行為は脳の中の考えを整理したい時の王道です。
取りとめのない考えも、文章にすれば自然とクリアになってきます。

そうやって「自分の意見」がはっきりしたら、あわてて発信するのではなく、まずは自分なりにチェックしてみてください。
あなた自身で自分の意見を論破できるかどうか試してみるのです。
そうすれば「自分の意見」の確実性を高めることができるはずです。

実際に「自分の意見」として発信しても、本当に重要な意味を持つ意見など1%程度にすぎません。
それ以外の99%は不要な意見にすぎず、聞き流されるのがおちでしょう。
あなたの意見が他人に尊重されるのは、あなたが「自分の意見」に自信をもって雄弁に語った時だけです。
自分が今までどのように「自分の意見」を発信してきたのか、ちゃんと「わからない」をうまく使いこなせてきたのか、一度立ち止まって考えてみてください。


“「わからない」の脳科学”のまとめ
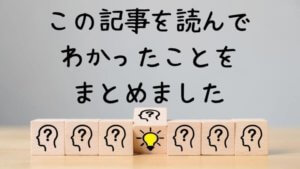
自分の意見がなく「わからない」と答えてしまうことの意味をわかりやすく脳科学で説き明かしてみました。
今回のまとめ
- 自分の意見がなく「わからない」と答えることは、決して悪いことではありません。
- 脳の直感に頼ってその場しのぎの「自分の意見」を言ったところで何の意味もありません。
- 自分が自信をもって意見を発信できないような問題には、まずは「わからない」と答えましょう。
- 「わからない」の後に、時間をかけて落ち着いて確実な「自分の意見」を作り上げてから発信すればよいのです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわりのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
最後にポチっとよろしくお願いします。