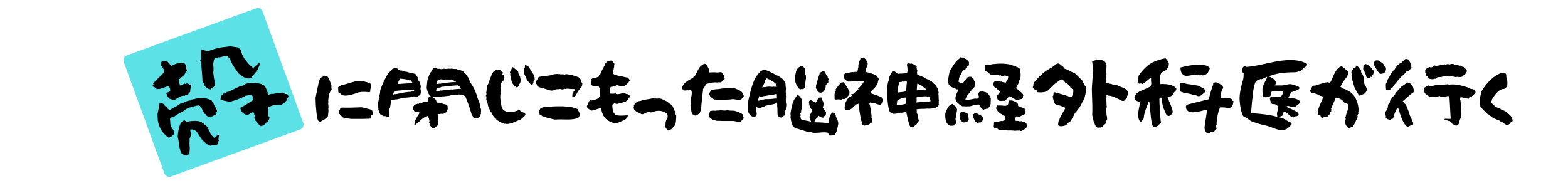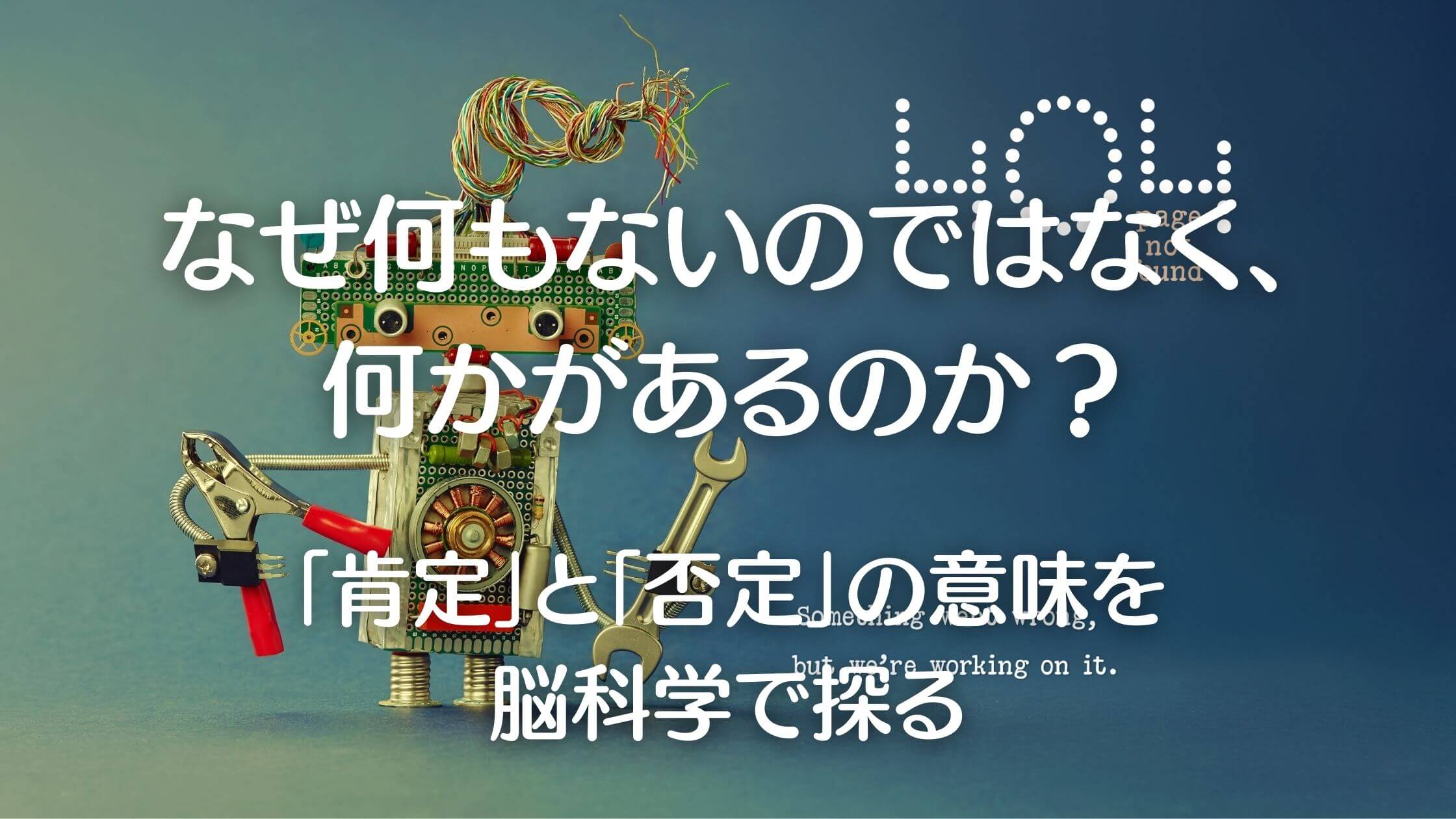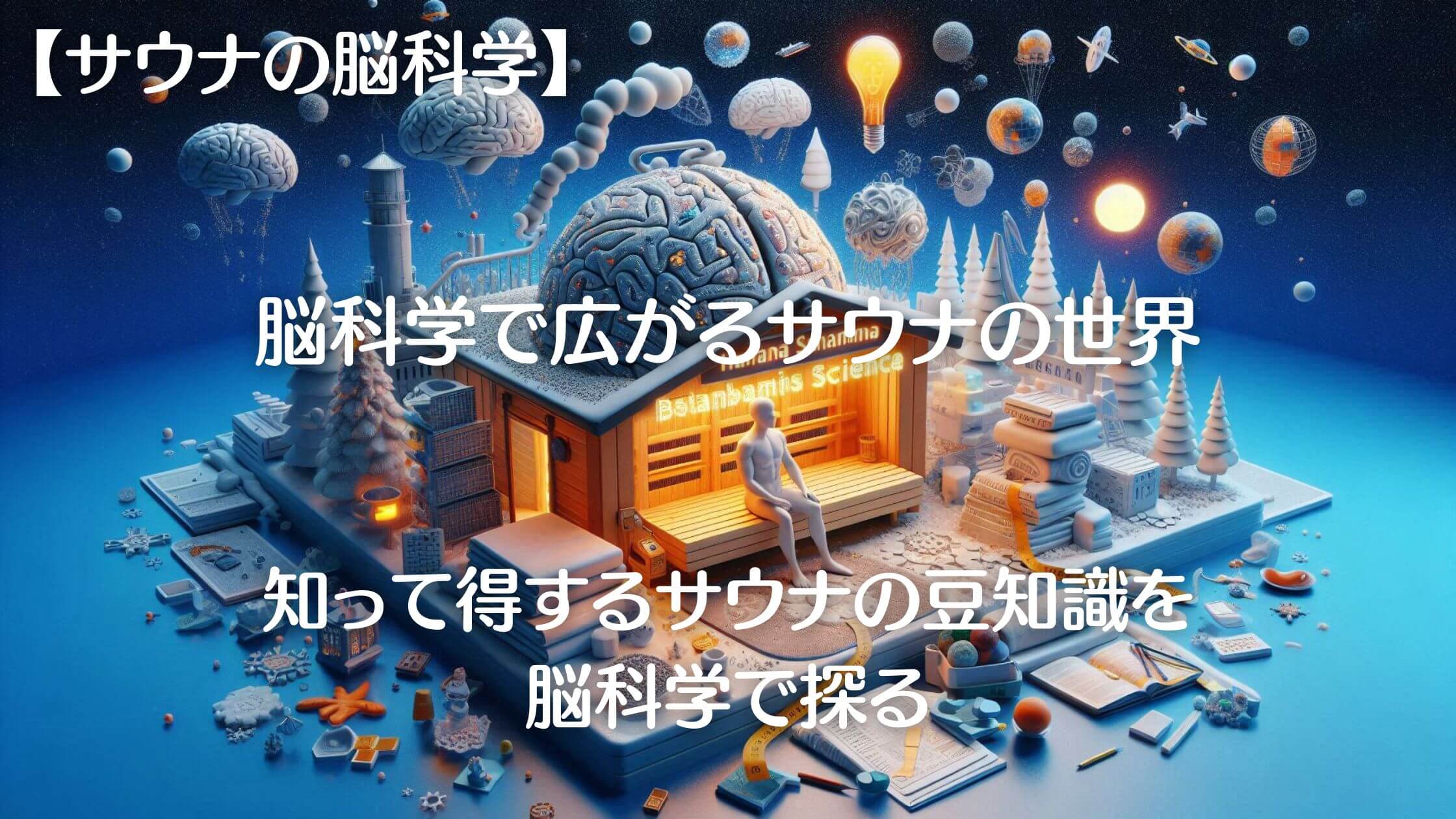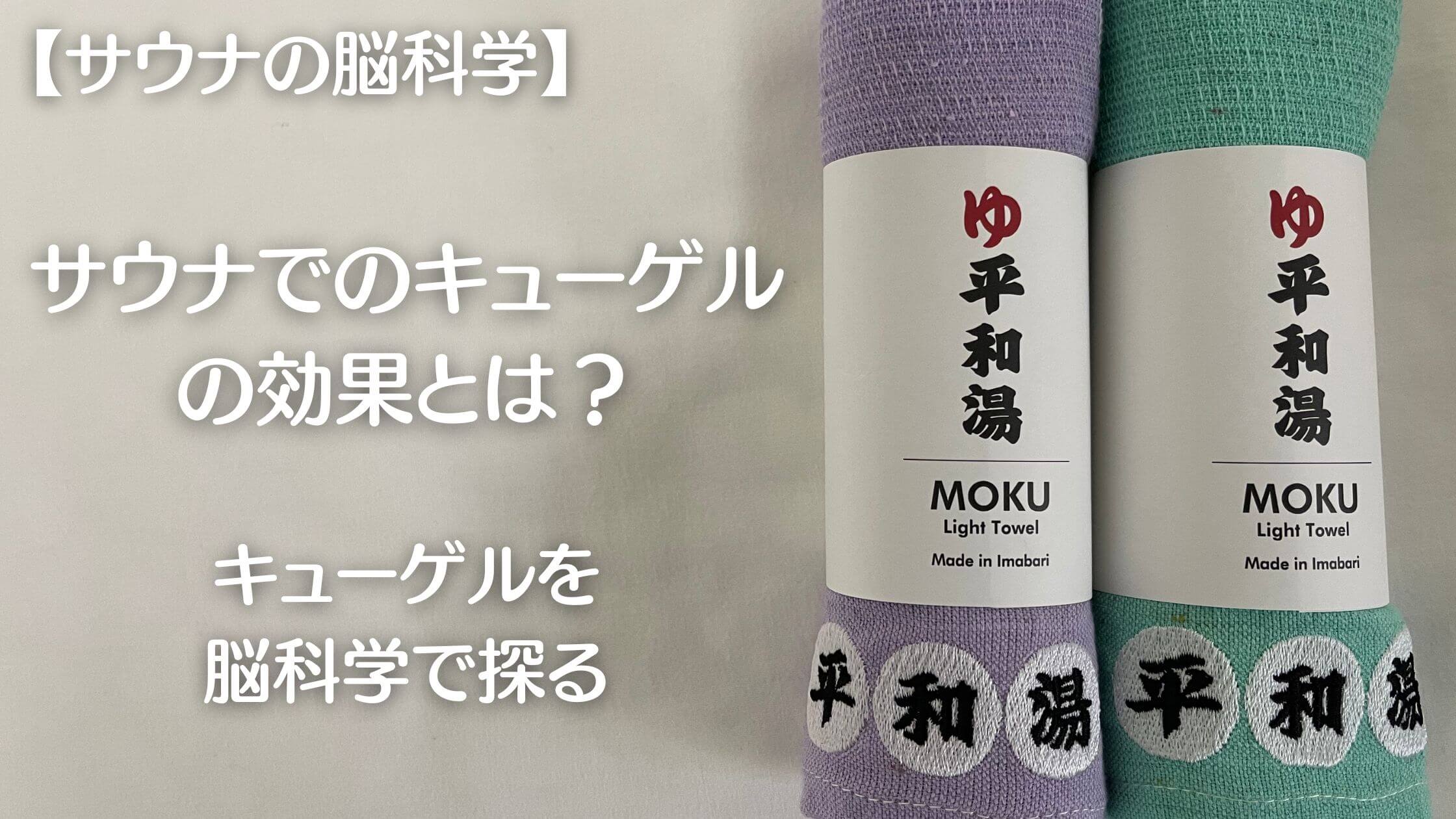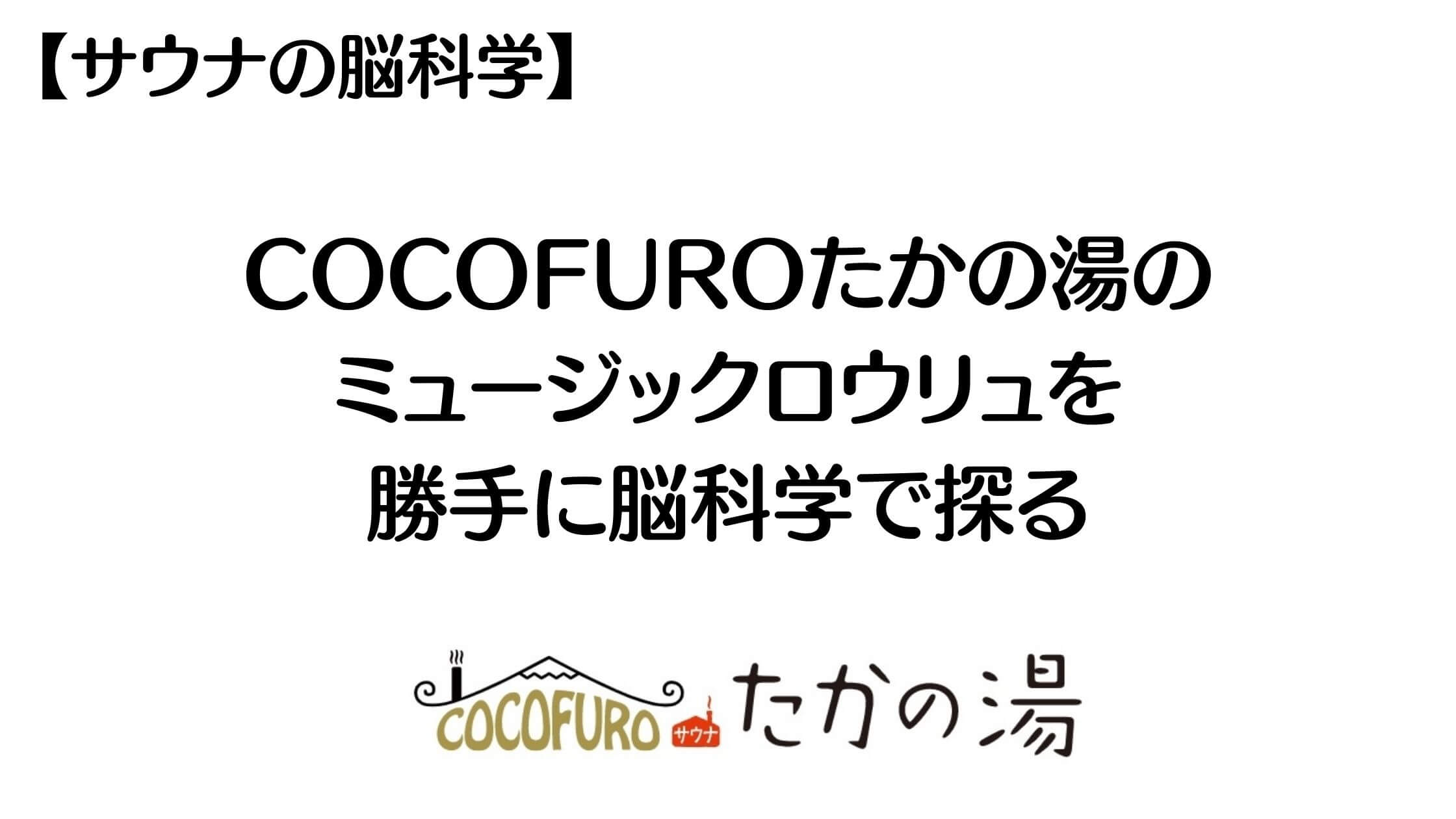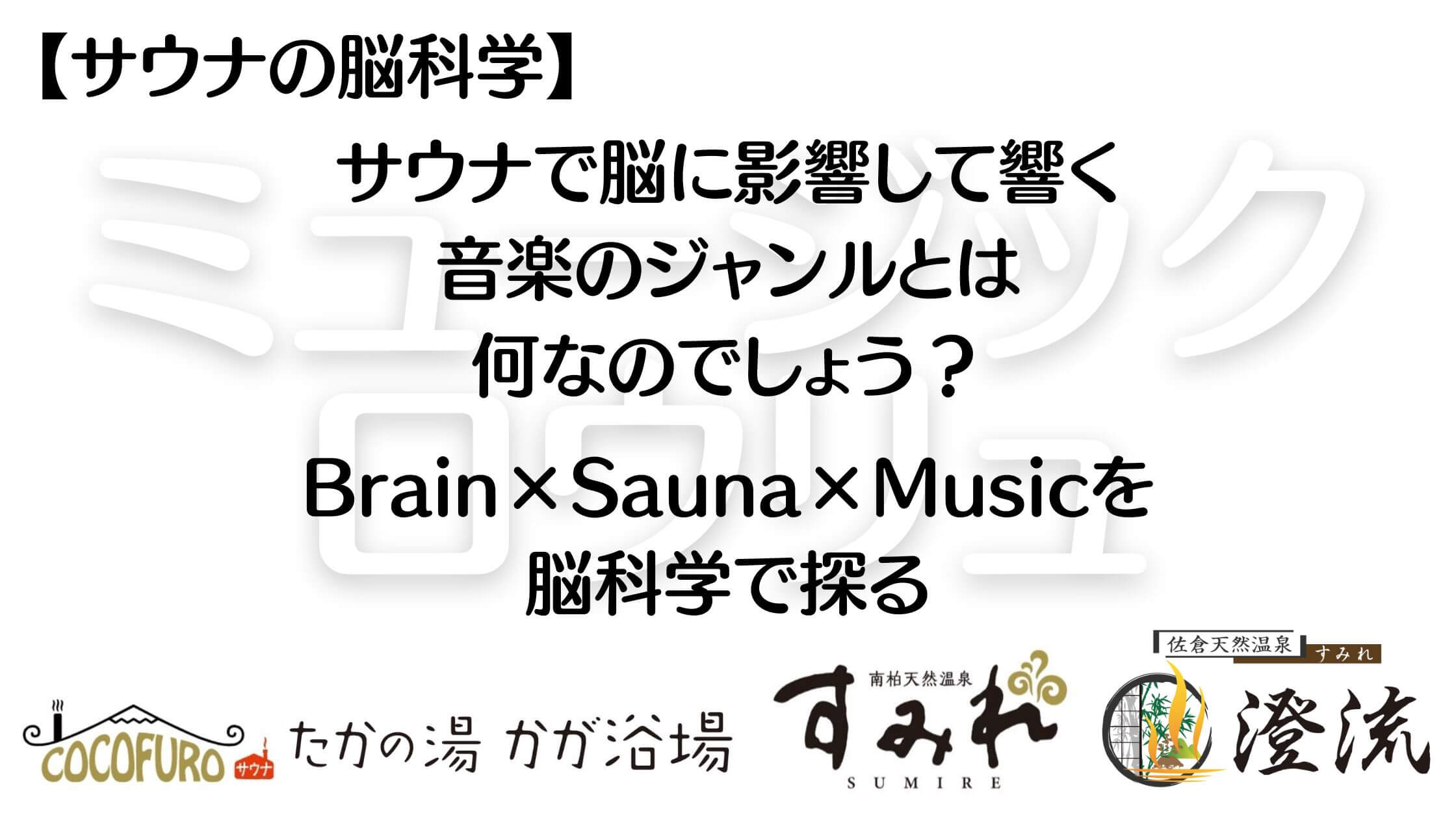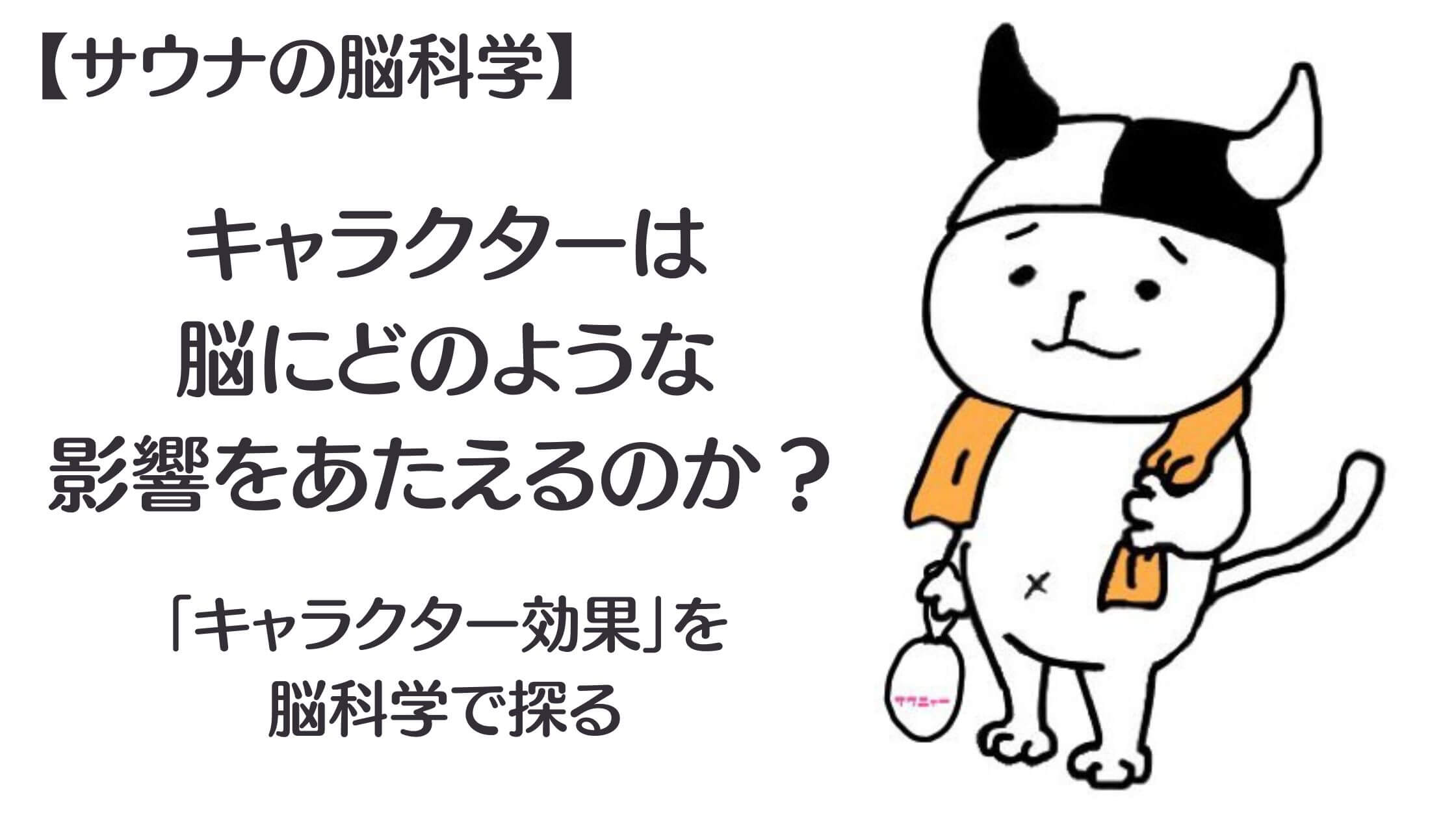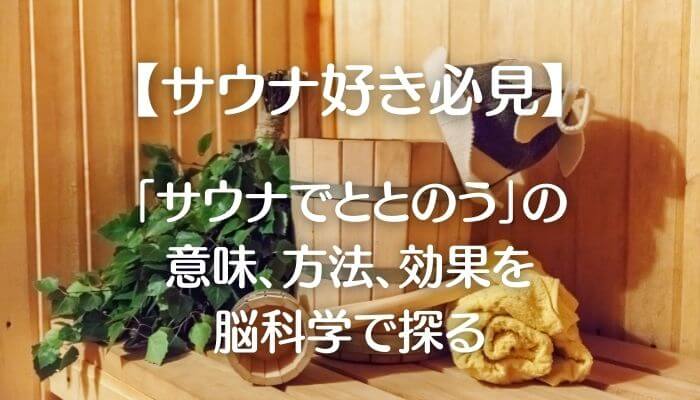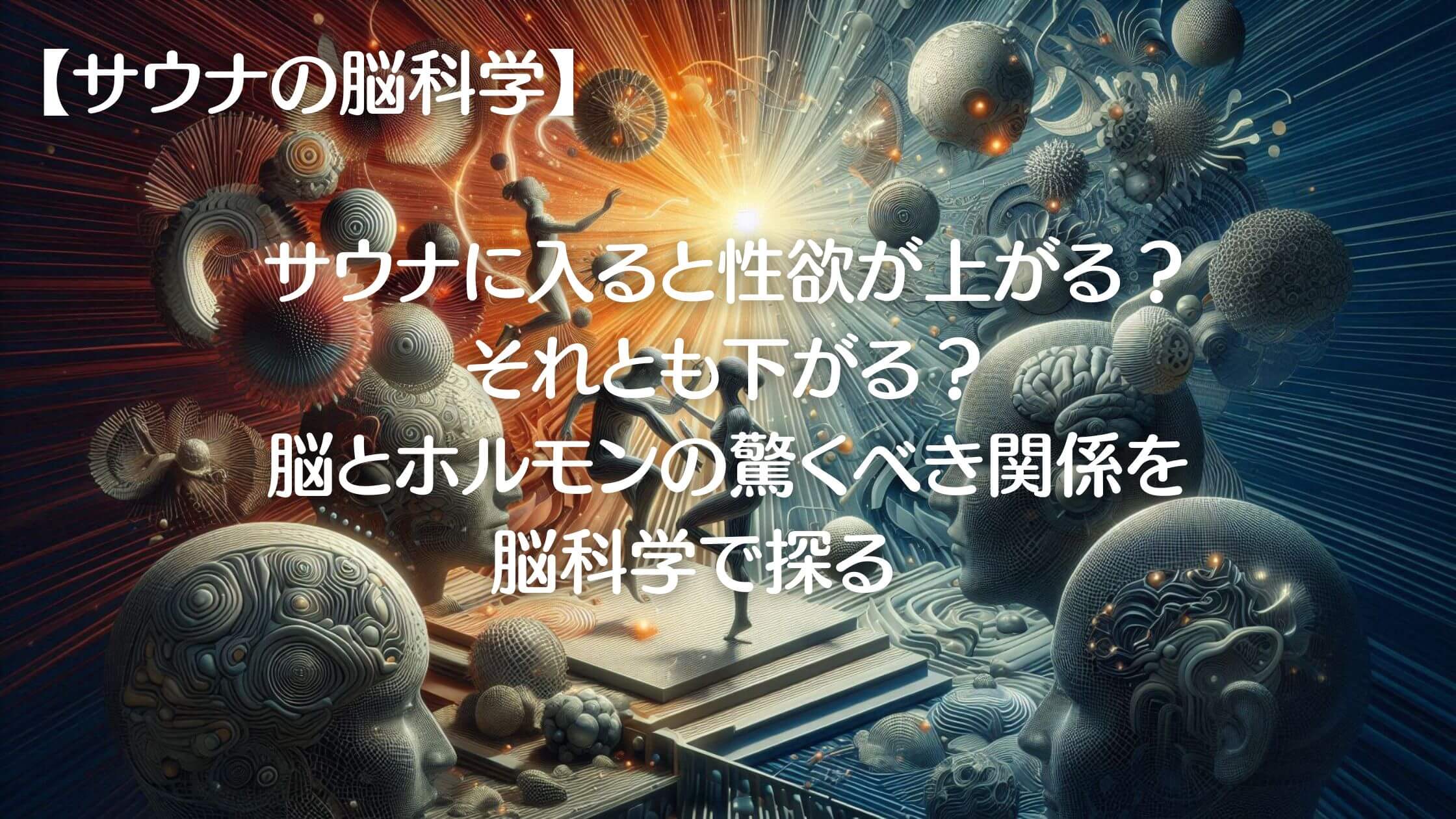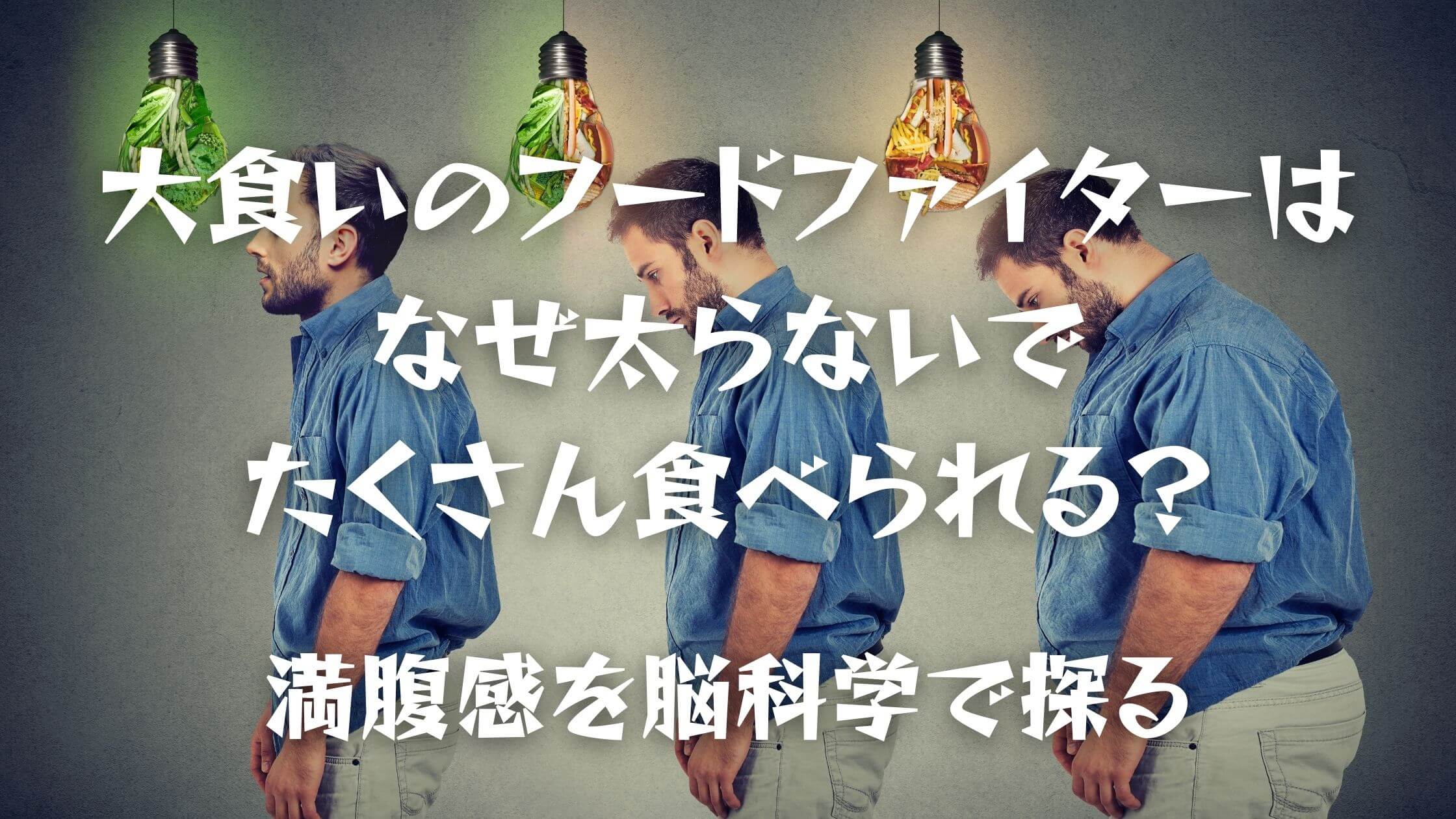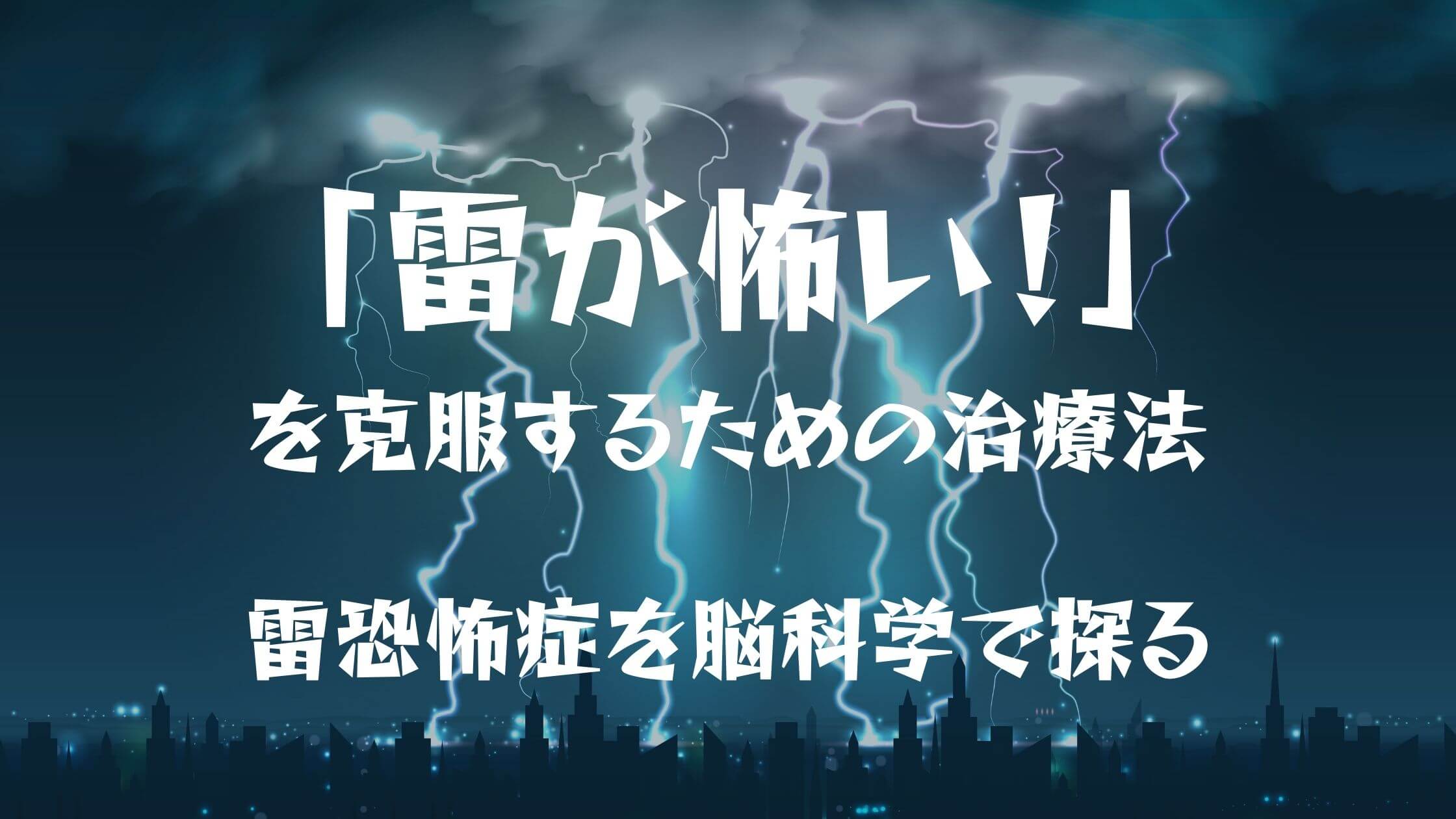肯定すること否定することではどちらの方が大切なのでしょう?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。
この記事を読んでわかることはコレ!
- 「肯定」と「否定」の意味をわかりやすく脳科学で説き明かします。
なぜ何もないのではなく、何かがあるのか?

「肯定」と「否定」の脳科学
- 脳は“何も存在しない”という「否定」よりも“何かがある”という「肯定」を重要視する傾向があります。
- ですから“存在する”ものにばかり気をとられて“存在しないもの”は見落としがちになります。
- あえて存在の「否定」について考えることで、今よりももっと素敵な幸せを見つけられるはずです。
ある哲学者が言った言葉
『なぜ何もないのではなく、何かがあるのか?』
みなさんは聞いたことがあるでしょうか?
これだけでは何を言っているのかよくわかりませんよね…
簡単に言ってしまえば、
「何もないということを証明することは難しいが、何かあるということを証明することは簡単」
といった感じでしょうか。
“何も存在しない”ということはおおよそ“完全な無”である。
しかし“何も存在しない”ということを考えた時点で、そこはすでに“完全な無”ではない。
なぜなら“完全な無”がそこに存在しているからだ。
“何も存在しない”ということは、本当の意味では誰も想像すらしていない何かであり、想像した時点でその事象は”空想としてそこに存在するもの”となってしまう。
だから、本当の意味で“何も存在しない”ということにはならず、“何かがある”ということになってしまう。
そのため、本当の意味で“何も存在しない”を見つけることは不可能であり無駄なことである。
何かを考えて想像すればするほど“何も存在しない”はどんどん減ってしまうので、”何も考えない”ことこそが“何も存在しない”に限りなく近い状態である。
つまり“何も考えない”ことこそが究極の“完全な無”である。
物事の存在理由を問う有名な言葉ですが、なかなか難しい言葉です。
良く考えればスピリチュアル的な世界観でしょう。
“スピリチュアルの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-

参考お盆と霊を科学する~スピリチュアルの意味を脳科学で説く
「お盆には祖先の霊が私たちのところに訪ねて来る」って言いますが、それってどういうことなのでしょう? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログ ...
続きを見る
悪く考えれば一種の屁理屈かもしれません。
“屁理屈の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
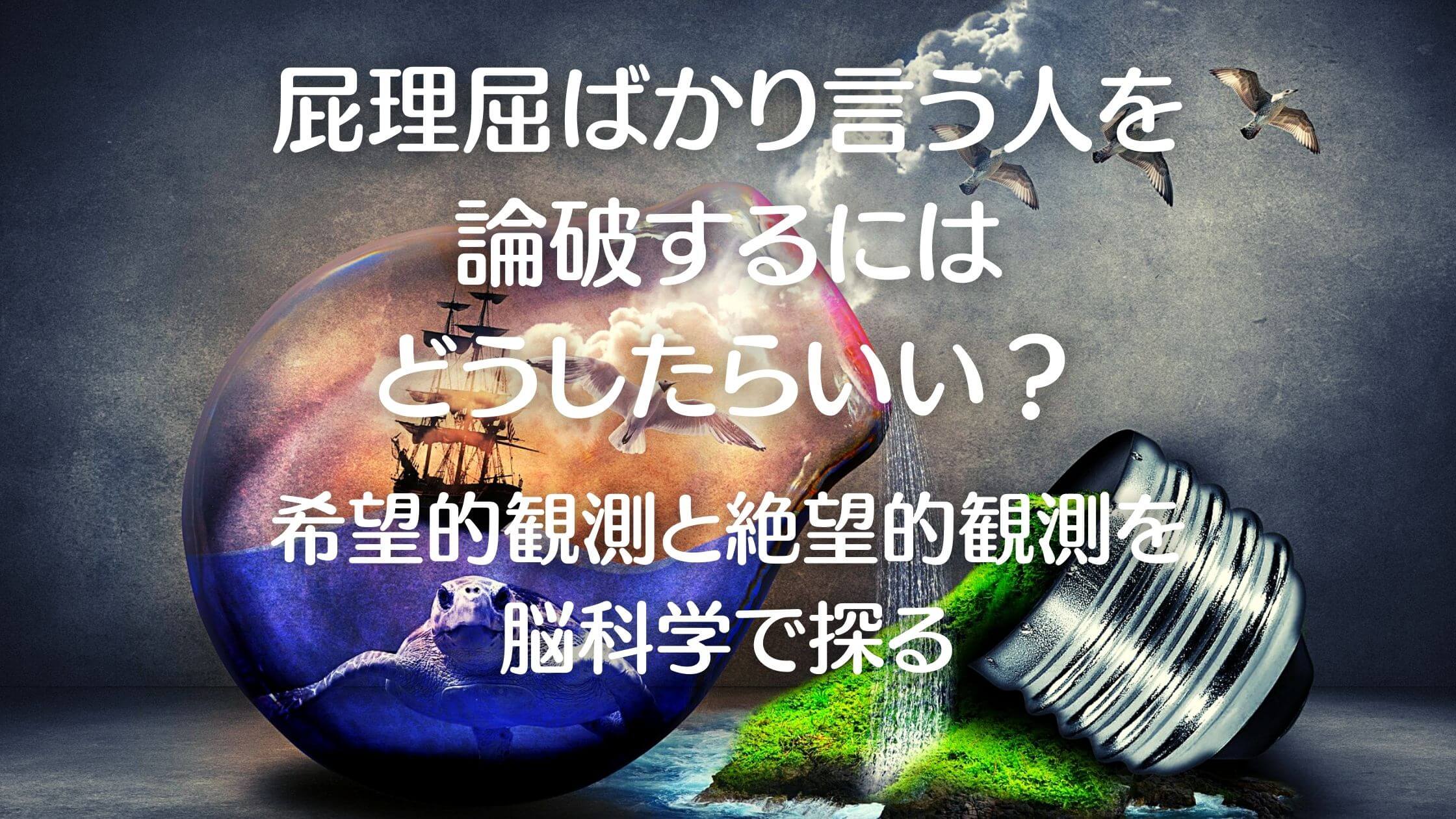
参考屁理屈ばかり言う人を論破するにはどうしたらいい?希望的観測と絶望的観測を脳科学で探る
屁理屈ばかり言う人を論破するにはどうしたらいいのでしょう? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳 ...
続きを見る
“何かがある”は存在の「肯定」であり、“何も存在しない”は存在の「否定」です。
脳は存在の「肯定」と「否定」をどのように区別して処理しているのでしょうか?

「肯定」は「否定」よりも重要である


724 942 547 614 214 478 554 469
答えは、単純ですべての数字に“4”が含まれているということです。

324 129 785 453 278 319 872 439
今度の問題の方がずっと難しいはずです。
答えは、どの数字にも“6”が含まれていないということです。
この2つの問題からわかることは
「存在しないものを見つける」ことは「存在することを認識する」ことよりもずっと難しいということです。
言い換えれば、脳にとって存在の「肯定」の方が、存在の「否定」よりもずっと重要ということです。
たとえば散歩をしていて、「自分の体に何の痛みも感じない」ことに気づくことはあまりないはずです。
膝が痛い、肩が痛い、指が痛い…たいがい体のどこかに痛みを感じることが多いはずです。
そんな時は否が応でも痛みの存在に気づきます。
しかし“体のどこにも何の痛みも感じない”はある意味当たり前のことすぎてなかなか気づかないものです。
そしてそのことに気づくには想像以上のエネルギーが必要となってきます。
痛みが存在しなければわざわざ痛みについて考えることはしないからです。

年末の恒例行事としてベートーベンの「第九」を聞きに行く人も多いでしょう。
特に第四楽章の合唱が始まると、コンサートホールは感動の渦に包まれていきます。


この世に第九がなければわたしたちは今よりも不幸になるのでしょうか?
そんなことはありません。
第九が作曲されていなくても、きっと誰一人として困る人はいないはずです。
そこに第九が存在するからこそ聴衆は魅了され感動するのです。
もしかしたらもっと人々を感動させるような調律の交響曲があり得たかもしれません。
しかし誰も「今すぐ第九よりももっと感動的な交響曲を作曲しろ!」などとは言いません。
つまり存在しているものは、存在していないものよりもずっと価値があり重要なのです。
脳が「否定」よりも「肯定」を重要視する傾向を、専門的には「特徴肯定性効果」と呼びます。

「特徴肯定性効果」のワナ

脳が“何も存在しない”よりも“何かがある”を重要視する「特徴肯定性効果」をうまく利用した物事は世の中にたくさんあります。

「ワクチンを打てばウイルスの感染を防げます!」
「ワクチンを打たなければウイルスの感染は防げません!」
どちらの方がよりインパクトがあるでしょうか?
おそらく前者の方が効果的なはずです。

チェックリストに記載されている項目については完璧かもしれませんが、記載されていない項目については見向きもしないはずです。
“存在しないものには目もむけない”
チェックリストさえなければより注意深く確認して気づきそうなミスも、チェックリストがあるがためにその項目になければ見落とされがちになるのです。
物件を探していて建物の内装や、駅や大型スーパーまでの距離ばかり気にしていて、建物の隣に何があるのか記載されていなければ気づかないでしょう。
しかし現地に行ってみたら、建物のすぐ隣にゴミ焼却場が建設予定になっていました。
不動産の価値が下落するようなリスクについては、チェックリストに記載がなければ見落としがちです。
“何かがある”ばかり気にしていると“何も存在しない”はついつい見落としがちになり、「特徴肯定性効果」のワナにはまりやすくなるのです。
存在の「否定」を考えて幸せになろう
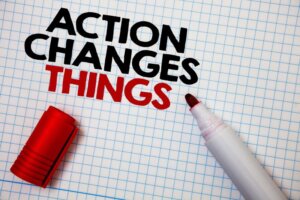
脳は“何も存在しない”という存在の「否定」について考えるのが不得意です。
そもそも“何も存在しない”ものは認識できません。
戦争が起きている時には戦争の恐ろしさを実感しますが、戦争がなく平和な時にはそのことに気づけません。
健康な時には、自分が病気になるかもしれないという事実はほとんど意識していません。
飛行機に乗って墜落せずに無事に目的地に到着しても、それが当たり前で何も驚いたりはしません。
学術や技術の世界では特に存在の「否定」は嫌われます。
学術的、技術的に優れた仮説を証明することができれば、素晴らしい業績として称えられます。
しかし仮説の誤りを証明しても誰も賞賛はしてくれません。
仮説の誤りの証明も、仮説の証明と同じくらい価値があるはずです。
しかし脳はネガティブなアドバイス(~しない方がいい)よりもポジティブなアドバイス(~した方がいい)の方に耳を傾けてしまうのです。
その際にそれが有益か無益かなどは問題ではありません。

きっと今まで見過ごしていた何かに気づいて、今までよりもずっと満ち足りた気持ちになれるはずです。
最初にも言いましたが、“何も存在しない”という存在の「否定」について考えることはとても骨の折れる作業です。
しかし骨を折って苦労してこそつかみ取れる幸せがきっとあるはずです。


“「肯定」と「否定」の脳科学”のまとめ
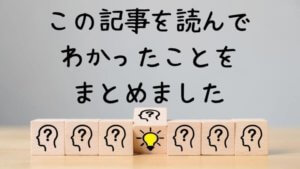
「肯定」すること「否定」することの意味をわかりやすく脳科学で説き明かしてみました。
今回のまとめ
- 脳は“何も存在しない”という「否定」よりも“何かがある”という「肯定」を重要視する傾向があります。
- ですから“存在する”ものにばかり気をとられて“存在しないもの”は見落としがちになります。
- あえて存在の「否定」について考えることで、今よりももっと素敵な幸せを見つけられるはずです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわりのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
最後にポチっとよろしくお願いします。