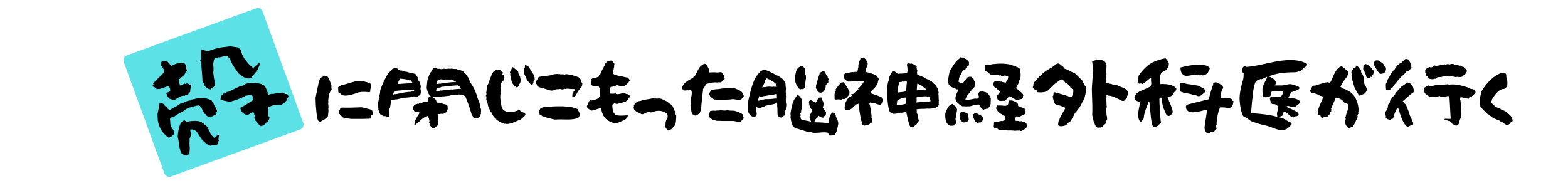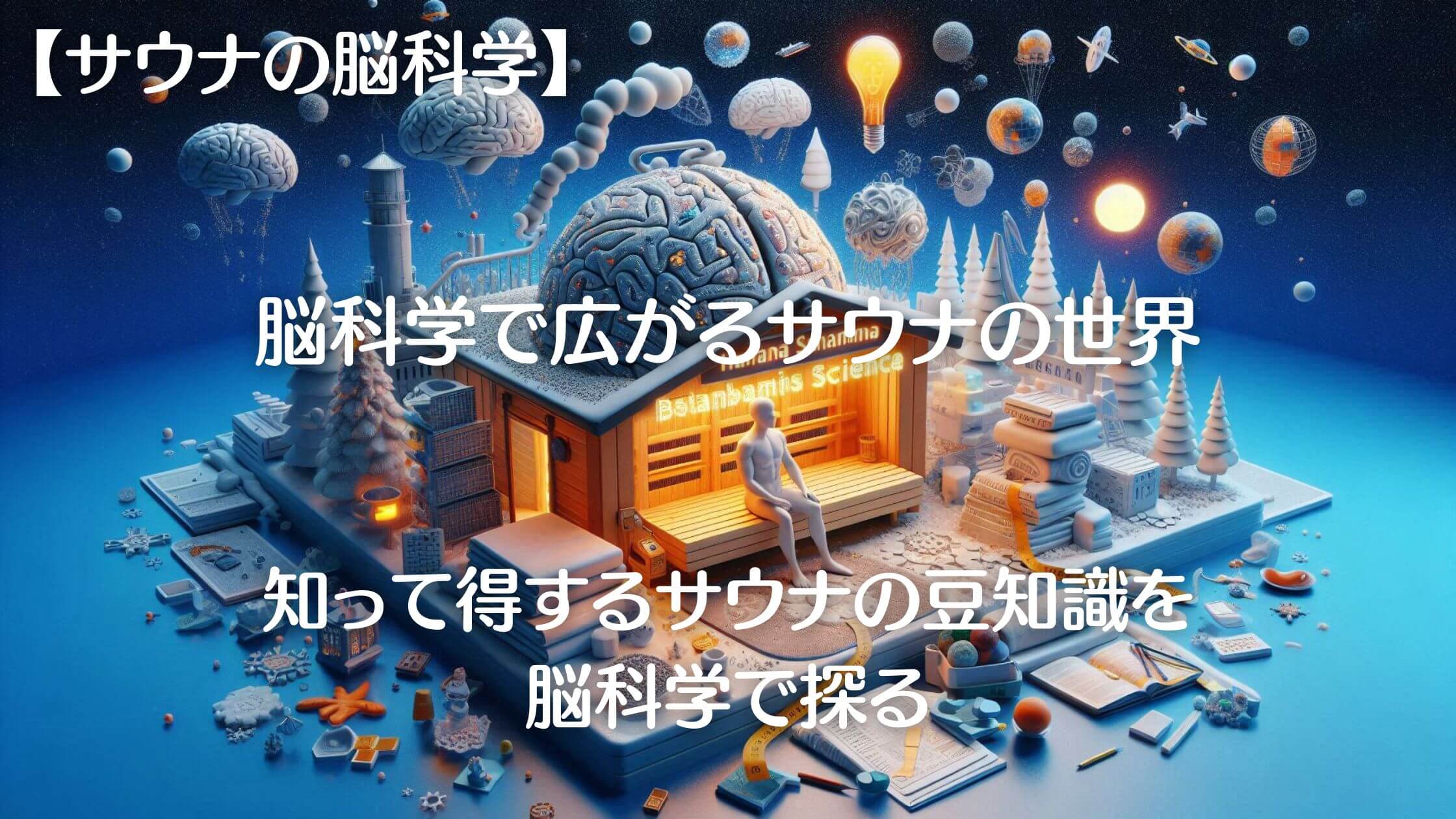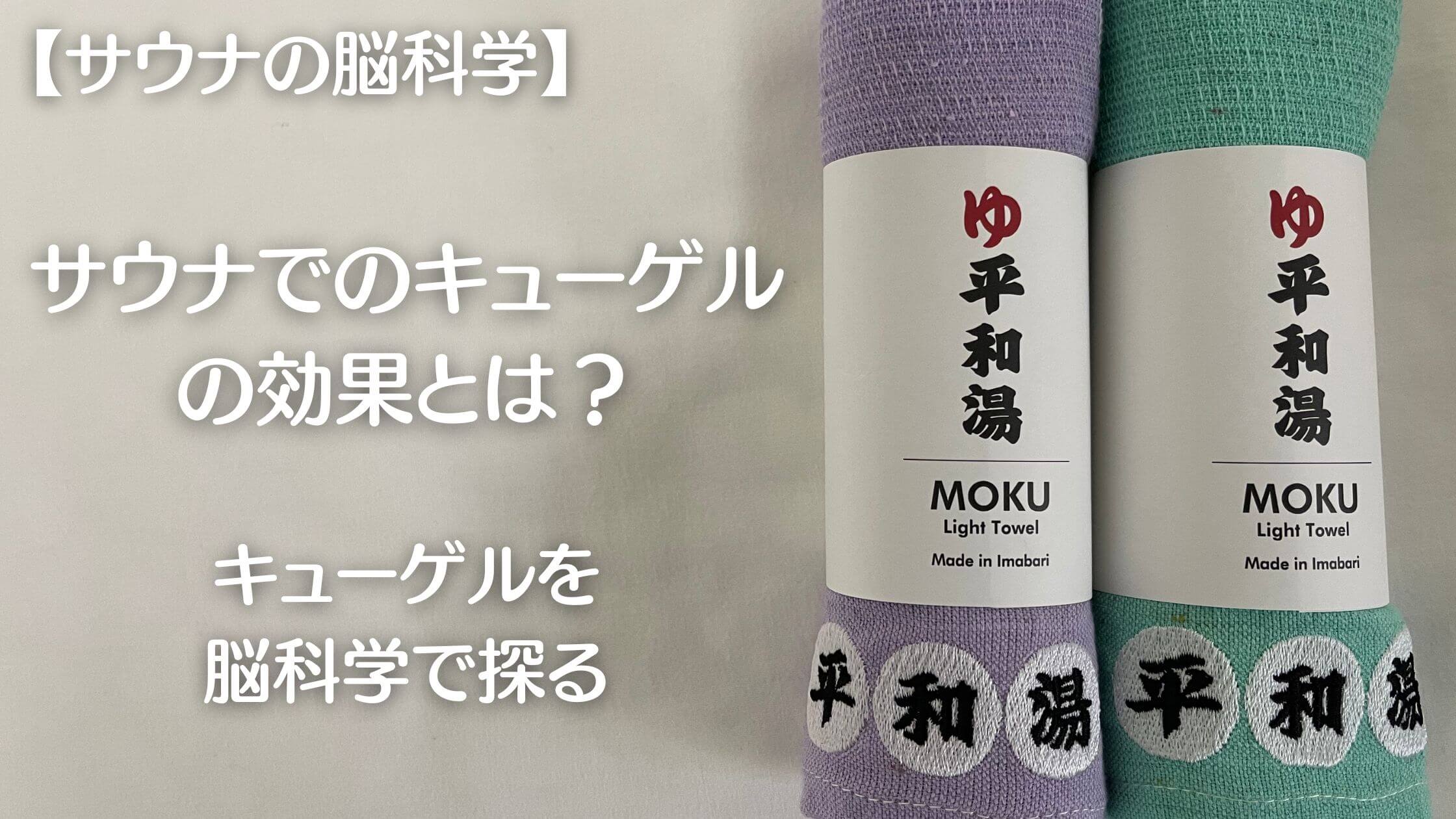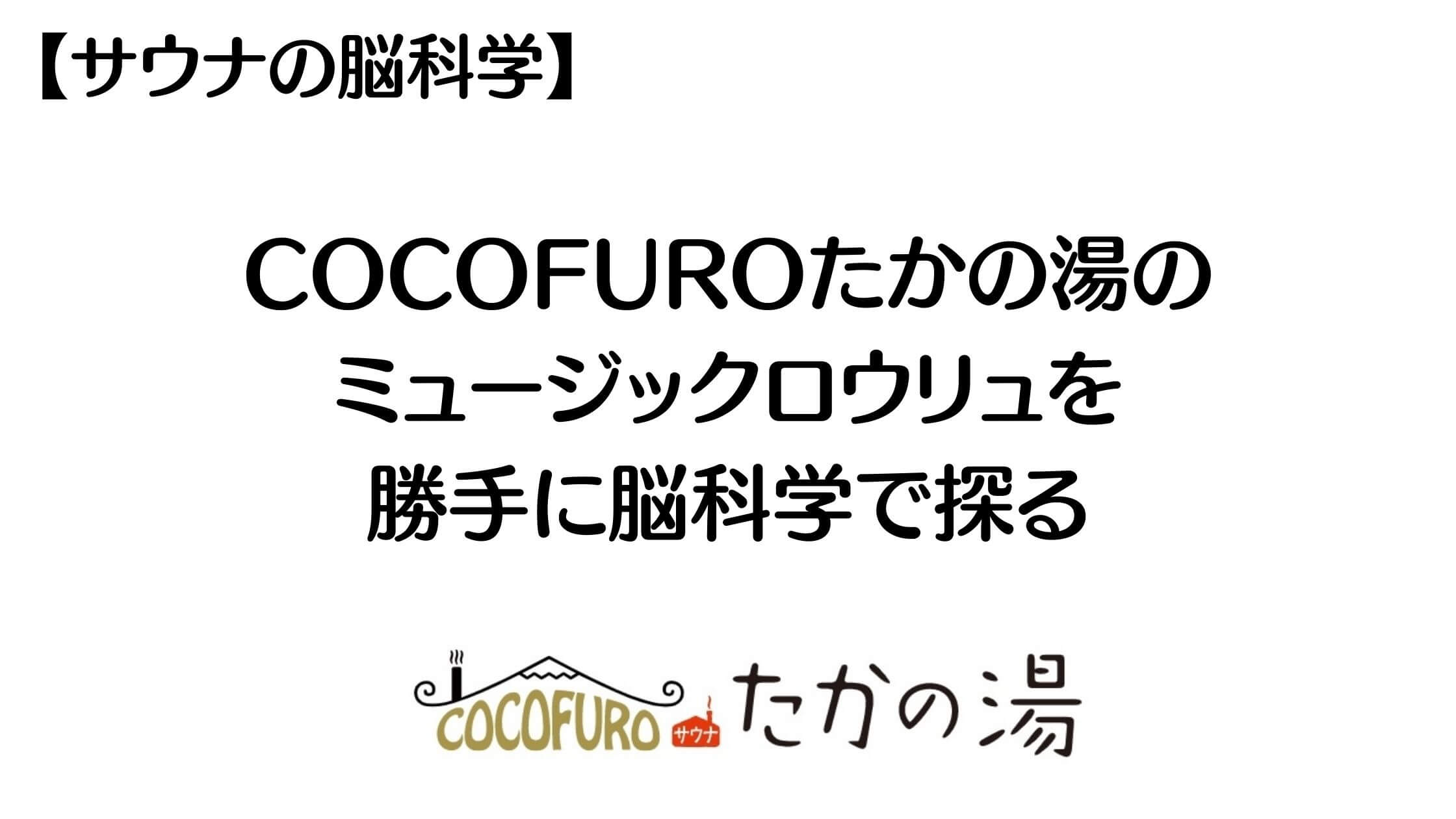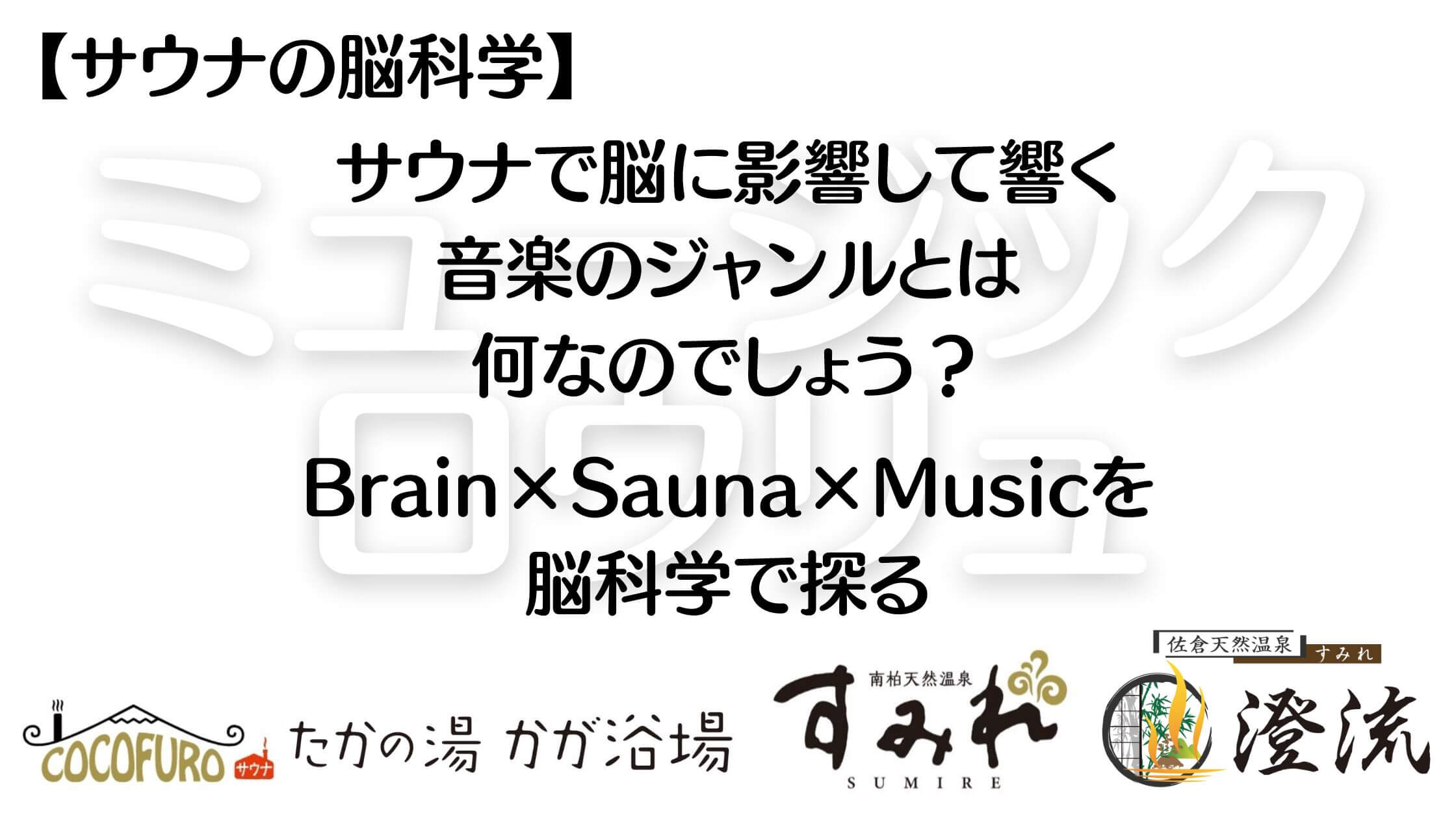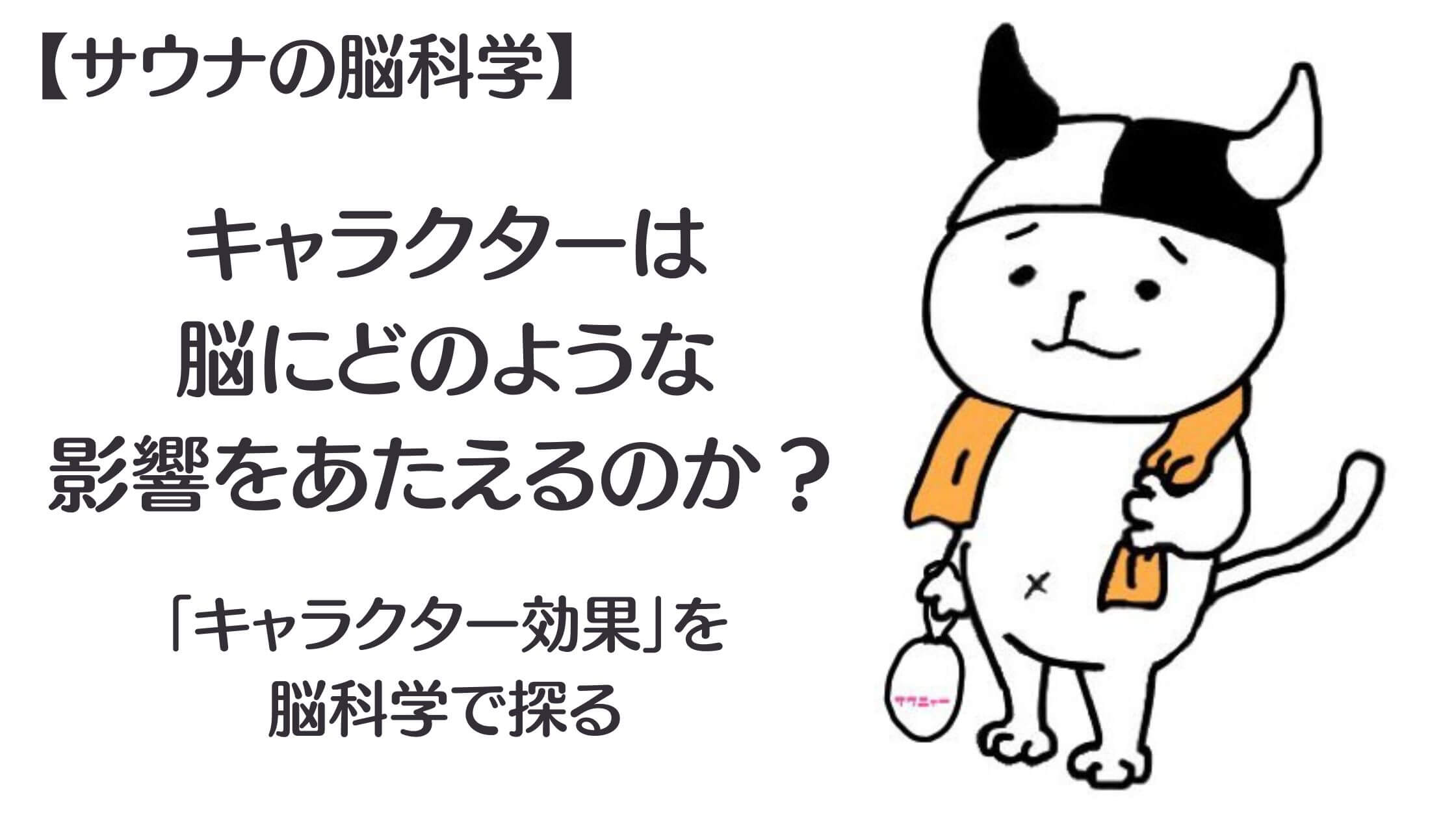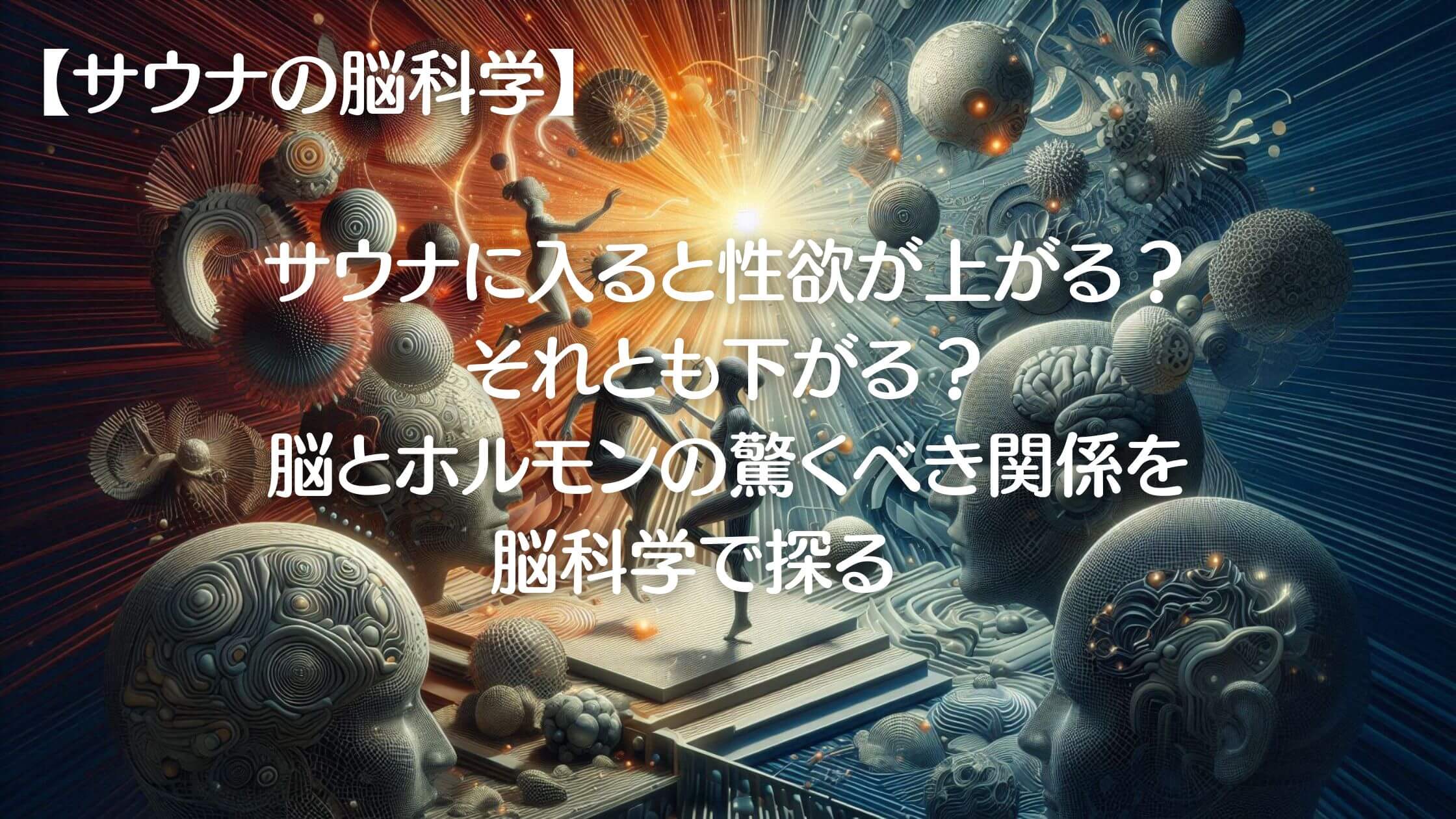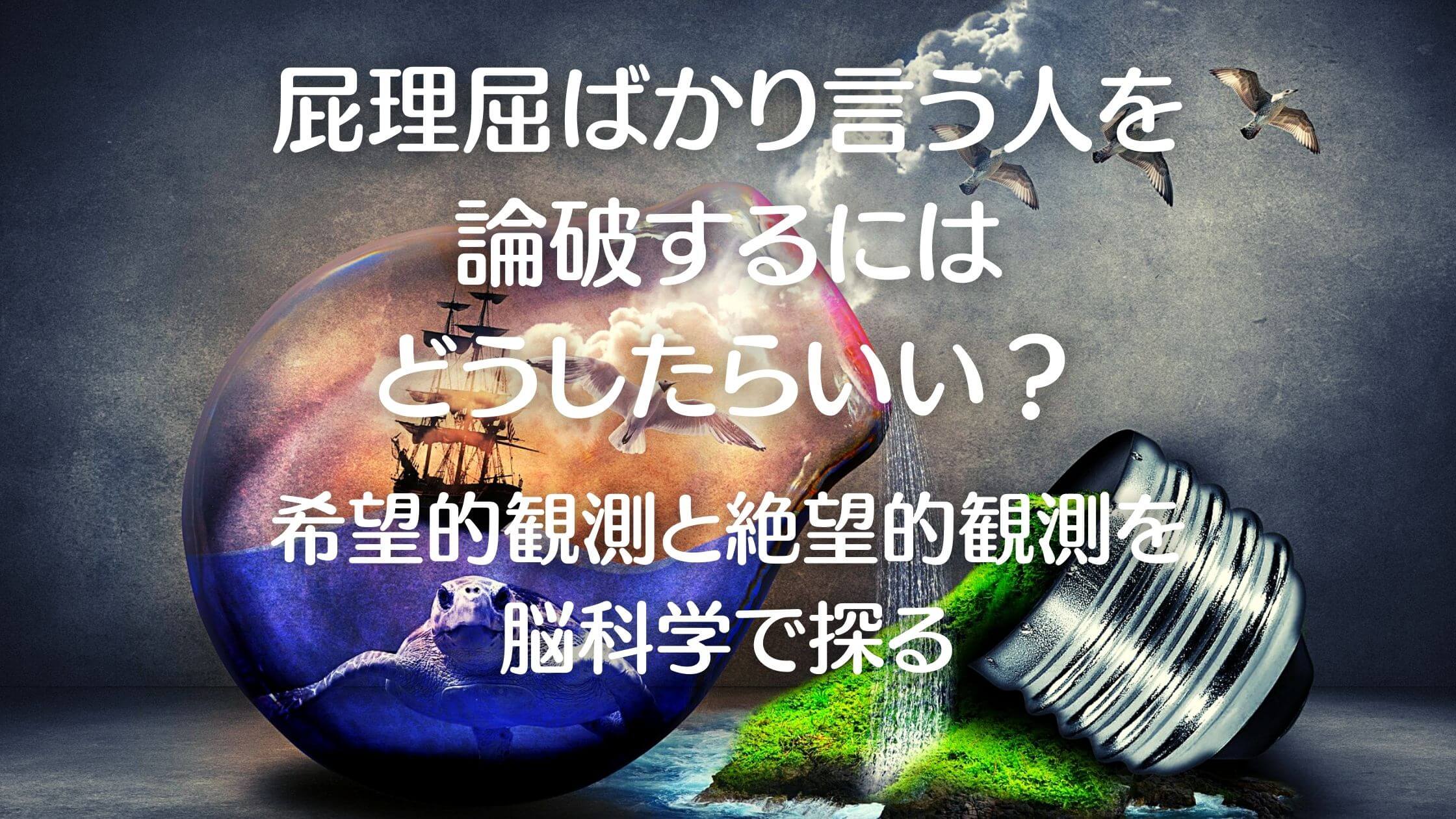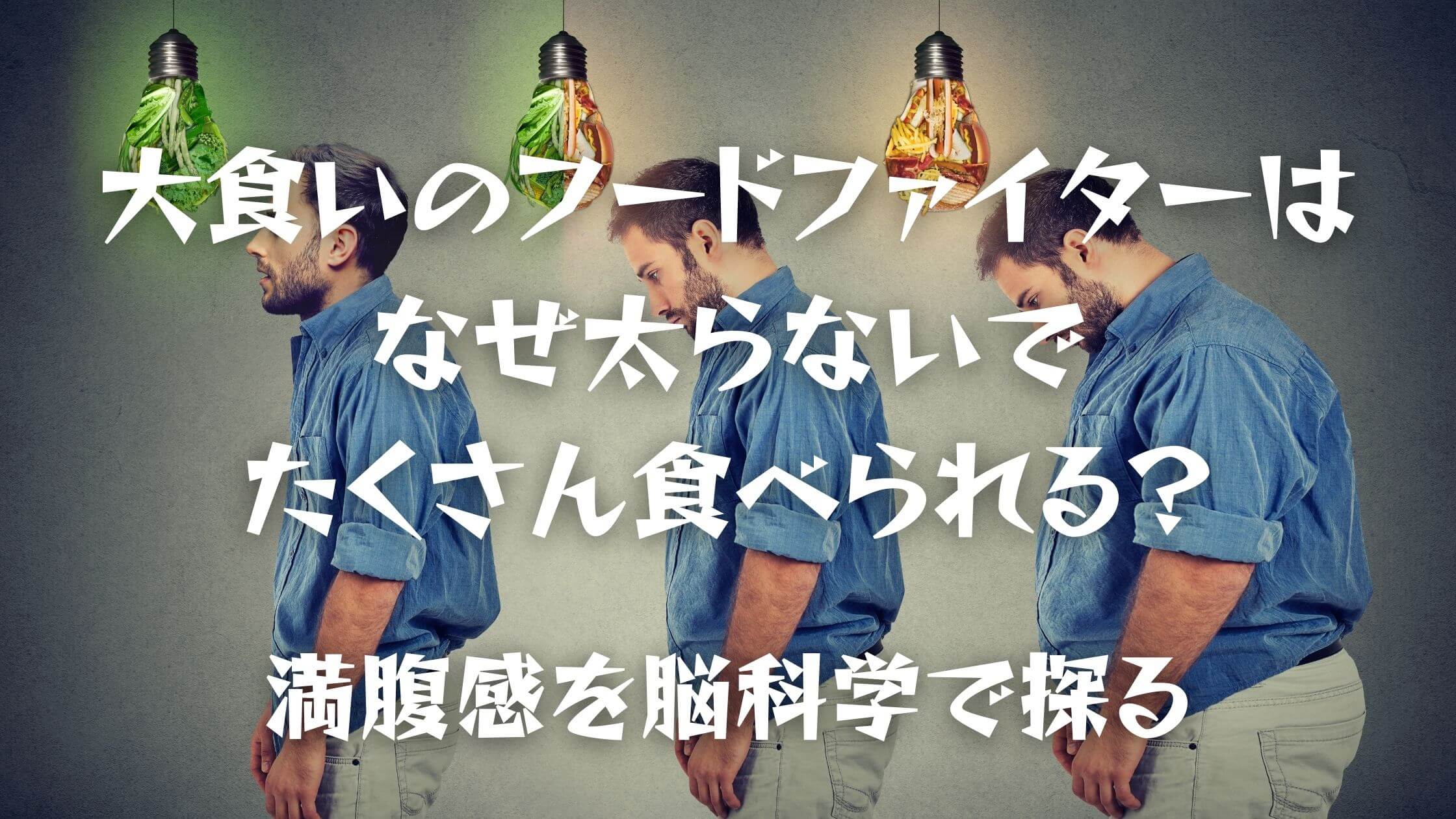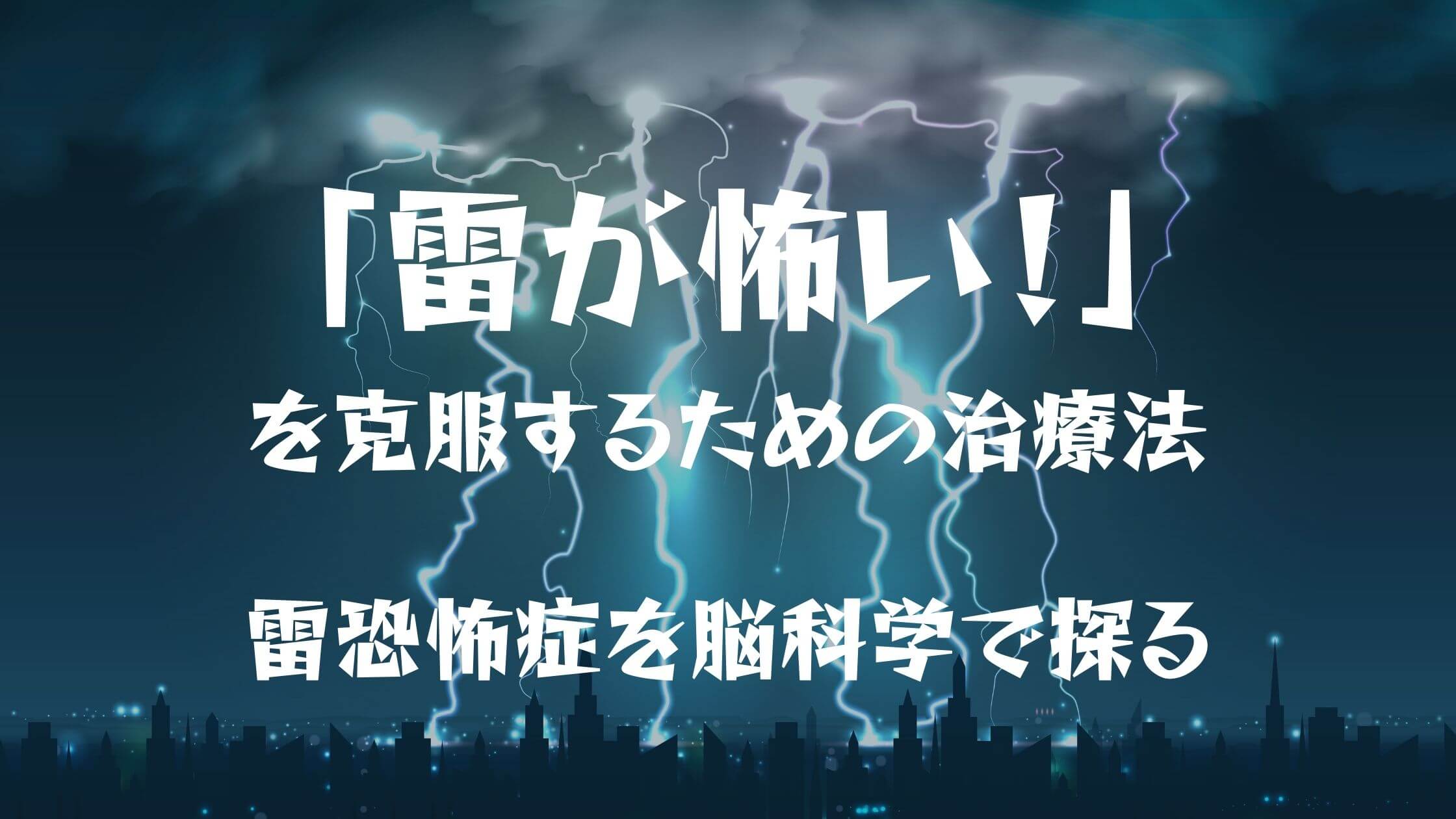サウナストーンとはなんなのでしょう?
サウナストーンは脳にどのような影響をおよぼすのでしょうか?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。
この記事を読んでわかることはコレ!
サウナストーンを脳科学で説き明かします。
サウナの「ととのい体験」は石から始まっていた

めサウナストーンの脳科学
- サウナストーンは単なる石ではなく、「五感の刺激」を通じて脳を“ととのえる”メカニズムの中核を担っています。
- 石の材質や交換頻度を見直すことで、より深いリラクゼーションや集中感を得ることが可能になります。
- 脳科学的視点から見ても、サウナストーンは心身のバランスを整える“仕組み”の一部として非常に理にかなっているのです。
現代の日本では第3次サウナブームによって多くの施設がにぎわっています。
“サウナブームの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-

参考【サウナの脳科学】なぜ今サウナは人気なのか?サウナブームを脳科学で探る
なぜ今サウナはこれほどまでに人気でブームを巻き起こしているのでしょうか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20 ...
続きを見る
サウナの醍醐味(だいごみ)は何と言っても、サウナトランス=「サウナでととのう」でしょう。
温かいサウナと冷たい水風呂、休息タイムを繰り返す温冷交代浴では徐々に体の感覚が鋭敏になってトランスしたような状態になっていきます。
トランス状態になると、頭からつま先までがジーンとしびれてきてディープリラックスの状態になり、得も言われぬ多幸感が訪れます。
これがいわゆるサウナトランスであり、そして「サウナでととのう」の状態です。
”サウナでととのうの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
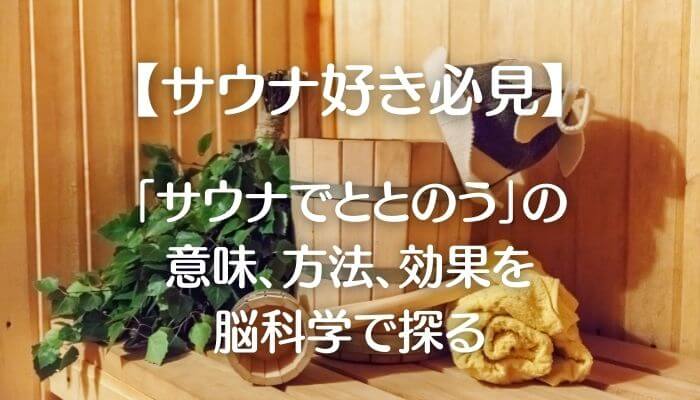
参考【サウナ好き必見】「サウナでととのう」の意味、方法、効果を脳科学で探る
「サウナでととのう」とは脳科学的にどのような意味や方法や効果があるのでしょうか?? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医 ...
続きを見る
サウナ―達は至高のサウナトランスを味わうためにサウナに通うわけです。
サウナに入ると、体の芯から温まり、心もスッと軽くなる感覚が得られます。
この「ととのい」と呼ばれる状態がサウナの魅力ですが、その裏側にあるメカニズムは実はとても奥深いものです。
そして、その中心にあるのが「サウナストーン」―つまり“石”です。
この記事では、サウナストーンの歴史や素材、寿命や交換のタイミングなどの基本情報に加え、その石がいかにして私たちの脳に作用し、「ととのう」感覚を導いているのかを、脳科学の視点から詳しく解説していきます。
サウナストーンとは? その歴史と役割

サウナ文化の発祥地として知られるフィンランドでは、古くから「石を熱する」という技法が用いられてきました。
サウナという言葉自体は「煙の出る小屋」を意味する古語に由来しており、その原型はおよそ2000年前までさかのぼると言われています。
当時のサウナは“スモークサウナ”と呼ばれ、薪を使って石を高温に熱し、煙と共に温かい空気を浴びるというスタイルでした。
石は空気を温めるだけでなく、熱を長時間蓄える能力があったため、室内を快適な温度に保つ重要な役割を担っていたのです。
その後、煙突付きの「モダンサウナ」が登場し、電気やガスによる加熱方式が普及しましたが、「石に熱を与えて、そこに水をかけて蒸気を出す」という基本的な構造は今もほとんど変わっていません。
つまり、サウナの核となる仕組みは、いまでも“石を通じて人を温める”ことに根ざしており、サウナストーンはまさにその心臓部なのです。
なぜ「石」が必要なのか?――サウナストーンの素材と特徴

現代のサウナでは、サウナストーンに「火成岩」と呼ばれる自然石が使用されることが一般的です。
これは、地中のマグマが冷えて固まった岩石であり、代表的なものに「玄武岩(バサルト)」や「閃緑岩(ガボロ)」があります。
これらの石が選ばれる最大の理由は、その耐熱性と蓄熱性の高さにあります。
数百度の高温にさらされても割れにくく、しかも長時間にわたり熱を保持し、水をかけたときに効率よく蒸気を発生させるという性質があるのです。
さらに、多孔質(穴の多い構造)を持つ石であればあるほど、ロウリュ時に水をしっかり受け止めて、柔らかく肌あたりの良い蒸気を発生させることができます。
逆に、密度の高すぎる石では水が滑り落ちてしまい、ロウリュ効果が薄れてしまうのです。
現在市場にはさまざまな種類のサウナストーンが流通しています。
フィンランド製の天然石は高品質で人気ですが、近年ではコストパフォーマンスの高いロシア産や中国産の石も多く使われています。
また、近年では阿蘇の玄武岩など国産の石にも注目が集まっています。
サウナストーンの寿命と交換のタイミング

石は永久に使えるように思われがちですが、サウナストーンにも寿命があります。
高温と水分の反復的な刺激によって、表面に微細なヒビが入り、やがて破裂や崩壊のリスクが高まっていくのです。
目安としては、業務用のサウナであれば6か月〜1年、家庭用であれば1年〜2年程度で交換が推奨されています。
石の表面が白くなったり、触ると粉を吹いたり、水をかけたときに“異音”がするようであれば、劣化のサインと考えて良いでしょう。
交換を怠ると、蒸気の質が悪くなったり、極端な温度変化によって破裂事故につながったりする可能性もあります。
つまり、サウナストーンは安全性と快適性の両方を担う重要な存在なのです。
また、新しい石に交換すると、ロウリュの蒸気が滑らかで柔らかく感じられることがよくあります。
これは物理的な蒸気特性の違いだけでなく、後述するように「変化に対する脳の反応」も関係している可能性があるのです。
ロウリュと蒸気の質――脳が“熱”をどう感じるか?

「ロウリュ」とは、サウナストーンに水をかけて一気に蒸気を発生させる行為です。
ジュワッという音とともに、室内の湿度が一気に高まり、体感温度が跳ね上がります。
この瞬間、多くの人が「あぁ、ととのい始めた…」と感じることが多いでしょう。
ここで不思議なのは、実際の温度がそれほど上がっていなくても、湿度の上昇によって体が“ものすごく熱い”と感じることです。
これは皮膚に分布する温度受容体―特にTRPV1(カプサイシン受容体)という神経センサーが湿度によって強く反応するためです。
さらに、高温多湿な環境下では、発汗による冷却効果が低下し、脳は「今は危険な状態だ」と判断して交感神経を活性化させます。
この一連の生理反応が、のちの副交感神経優位(リラックス)への揺り戻しをより強調する形となり、いわゆる“ととのい”感覚につながるのです。
つまり、ロウリュとは単なる蒸気の演出ではなく、脳と自律神経に強く作用する「温熱刺激」の装置ともいえるのです。
そして、その源がサウナストーンなのです。
サウナストーンが脳に働きかけるメカニズム

ここからは、サウナストーンと脳の関係について、より詳しく掘り下げていきます。
サウナ体験には、温熱刺激だけでなく、音・香り・光・触覚など、五感すべてが関与しています。
そして、それらの多くはサウナストーンを介して発生しているのです。
たとえば、ロウリュ時の「ジュワッ」という音。
これは単なる水の音ではなく、脳の快感中枢を刺激する“ASMR(自律感覚絶頂反応)”として機能している可能性があります。
ある研究では、心地よい水音や環境音を聞くことで扁桃体の活動が抑制され、不安が軽減されたという報告もあります。
また、アロマ水を使ったロウリュでは、香りの分子が嗅球を通じて大脳辺縁系(海馬や扁桃体)に直接伝わり、記憶や感情に働きかけることが知られています。
つまり、「いい香りのサウナ体験」は、脳に記憶として強く刻まれ、“また行きたい”という快の再現性を生むのです。
さらに視覚的にも、整然と積まれたサウナストーンを見ると、脳は「秩序がある」「管理されている」という安心感を得ます。
これは前頭前皮質の報酬系が反応し、ドーパミンの分泌を促す要因になるとも考えられています。
新しいサウナストーンに交換したとき“ととのいやすくなる”理由

サウナ愛好者の多くが、「新しい石に交換された日は、なぜかととのいやすかった」と感じた経験があるのではないでしょうか。
これは決して偶然ではなく、物理的要因と心理的要因、そして脳科学的要因が重なって起こる現象なのです。
まず、物理的な面で言えば、新しいサウナストーンは表面が清潔かつ多孔質であり、ロウリュ時の蒸気発生が非常にスムーズで効率的です。
水をかけた際に十分に吸水し、細かくやわらかい蒸気を安定して発生させるため、熱が体表に均一に伝わり、「ピリピリしない柔らかい熱」を体験できます。
加えて、長年使用された石には微細なひび割れや石粉が溜まり、蒸気の質が劣化するだけでなく、焦げたような臭いを発生させることもあります。
これは自律神経にストレス刺激を与える可能性があり、ととのいを妨げる一因になります。
心理的にも、新しいサウナストーンは見た目にも「整っている」「清潔で安心できる」という印象を与えます。
これが脳に与える影響は非常に大きく、秩序だった環境に接することで前頭前皮質が報酬反応を示すことが知られています。
つまり、整えられた空間に触れたことで、私たちの脳はすでに“ととのいモード”へと準備を始めているのです。
さらに「変化」がもたらす脳の報酬系活性化も関係しています。
私たちの脳は、単調な環境よりも“ちょっとした変化”に対して強く反応します。
これは進化的にも理にかなっており、新しい刺激や環境を「報酬」や「学習のチャンス」として受け取る性質があるからです。
このとき中心的に働くのが、ドーパミン神経系、特に腹側被蓋野(VTA)から側坐核(nucleus accumbens)への経路です。
ここは「報酬系」と呼ばれ、快楽やモチベーションに関与する脳領域として知られています。
新しいサウナストーンを見たり、そこから生まれる新しい音や蒸気に触れたりすることで、脳は“予期せぬポジティブな変化”として反応し、ドーパミンが放出されやすくなります。
これにより、普段以上の快感や満足感が得られやすくなり、「ととのった」と感じる閾値が下がるのです。
また、「今日はいつもと違うな」という意識的な注意も、感覚への集中度を高め、結果としてマインドフルネス的な状態を誘導しやすくなることも分かっています。
サウナストーンと自律神経の再調整メカニズム

「ととのう」という言葉は、実際には自律神経のバランスが劇的に変化し、身体と心が“調律”されていく過程を指しています。
この変化を司っているのが、交感神経と副交感神経という2つの自律神経系です。
サウナ室で高温の環境に身を置くと、まず交感神経が優位になります。
心拍数が上がり、血管が拡張し、発汗が促される。この状態は、身体にとって軽いストレスですが、この緊張状態があるからこそ、その後の急冷(冷水浴)→静止(外気浴)で副交感神経が優位になったときに、強烈なリラックス感が得られるのです。
この切り替えがスムーズに起こるかどうかは、「最初の熱刺激の質」に大きく左右されます。
そしてその質を決定づけるのが、まさにサウナストーンなのです。
良質な石は、適度に穏やかで包み込むような蒸気を生み出し、皮膚の温点(温度センサー)にちょうどよい刺激を与えます。
また、視床下部という脳の温度制御中枢を通じて、体温調節・自律神経・内分泌機能の調整が連動します。
この一連の反応においても、石の質が体験の質を左右するのです。
あなたの“ととのい”は、サウナストーンから始まっているといっても過言ではありません。
石を見直せば、サウナが変わる。
サウナが変われば、脳と人生にもあらたな“ととのい”が生まれるかもしれません。


まとめ:サウナストーンは“脳をととのえるための五感装置”
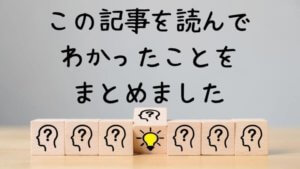
ここまで見てきたように、サウナストーンは単なる熱源ではありません。
それは、熱・湿度・音・香り・視覚といった五感を介して脳へ影響を与える高度な“装置”なのです。
現代の脳科学は、「五感を同時に刺激する体験」が、扁桃体や海馬、報酬系、前頭前皮質など、複数の脳領域を相互に活性化させることを明らかにしています。
これにより、ストレス軽減、注意の集中、情緒安定といった効果が得られ、「ととのい」という主観的な感覚へと昇華していくのです。
サウナストーンは、その五感刺激の“始点”であり、脳をととのえるためのスイッチでもあります。
サウナ愛好家であれば、ぜひ一度、自身の「石」を見直し、整備し、脳科学的に最適化された“ととのい”体験を追求してみてください。
今回のまとめ
- サウナストーンは単なる石ではなく、「五感の刺激」を通じて脳を“ととのえる”メカニズムの中核を担っています。
- 石の材質や交換頻度を見直すことで、より深いリラクゼーションや集中感を得ることが可能になります。
- 脳科学的視点から見ても、サウナストーンは心身のバランスを整える“仕組み”の一部として非常に理にかなっているのです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
最後にポチっとよろしくお願いします。