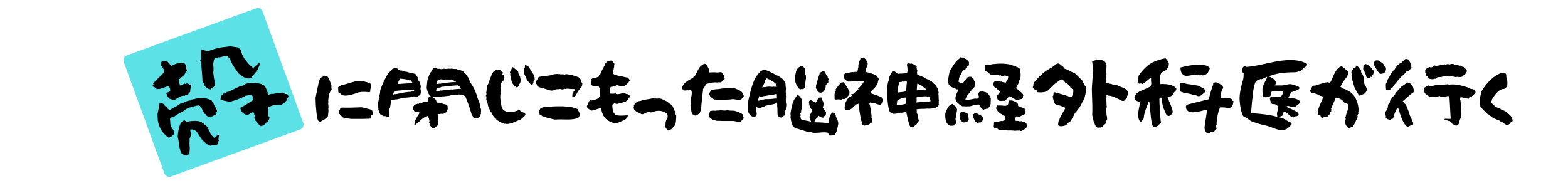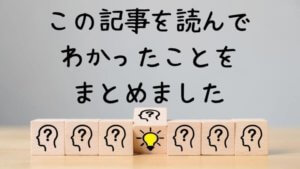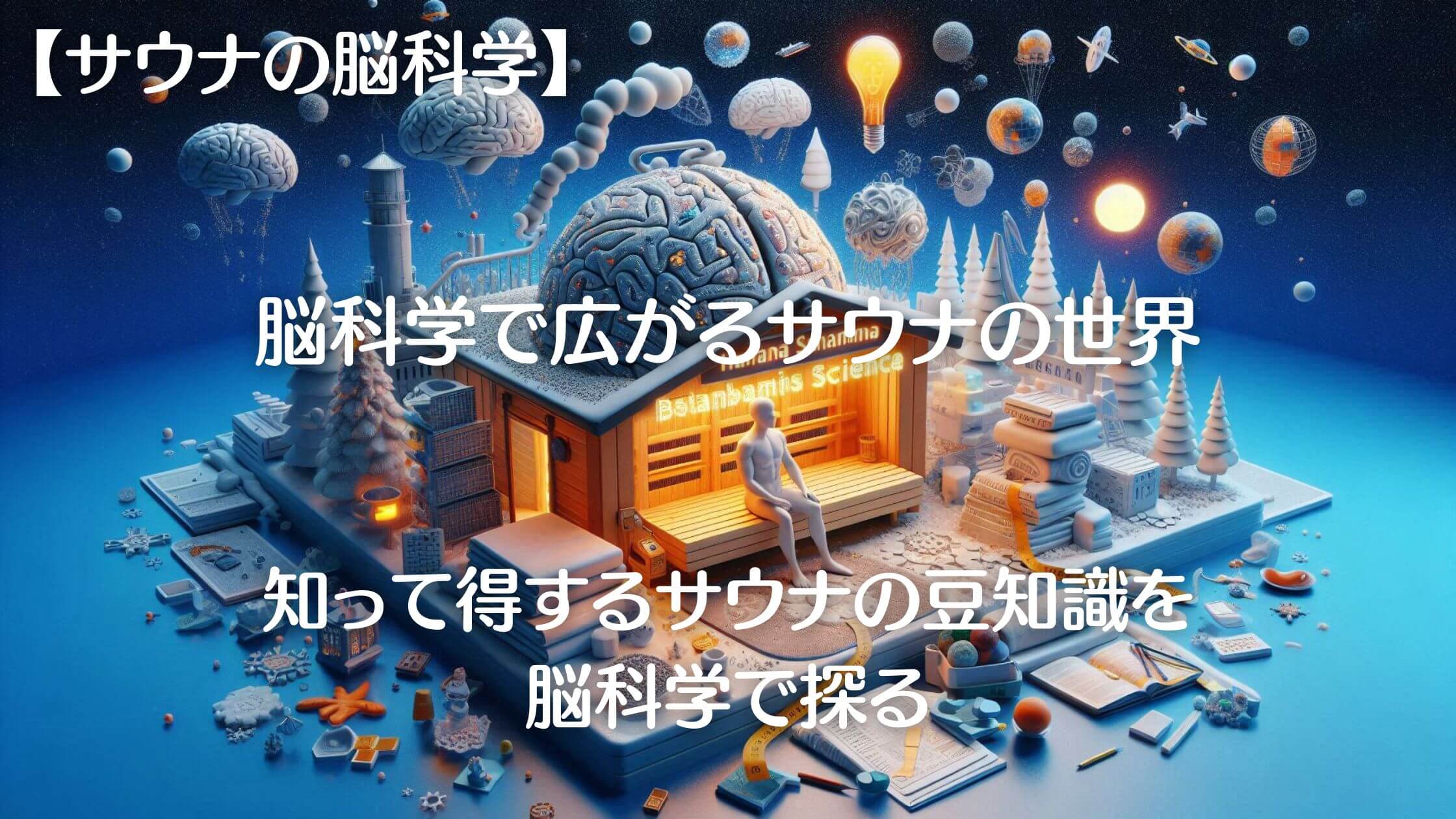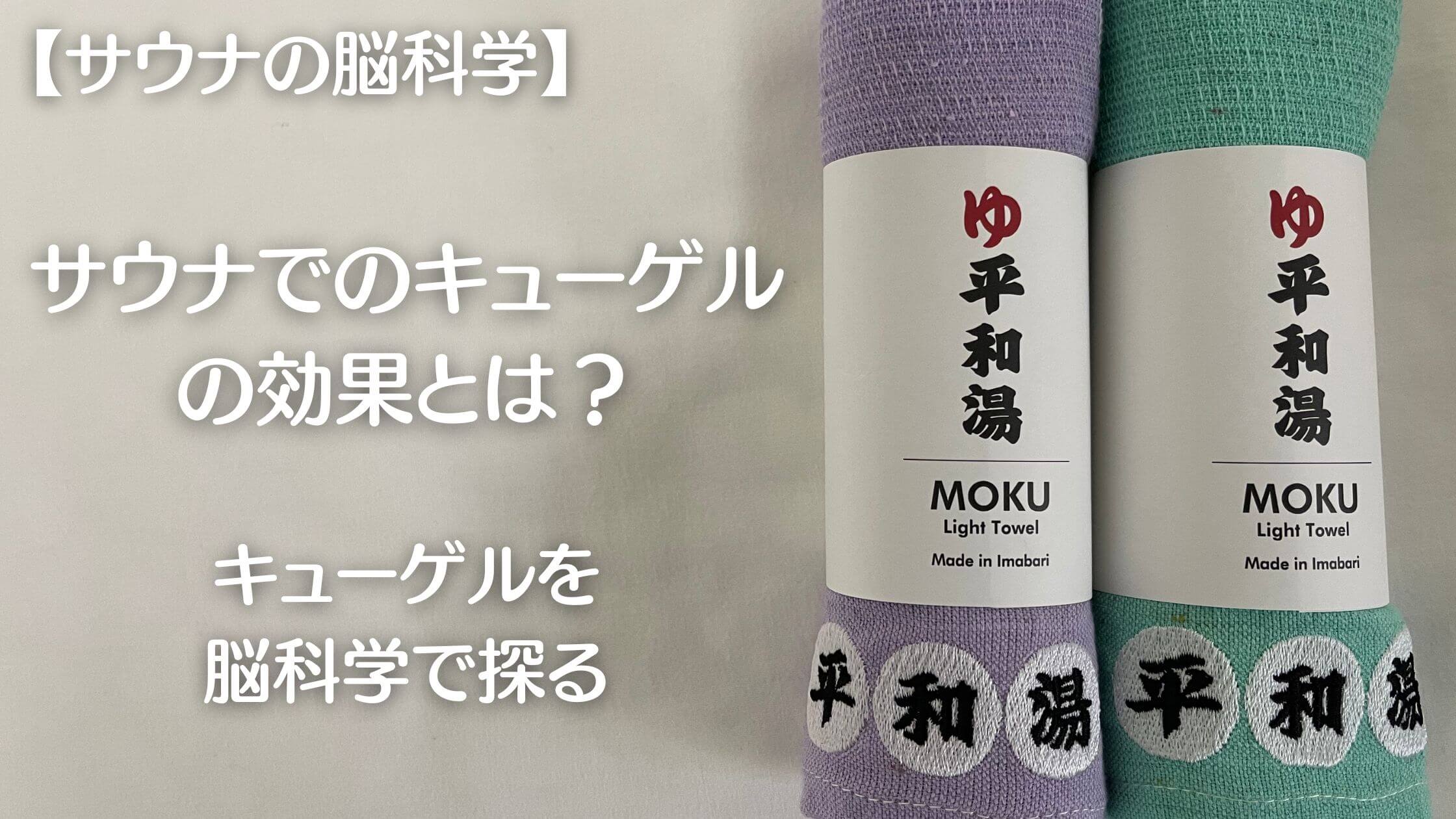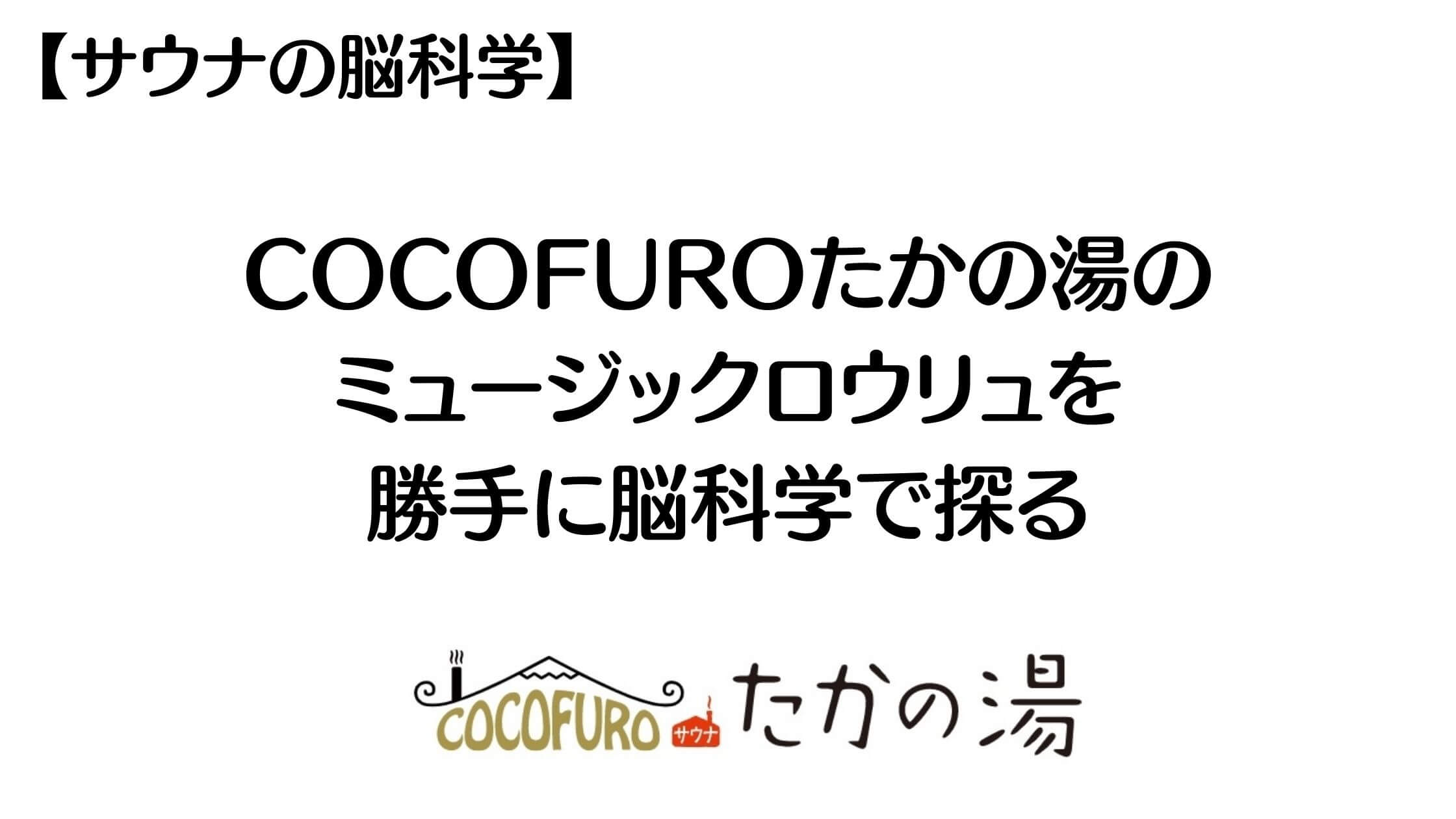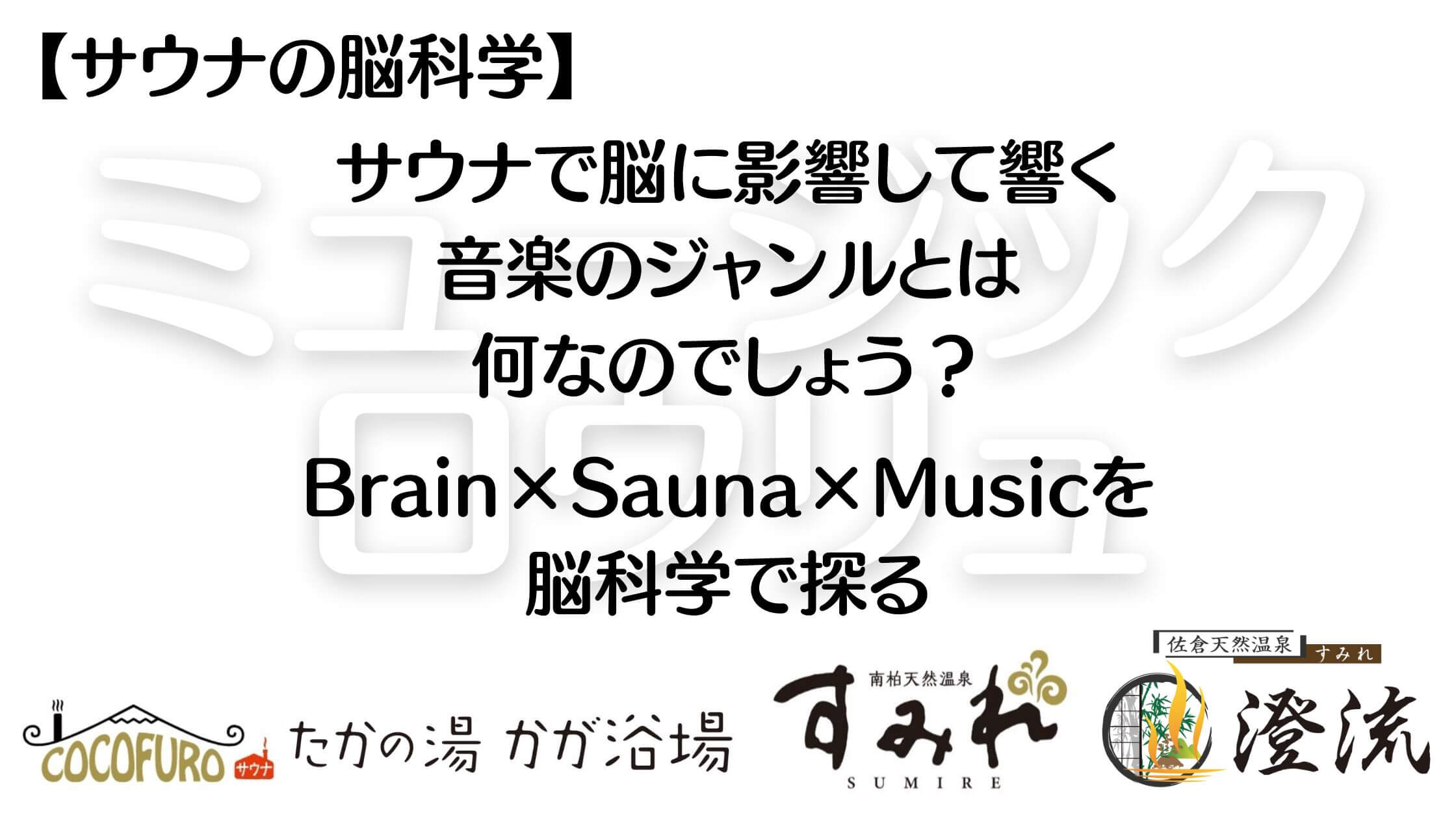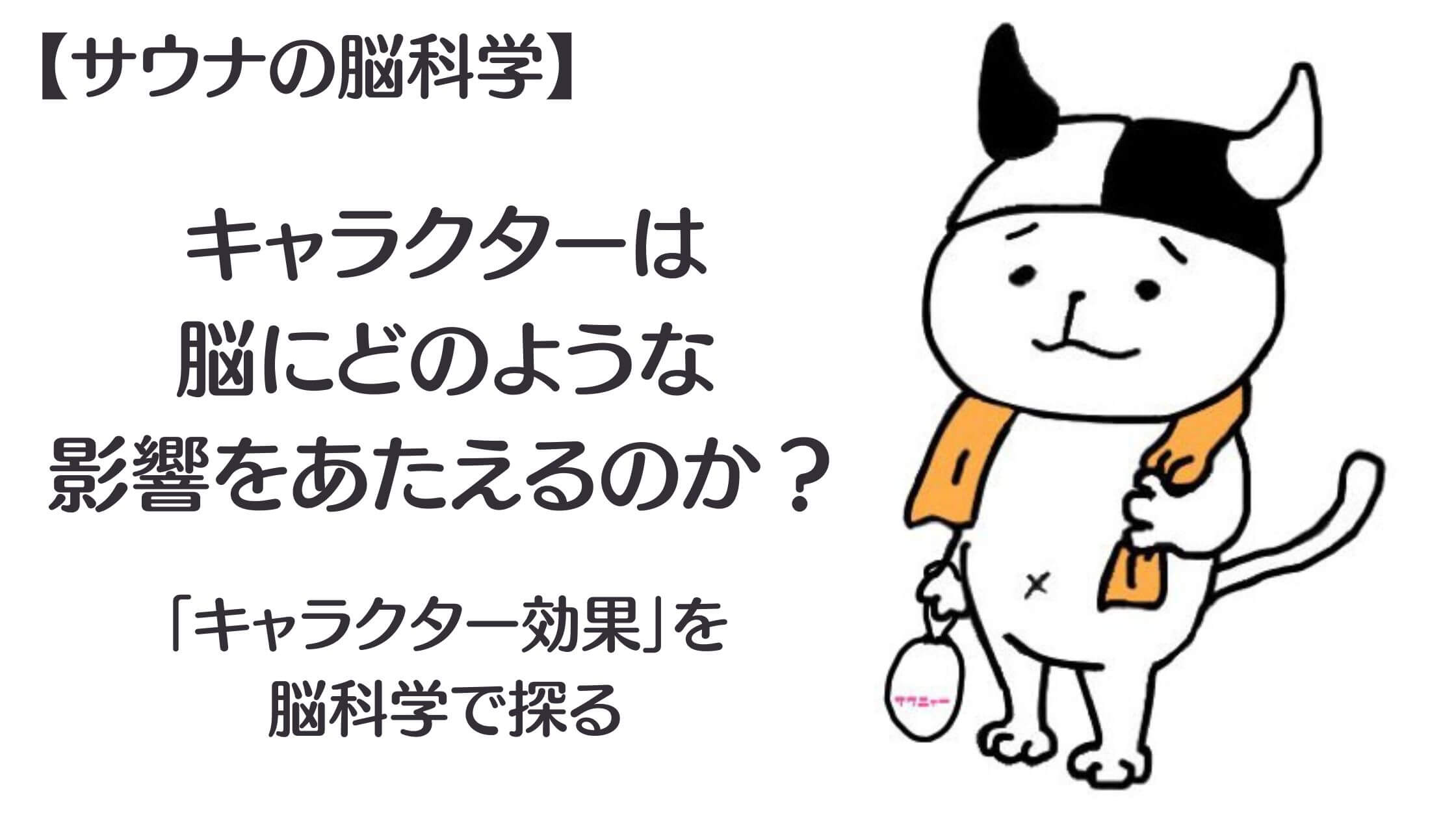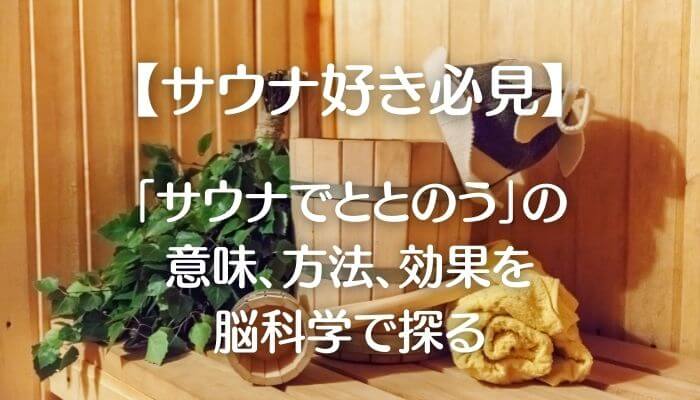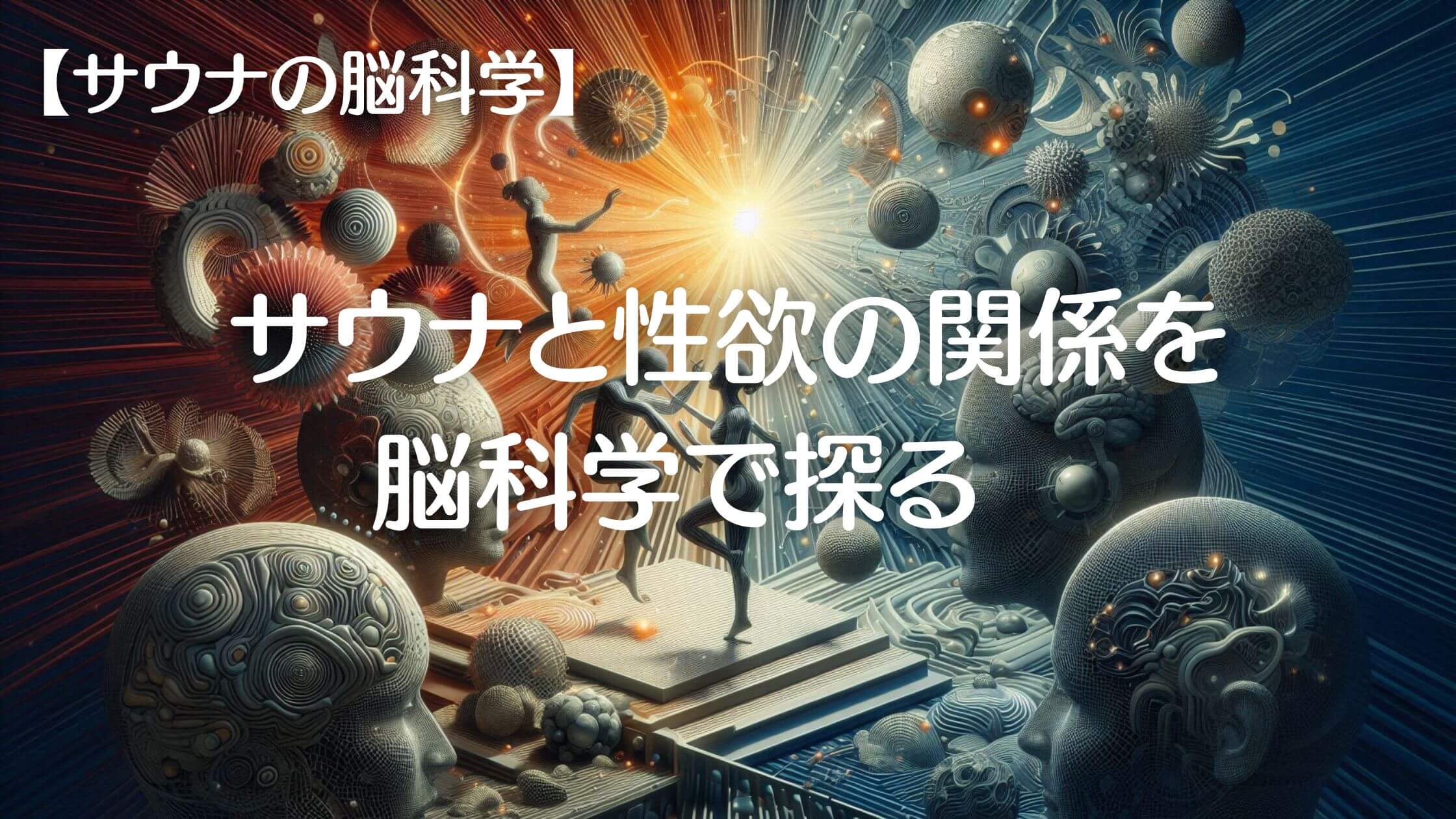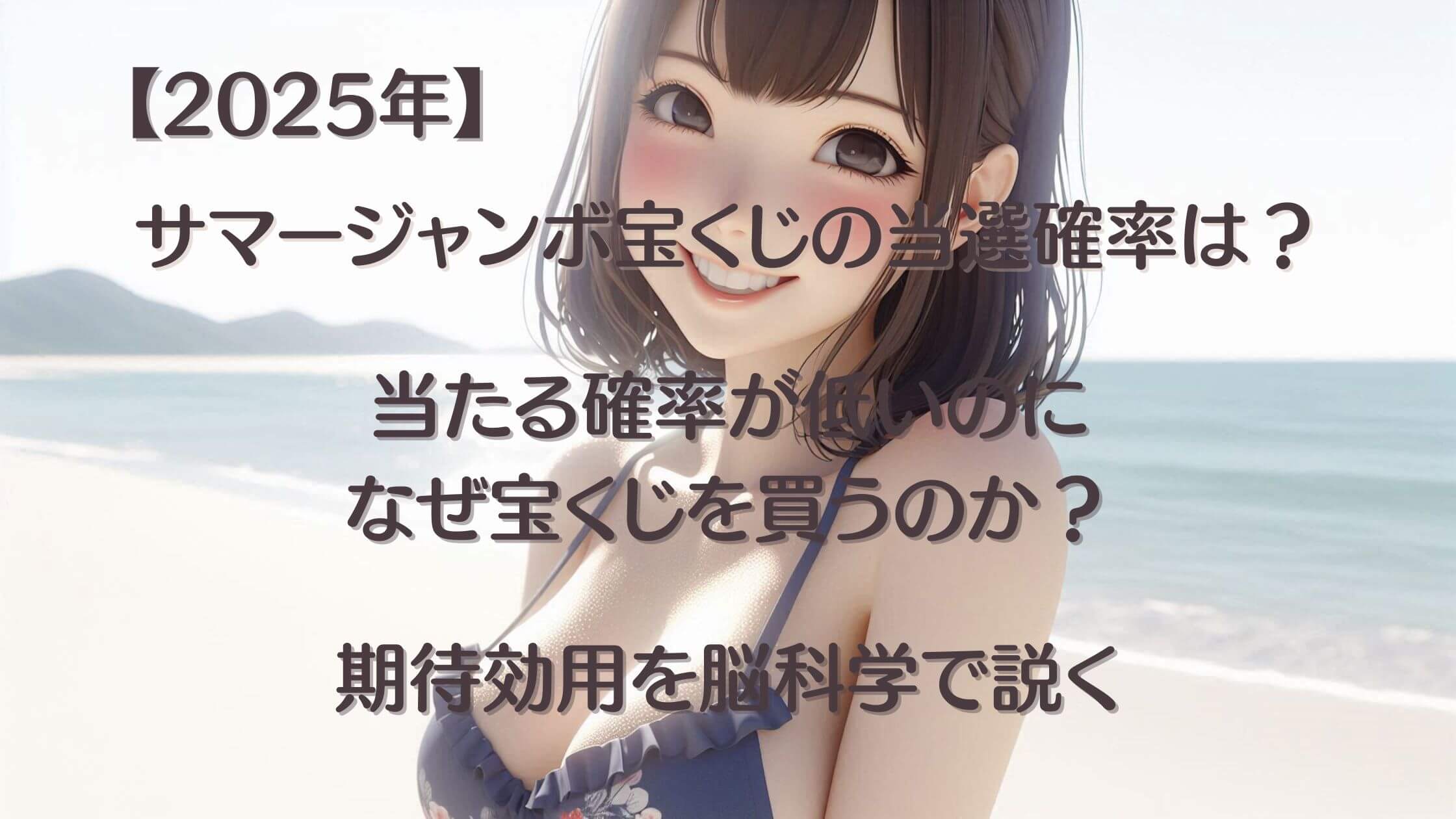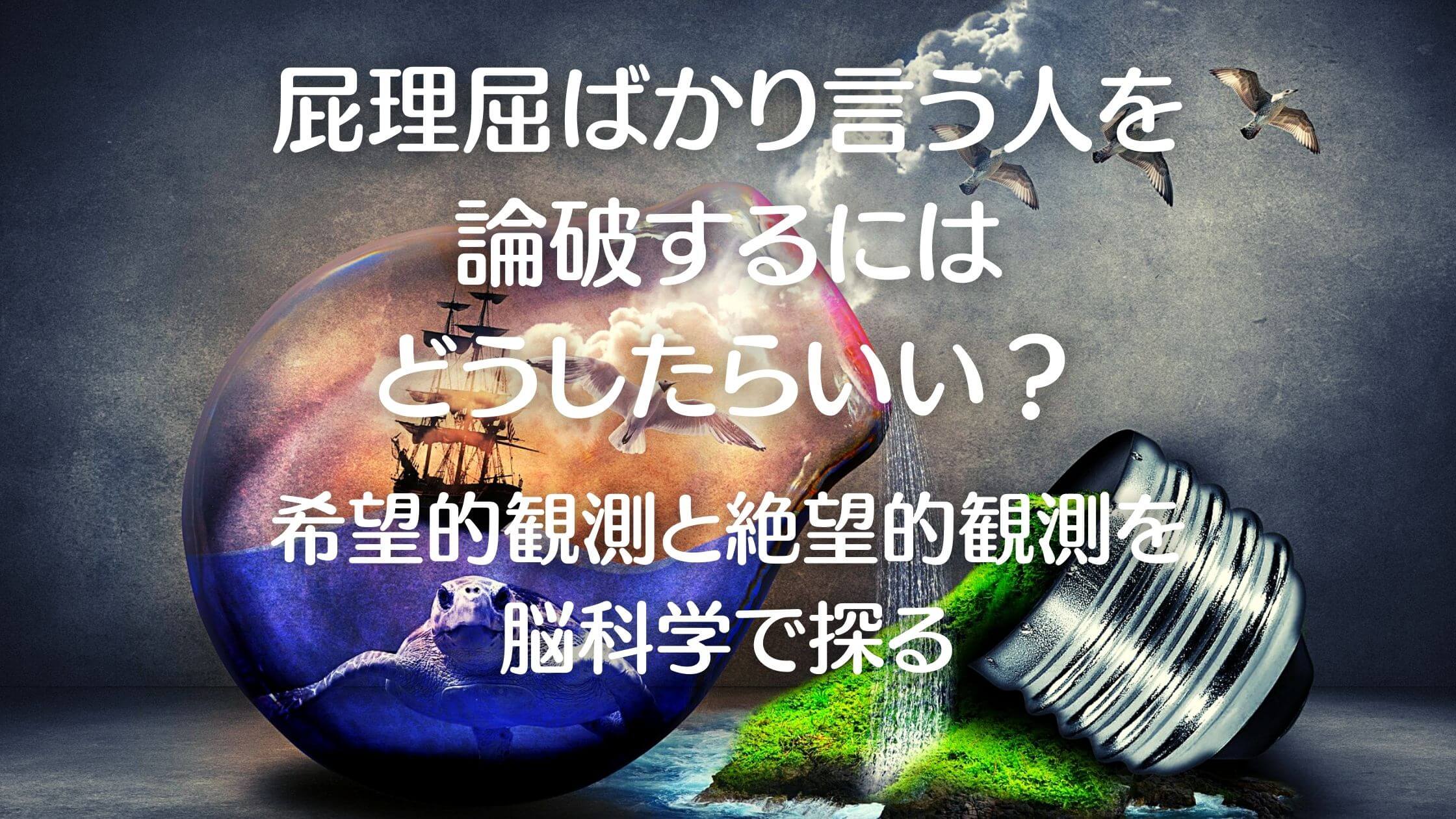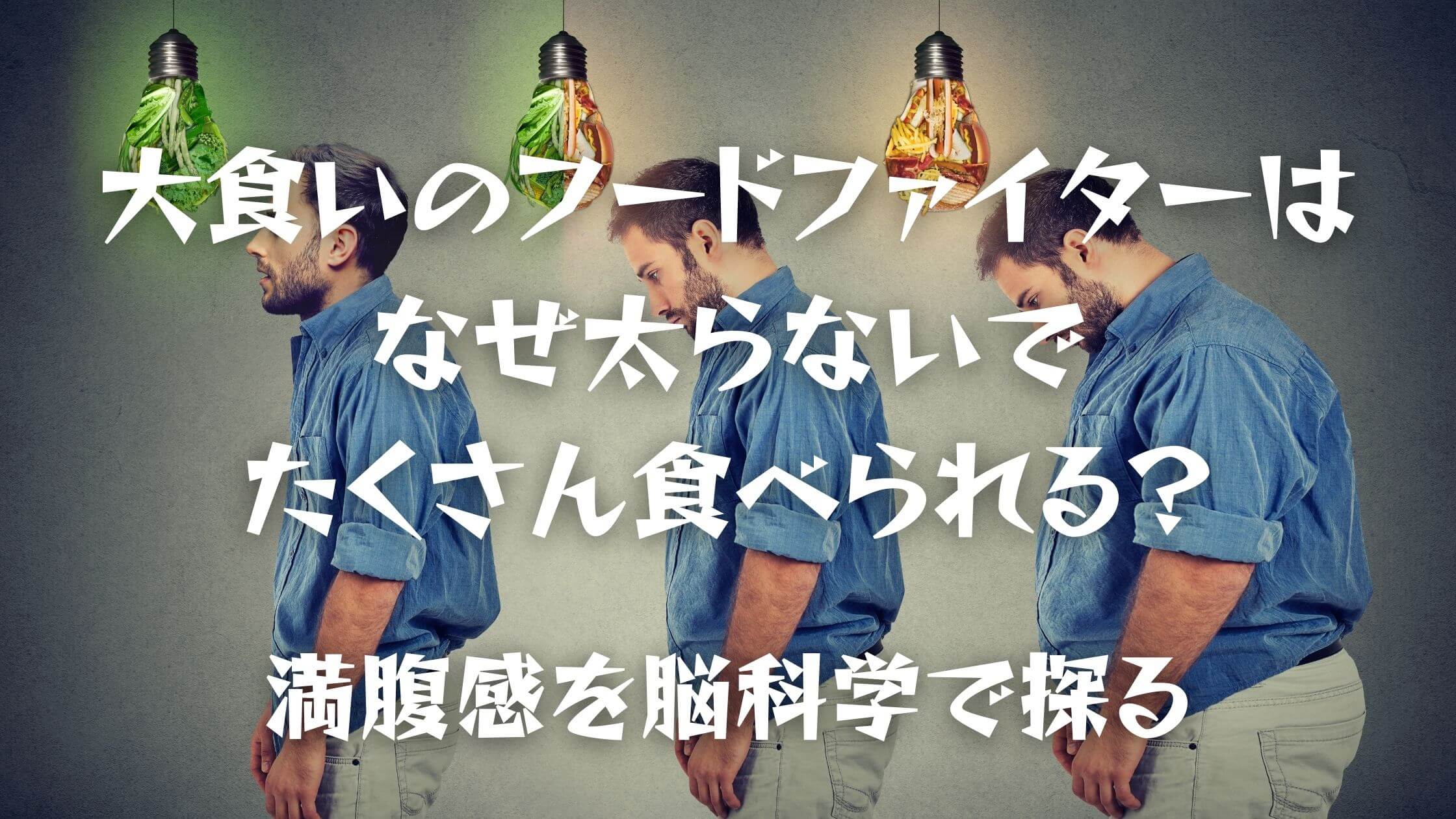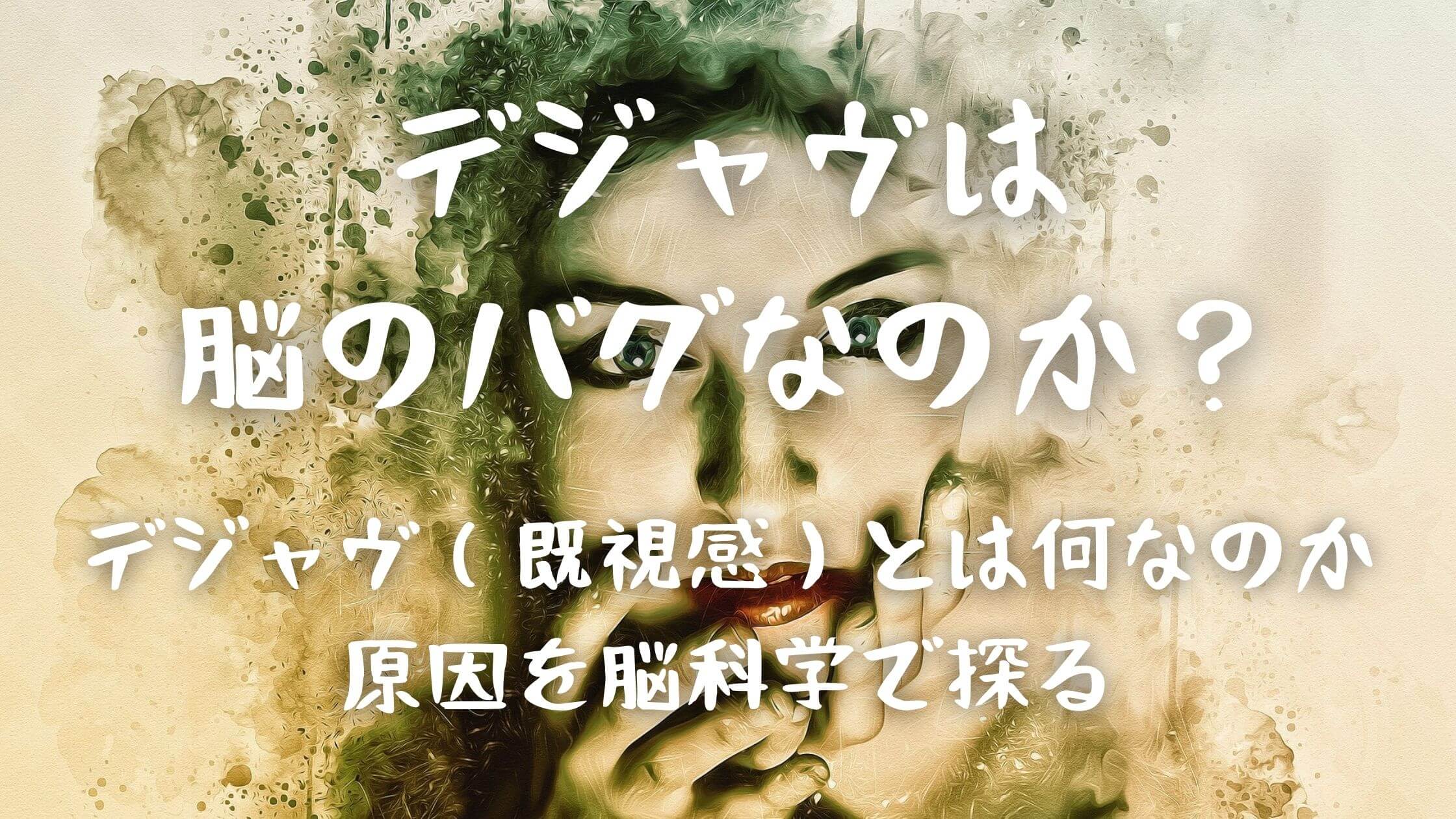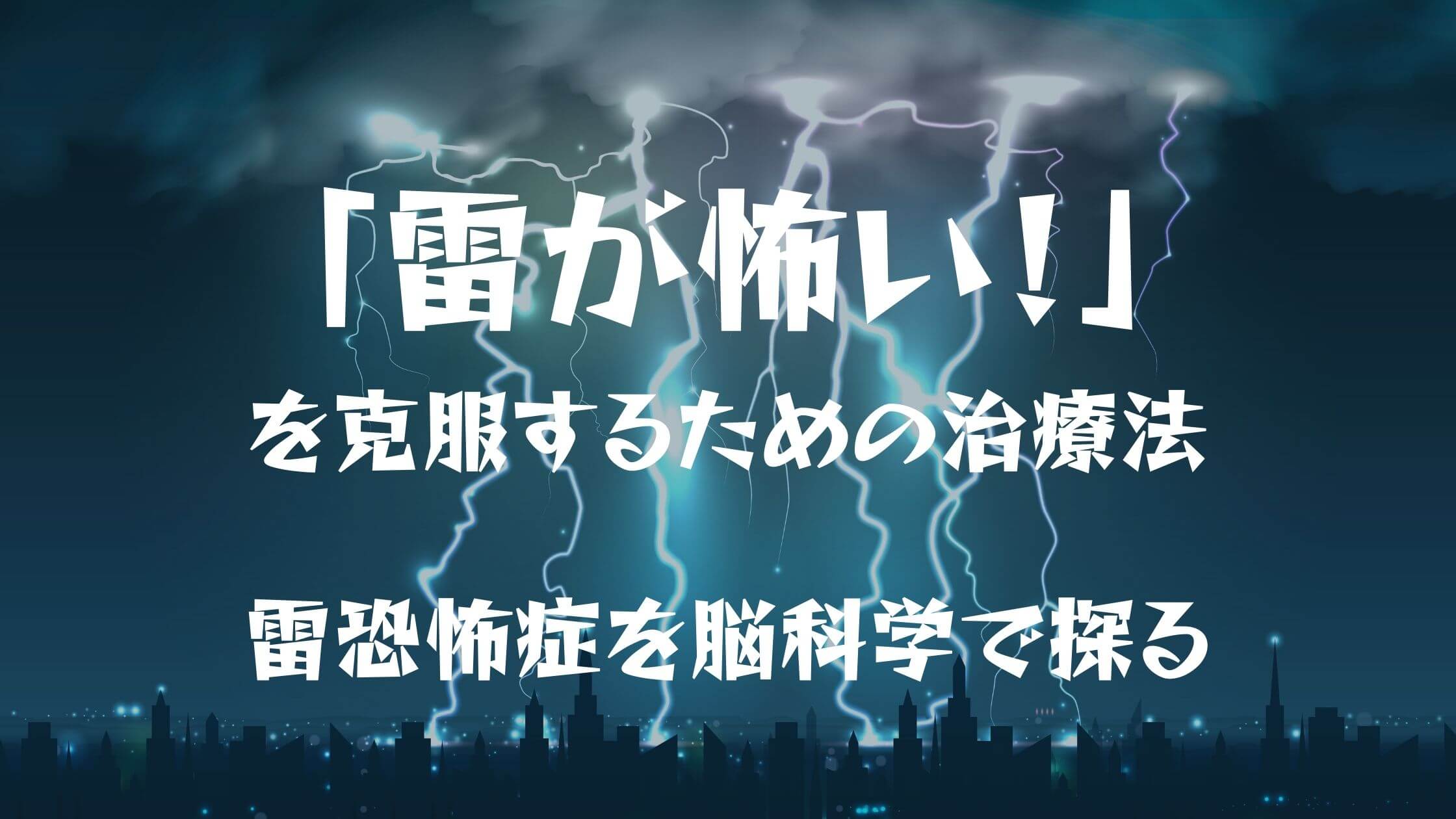モノクロの世界の意味と魅力ってどこにあるの?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。
この記事を読んでわかることはコレ!
- 色彩心理効果を脳科学で説き明かします。
色彩心理効果って何?
色彩心理効果の脳科学
- 色彩心理効果によって色は脳にさまざまな影響を与えます。
- ヒトは色を認識する能力はあまり高くはありませんが、色を処理してカラーの世界を作り出す能力はとても優れています。
- しかしそれ以上に、モノクロの世界に自分の好きな色を自由に想像して塗りまくることにたまらない快感を覚えます。

色彩心理効果
色が行動や思考に及ぼす影響を「色彩心理効果」と言います。
色によってモノのイメージをしたり気分を変えたり、時には健康に影響することだってあります。
寒い色と暖かい色
軽い色と重い色
興奮する色と沈静する色
柔らかい色と堅い色
進出する色と後退する色
膨張する色と収縮する色
あげたらキリがありません。


世界中のどの文化圏でも共通して人の心を吸い寄せる魅力的な色は「赤」です。
“赤の脳科学”についてはこちらの記事をご参照ください。
-
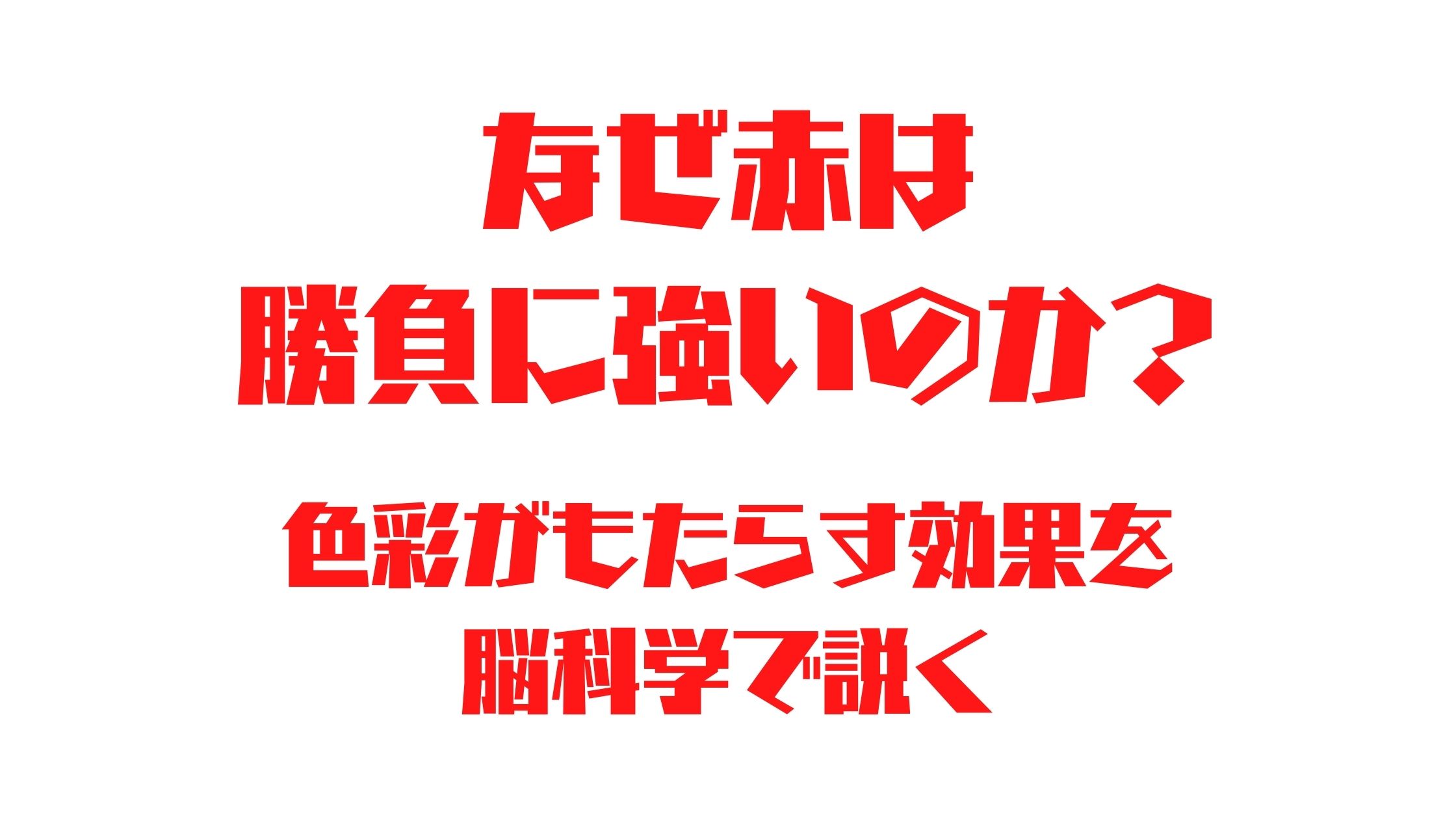
参考なぜ赤は勝負に強いのか?~色彩がもたらす効果を脳科学で説く
赤は勝負に強い色って本当なの? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として ...
続きを見る
人が赤に惹かれる理由はいろいろありますが、一番の理由は血液にあると考えられています。
酸素が結合した色鮮やかな血液の赤色は、心肺が健康であることのいわば象徴です。
血液が活き活きと流れる毛細血管は気分が高揚している状況を表します。
脳はそのような血液の状況に瞬時に反応します。

ショーウインドウや危険表示には赤色が目を引き効果的です。
勝負ごとでも赤は効力を発揮します。
ボクシングやレスリングなどの格闘技では、赤コーナーの方が青コーナーよりも勝率が高いことが知られています。
サッカーのPKではキーパーが赤色のユニフォームを着ていると、ゴールをきめる成功率は下がると言われています。
このように色には不思議な力があります。



色彩心理効果の脳科学-その1
色の持つ不思議な力を理解してこそ、モノクロの意味と魅力がよりわかりやすくなるのです。

色の持つ意味と効果を探る
ヒトの脳は色を認識する能力においては、残念ながら他の動物と比較してとても劣っています。
そもそも「色」とは何なのでしょう?
わたしたちは目から入った光を目の中の網膜の色彩センサーで電気信号に変換して脳で受け取っています。
つまり脳に入力される情報は電気信号であって、光そのものではありません。
脳はこの電気信号を「色」として読み解いているのです。
色彩心理効果の脳科学-その2
ヒトが認識できる光は赤・緑・青の3種類のみであり、「光の3原色」と呼ばれています。
ヒトの認識する3原色は動物界では特殊なケースです。
多くの哺乳類は橙と青の2原色です。
一方鳥類や昆虫の多くは赤・緑・青の3種類に加えて、紫外線を認識できるので4原色です。

初期の動物たちは、4つの色のセンサーを使って世界を眺めていました。
ところが進化の過程で次々と色感覚を失ってゆき、最終的に2原色になってしまいました。
当時の哺乳類の多くは夜行性でしたから、2原色でも生活に差し支えなかったのでしょう。
その後、一部の哺乳類は昼行性になると、2原色のうち橙色のセンサーを2つに分離させて緑と赤のセンサーを生み出したのです。
これが3原色のルーツとされています。
とはいえヒトには紫外線は見えません。

ですから鳥や虫たちの視覚世界は知り得ません。
紫外線カメラで撮影を行うと、世界が見たこともない鮮やかな色彩に満ちていることに驚きます。
しかし鳥や虫たちにとってはこの鮮やかな世界は当たり前の光景です。

色彩心理効果の脳科学-その3
ヒトの脳は、どんな動物にも負けないくらいすさまじく発達して進化しているのに、残念ながら網膜の色彩センサーは脳の性能に見合った発達をしていないのです。

地球上でもっとも多くの色彩センサーを持ち合わせているのは、なんと甲殻類の「シャコ」です。
シャコはなんと12色もの色彩センサーを持っています。
ヒトの4倍ですから、想像のつかないほどの豊かな色彩の世界に生きているのでしょう。
と思いきや実はそうでもないのです。
シャコの色の識別能力を調べたおもしろい研究があります。


なんとシャコはこれだけの色彩センサーを持っていながらにしてほとんど色を区別できないのです。
もっとも識別しやすそうな赤と青の区別すらできません。
シャコは優れた色彩センサーを持っていますが、それを認識する脳の神経が充分に発達していないのです。
つまり脳の中で色彩センサーから送られてきた電気信号をうまく処理できないのです。

しかも色をブレンドして…たとえば「赤」と「緑」から「黄」を生み出すこともできません。
結果としてシャコは光があるかないかだけの、実質的には「モノクロの世界」に生きていることになります。
ヒトとは逆で、脳よりも色彩センサーが進化しすぎているのです。
色彩心理効果の脳科学-その4
一方で、ヒトの脳は3つしかない色彩センサーから送られてきた乏しい電気信号を、脳の中でさまざまにブレンドさせて目の前には存在しない色を次々と作り出します。
右目に緑、左目に赤の光を当てると脳は「黄」を生み出します。

とここまでは色が持つ意味と効果について説明してきました。

色彩心理効果の脳科学-その5
色に対してすさまじい処理能力を示すヒトの脳は、意外にも「カラーの世界」よりも、実は「モノクロの世界」の方がお気に入りなのです。

モノクロの持つ意味と魅力を探る

ちなみに自分はクラシック音楽は好きですが、たいして耳が肥えていないので細かい音の違いまではわかりません。
たとえばベートーヴェンの交響曲を聴いたとします。
さまざまな指揮者がさまざまな交響楽団を率いて、多くの録音がされて世に出回っています。

古き時代の名指揮者が名交響楽団を率いて何十年も前に録音されたモノラル録音の音源は、最新のステレオ音質に比べてどうしても貧弱な音質に聞こえてしまいます。
しかし耳の肥えたクラシック音楽ファンにとっては、熱気のある演奏によって奏でられた壮絶な交響曲は、モノクロであっても最新のデジタルサウンド顔負けの「総天然色」の薫りを放っているのです。

映画ファンにとっては、名映画監督が撮影したモノクロの名映画たちは、「単色さ」を全く感じさせない色彩豊かな作品に映ります。


「白黒なのにカラフル」とは「色があれば色彩が豊かになる」とは限らないということです。
モノクロとカラーの世界の違いについての研究をご紹介しましょう。
画面に色鮮やかなバナナの写真が写っています。
バナナはヒトの脳が赤と緑から生み出した美しい黄色です。
ここでレバーを左右に動かすとバナナの鮮やかな黄色が変化します。
左に動かすと次第に色あせていき、ついには完全な「白黒写真」になります。
そのままさらに左に動かし続けるとまるでネガ写真を見るように反射色である「青色」のバナナへと変化します。
さてそのように自由自在にバナナの色を変化させることができる状況において

とお願いします。
すると不思議なことに、ほぼすべての人が白黒ぴったりのポイントではなく、わずかに青みがかったところでレバーを止めるのです。
つまり真に白黒の状態だと、ヒトの目にはバナナはまだ黄色に見えるということです。
完全に白黒に見えるためには、わずかに青みがかっている必要があるのです。

今度はバナナでなく、不規則な見たことのない形状をした黄色のモノを用いて同じ実験をしてみます。
すると今度はちょうど白黒のポイントでレバーを止めるのです。

わたしたちは「バナナは黄色である」ということを経験則から知っているので、たとえモノクロ写真でも実際のバナナを見るかのように黄色みを帯びて潜在的に見てしまうのです。
ですから多少青みを混ぜてあげないと黄色をかき消すことができないわけです。

“経験則の脳科学”についてはこちらの記事をご参照ください。
-

参考知らないと損をする「ヒューリスティック」とは~経験則を脳科学で探る
経験則って正しいの? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた ...
続きを見る
色彩心理効果の脳科学-その6
経験則から色を想像で補って、記憶にある理想のイメージ像に近づけようとするのは脳の独特の能力です。
この脳の創造力は、ステレオ録音よりもモノラル録音を愛し、カラー映画よりもモノクロ映画を楽しむ源になっています。
脳の持つ想像力は無意識的に湧き上がってくるものです。
原作小説を読んで抱いていたイメージが、しばしば映像化されることで壊されてがっかりするのも、こんな脳の理想化力によって必然的に引き起こされているのかもしれません。
色彩心理効果の脳科学-その7
ですから自由に想像力を膨らませて自分の理想の世界を作りやすいモノクロの世界をヒトの脳は好むのです。
自由に塗り絵をすることに脳は快感を覚えるということです。
“快感の脳科学”についてはこちらの記事をご参照ください。
-
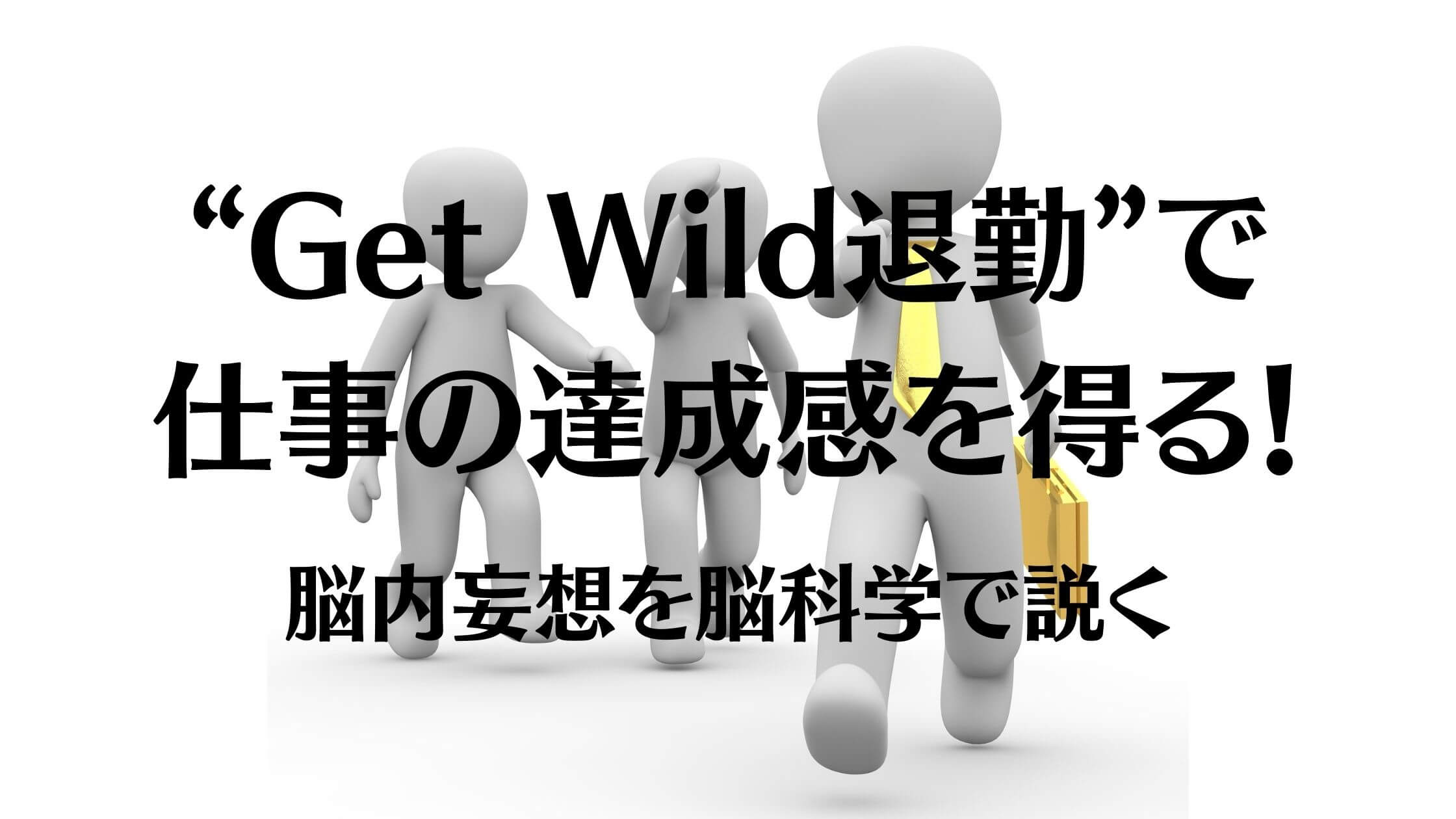
参考“Get Wild退勤”で仕事の達成感を得る!脳内妄想を脳科学で説く
「”Get Wild退勤”で仕事の達成感を得る」とはどういうことなのでしょうか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医と ...
続きを見る

なにせモノクロの世界では自由に脳の中で色塗りをして、自分のお気に入りの映像を作り出すことができるのですから…


“色彩心理効果の脳科学“のまとめ
モノクロの世界の意味と魅力を色彩心理効果を脳科学で探ることで説き明かしてみました。
今回のまとめ
- 色彩心理効果によって色は脳にさまざまな影響を与えます。
- ヒトは色を認識する能力はあまり高くはありませんが、色を処理してカラーの世界を作り出す能力はとても優れています。
- しかしそれ以上に、モノクロの世界に自分の好きな色を自由に想像して塗りまくることにたまらない快感を覚えます。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわりのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
最後にポチっとよろしくお願いします。