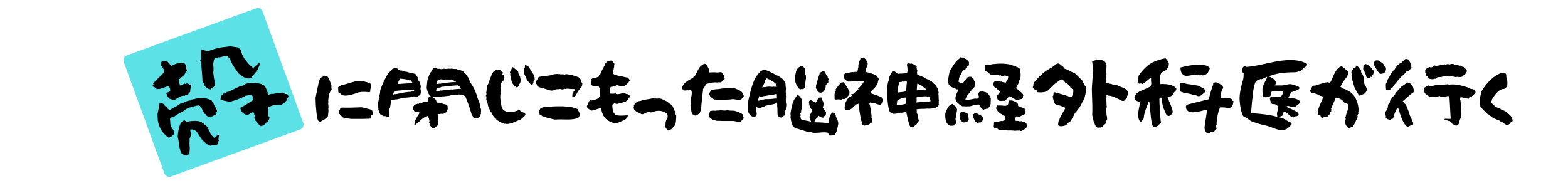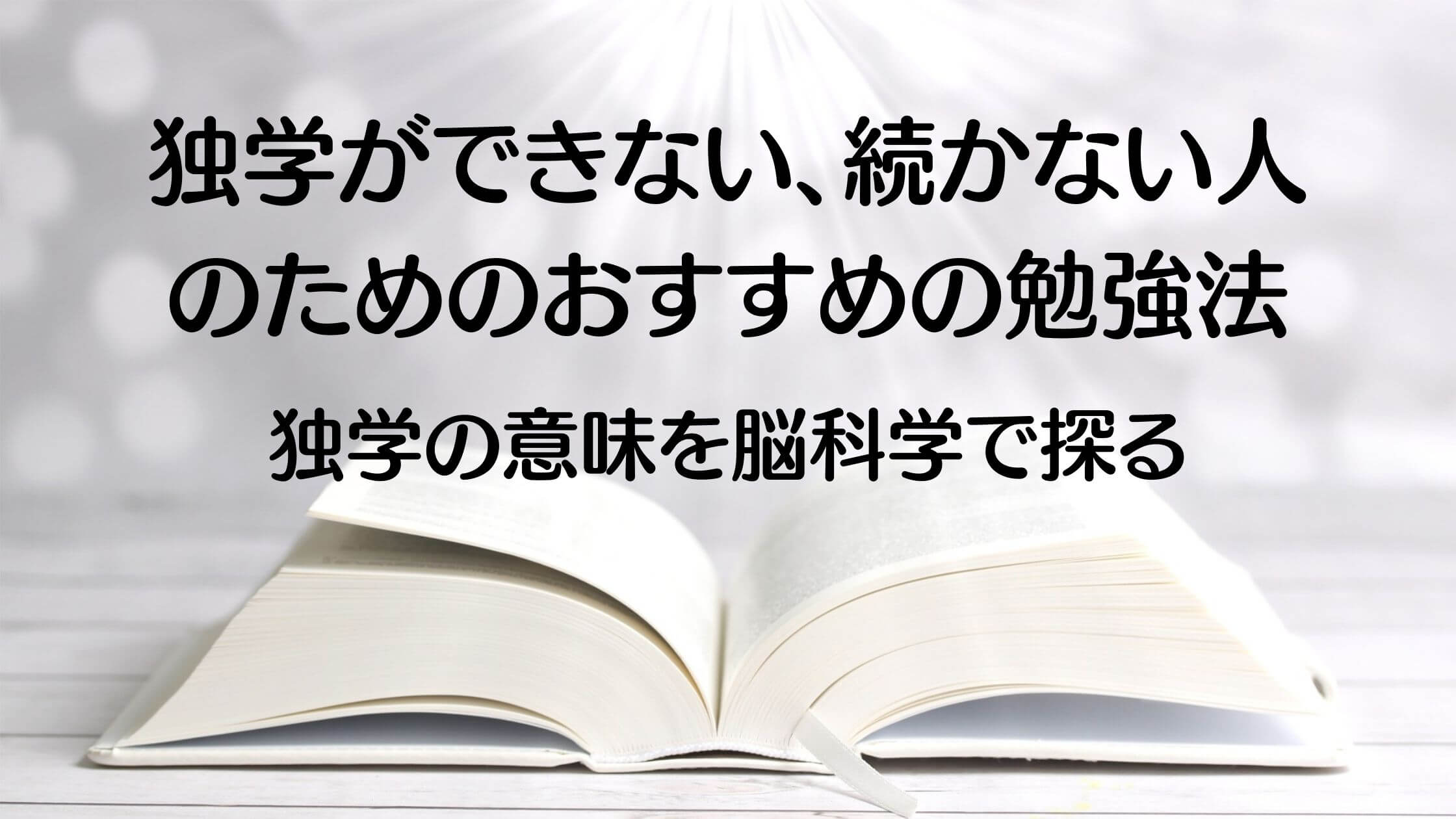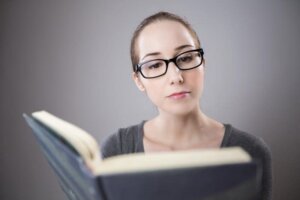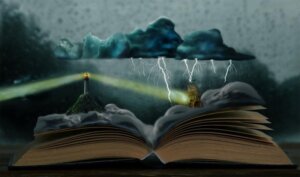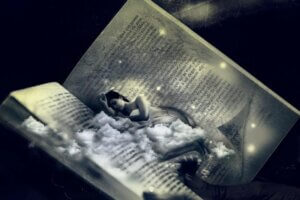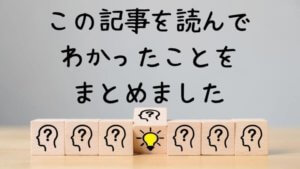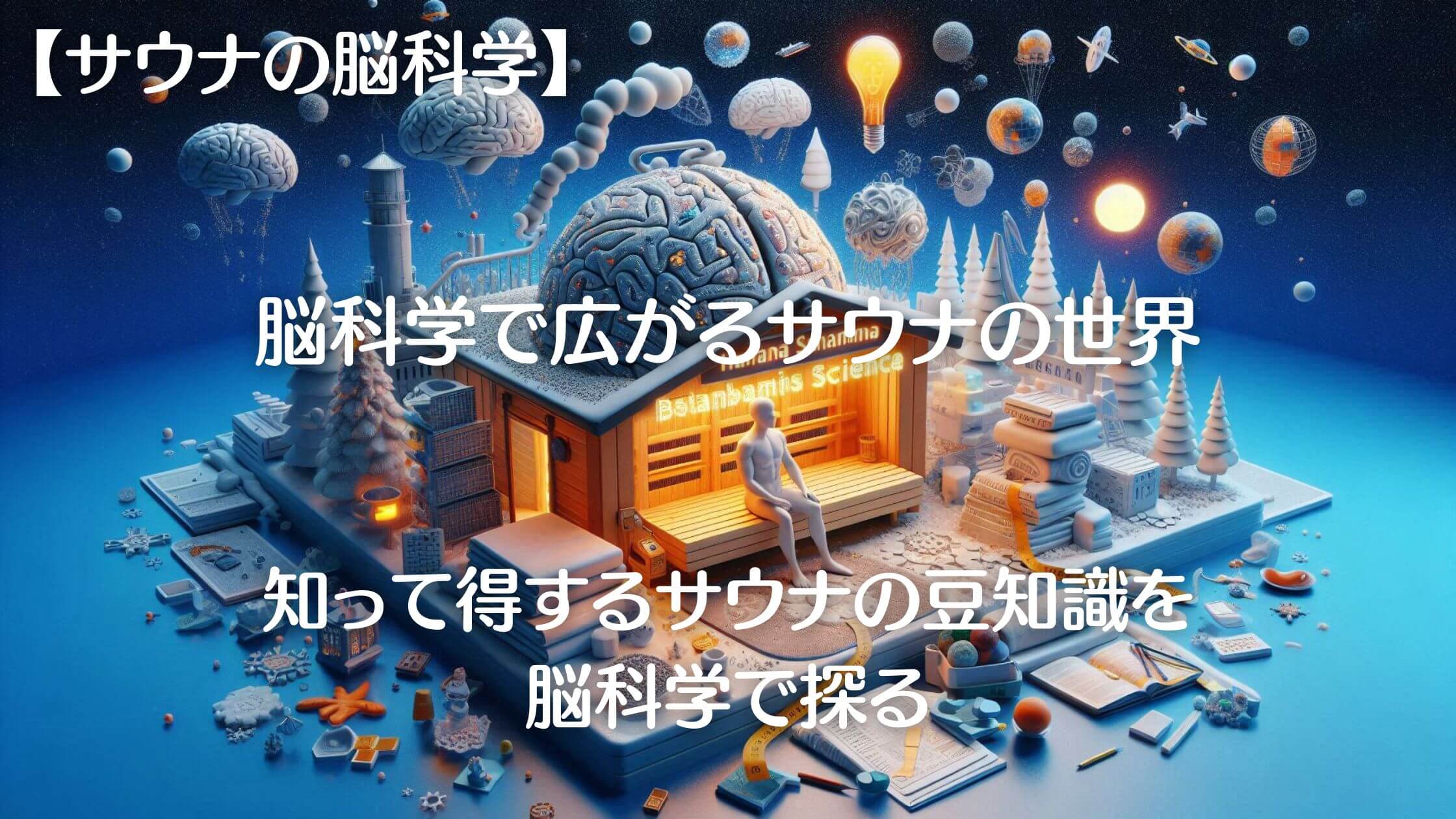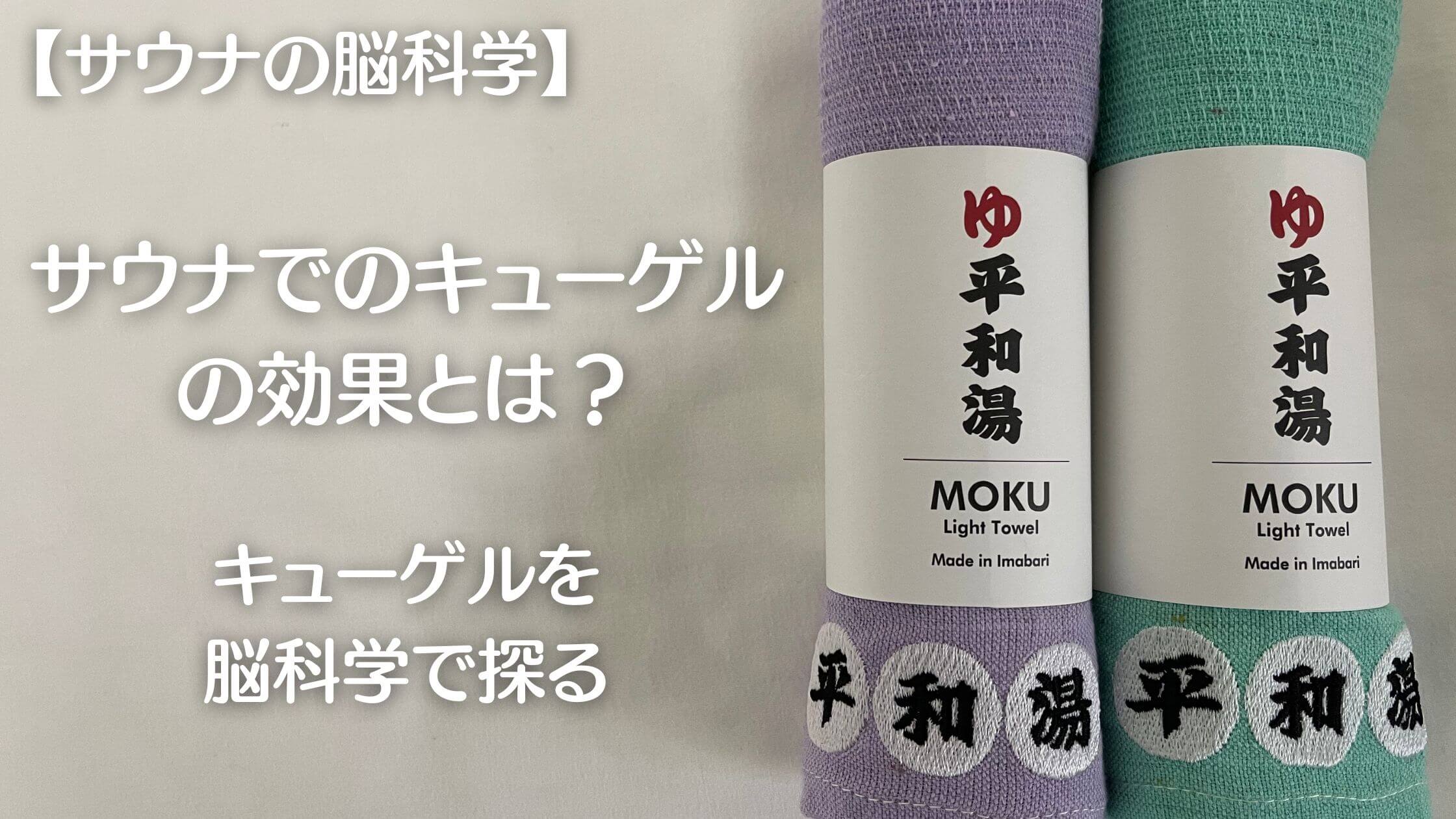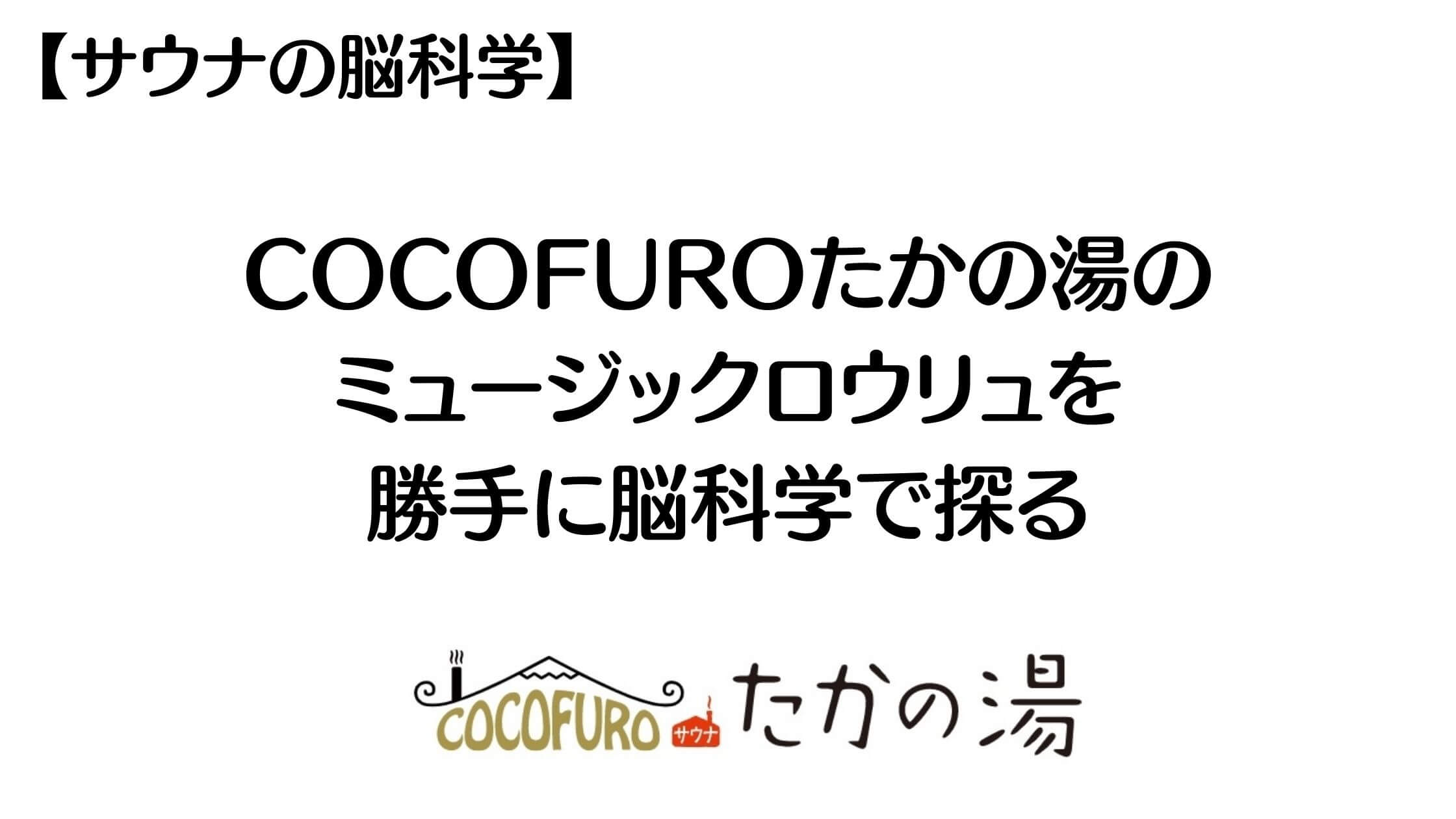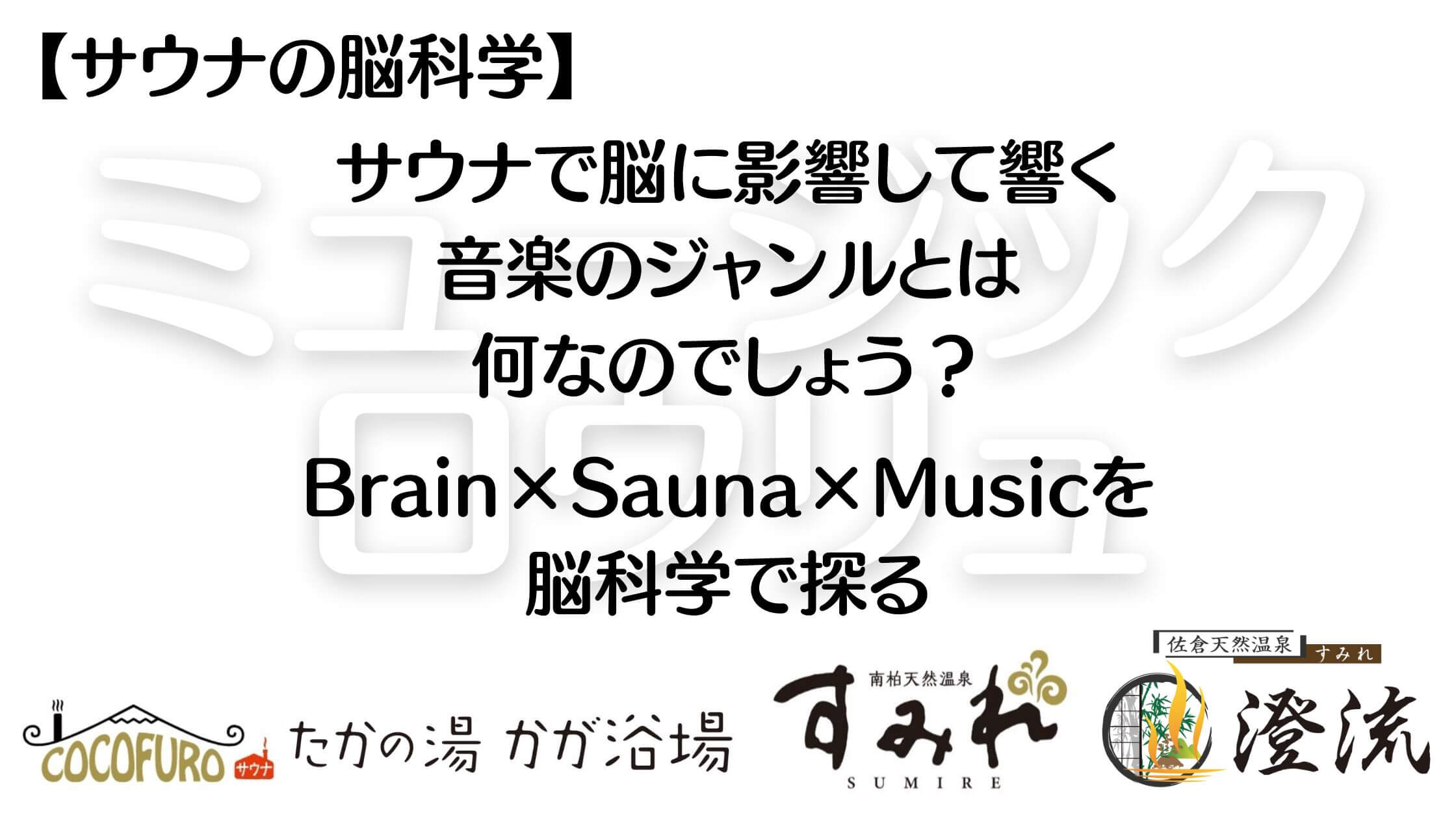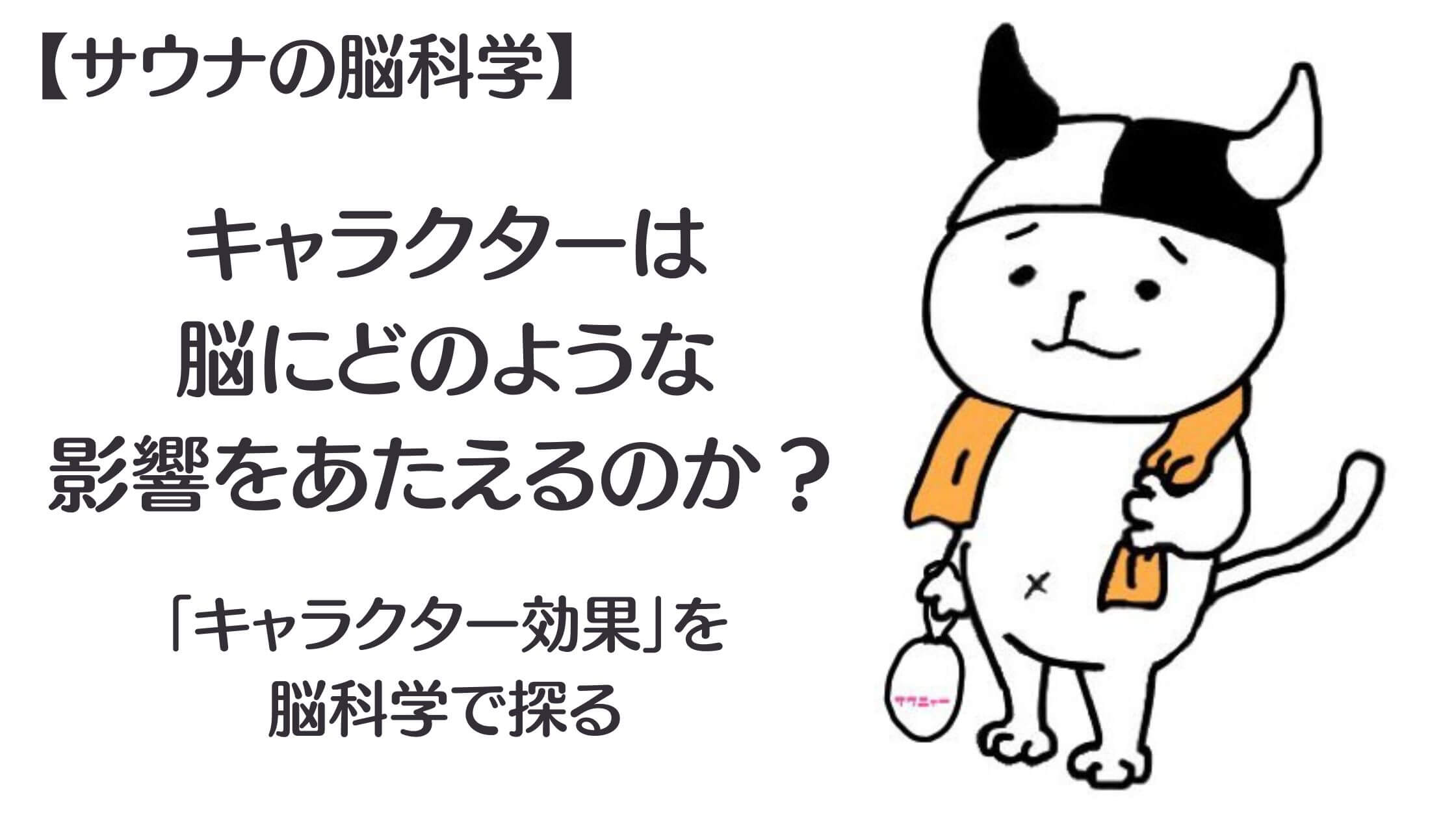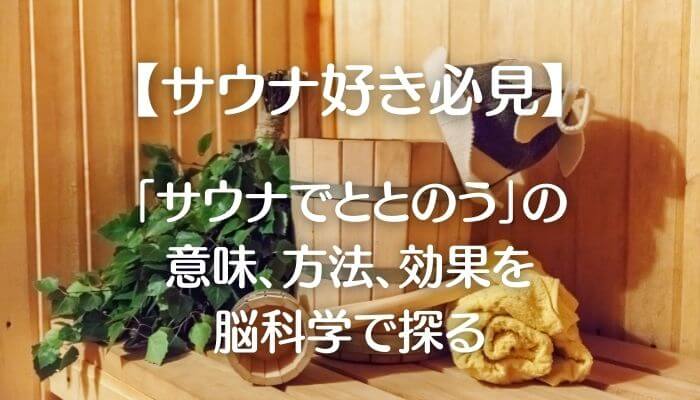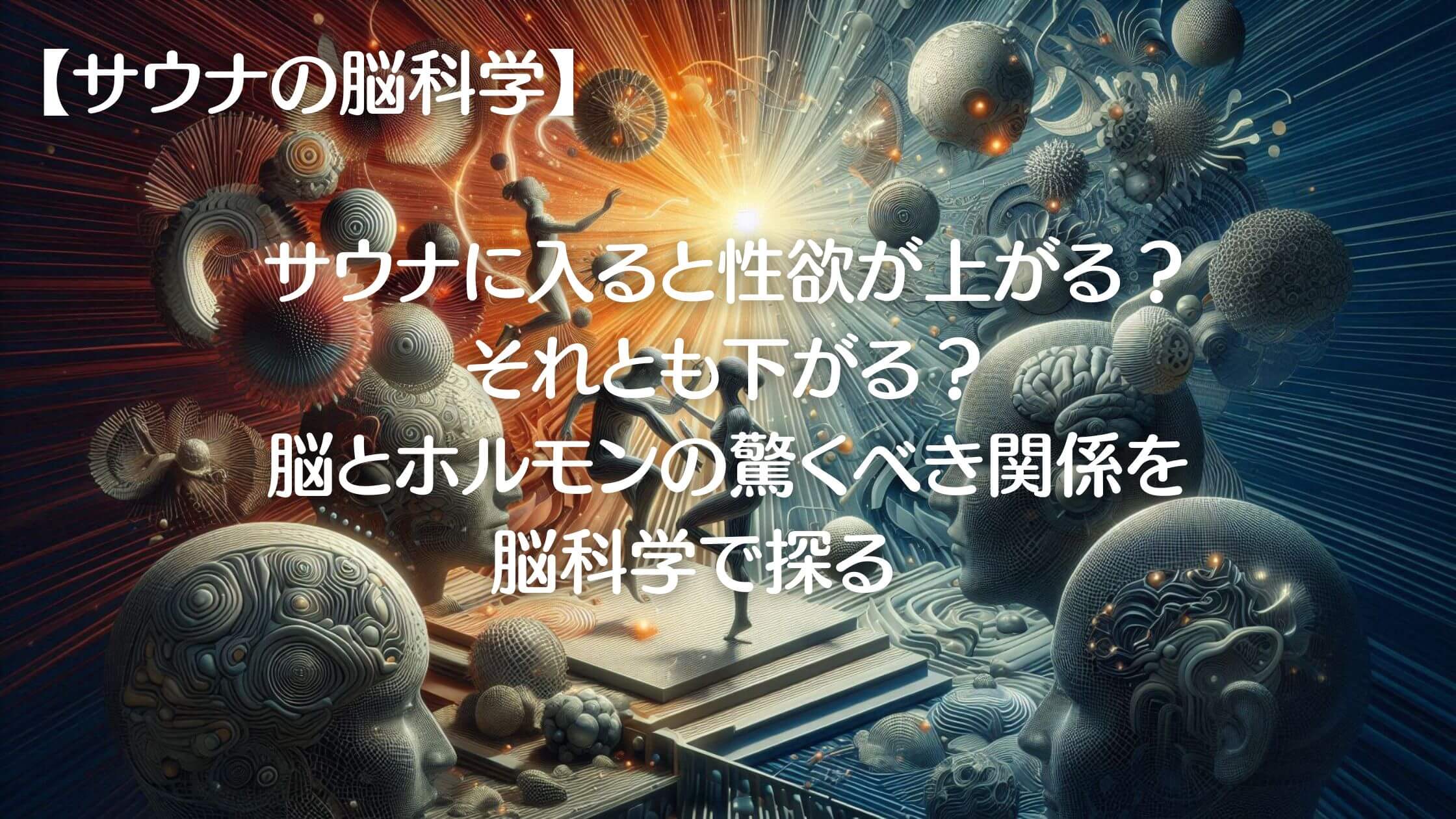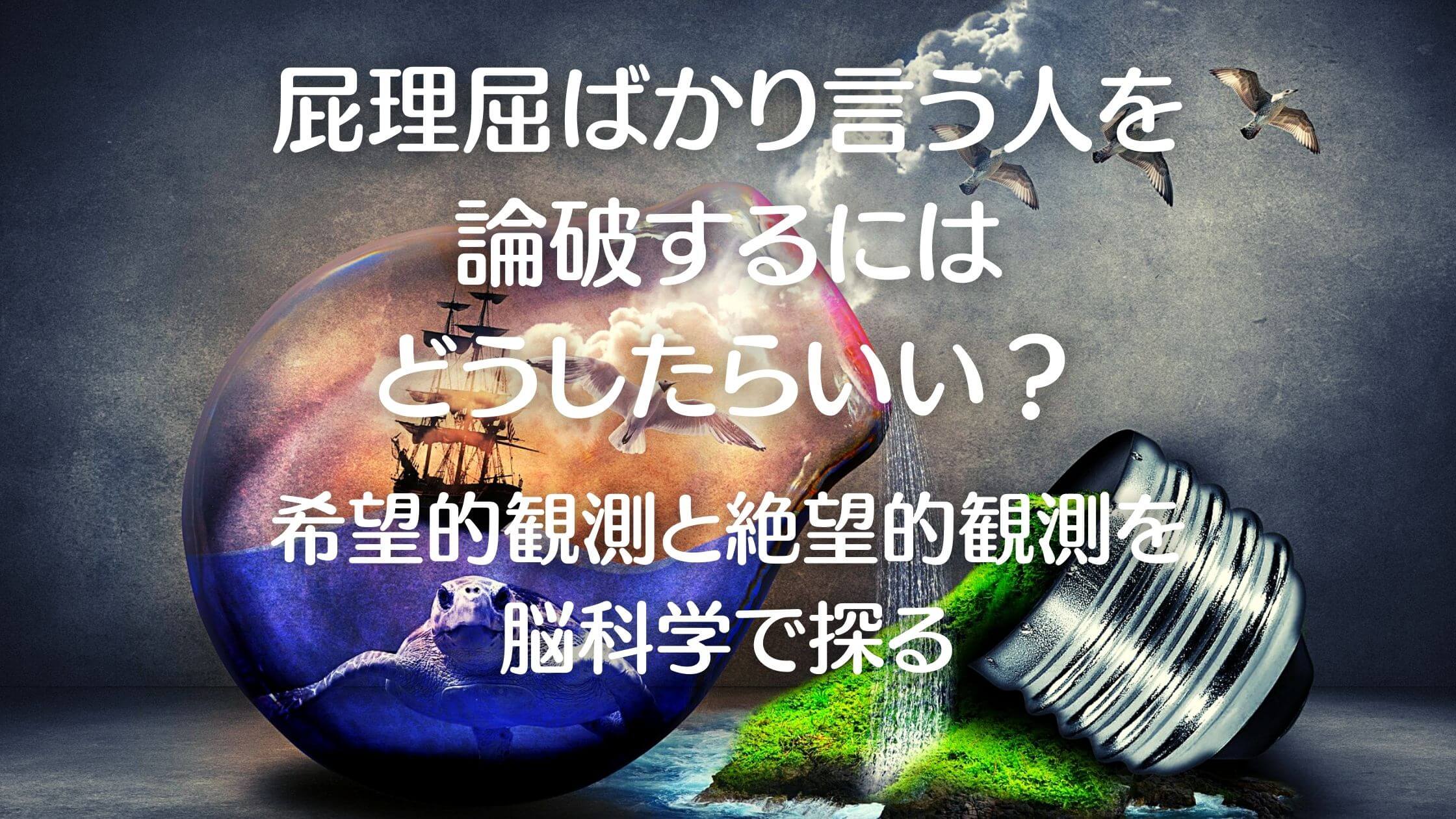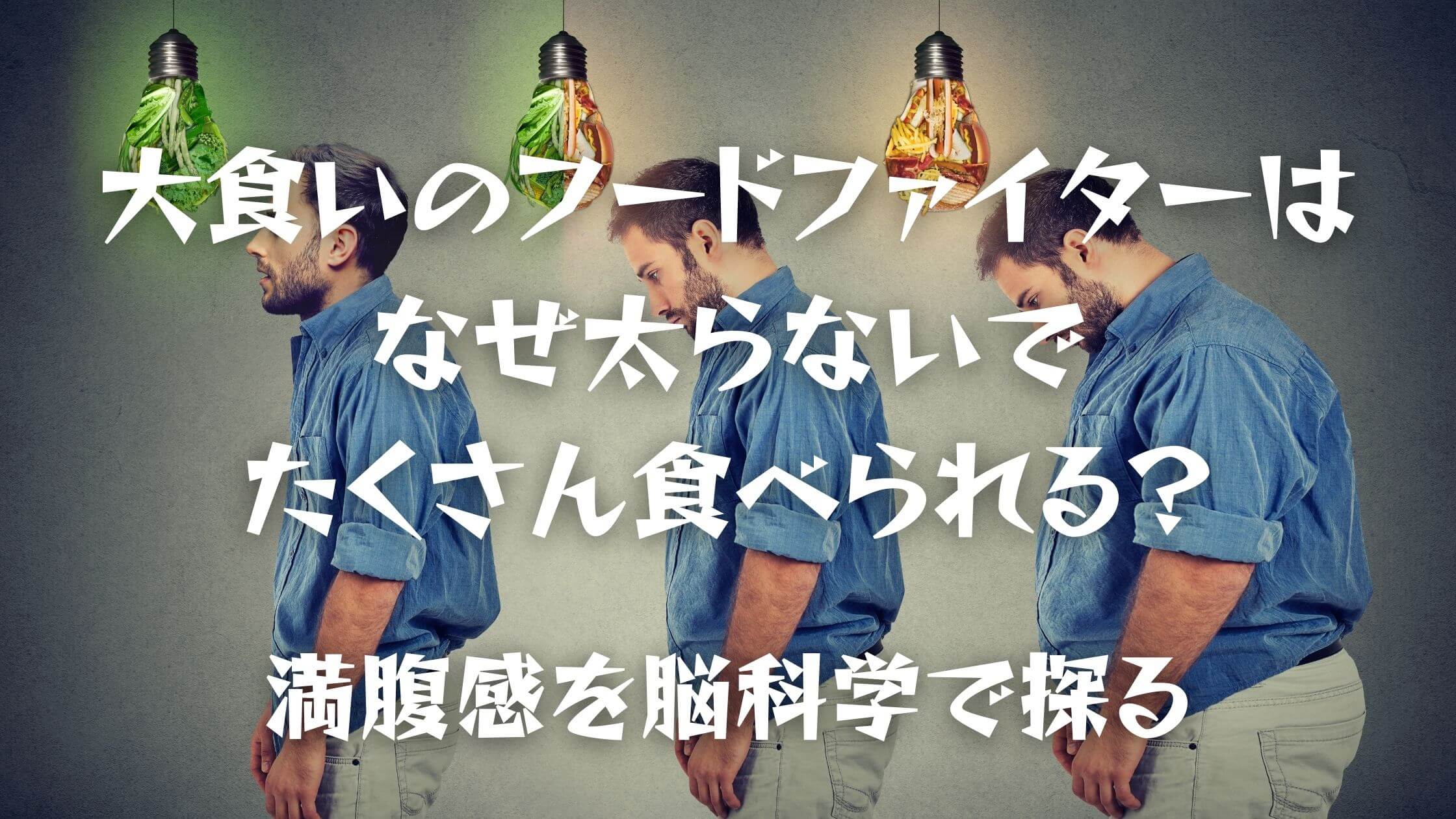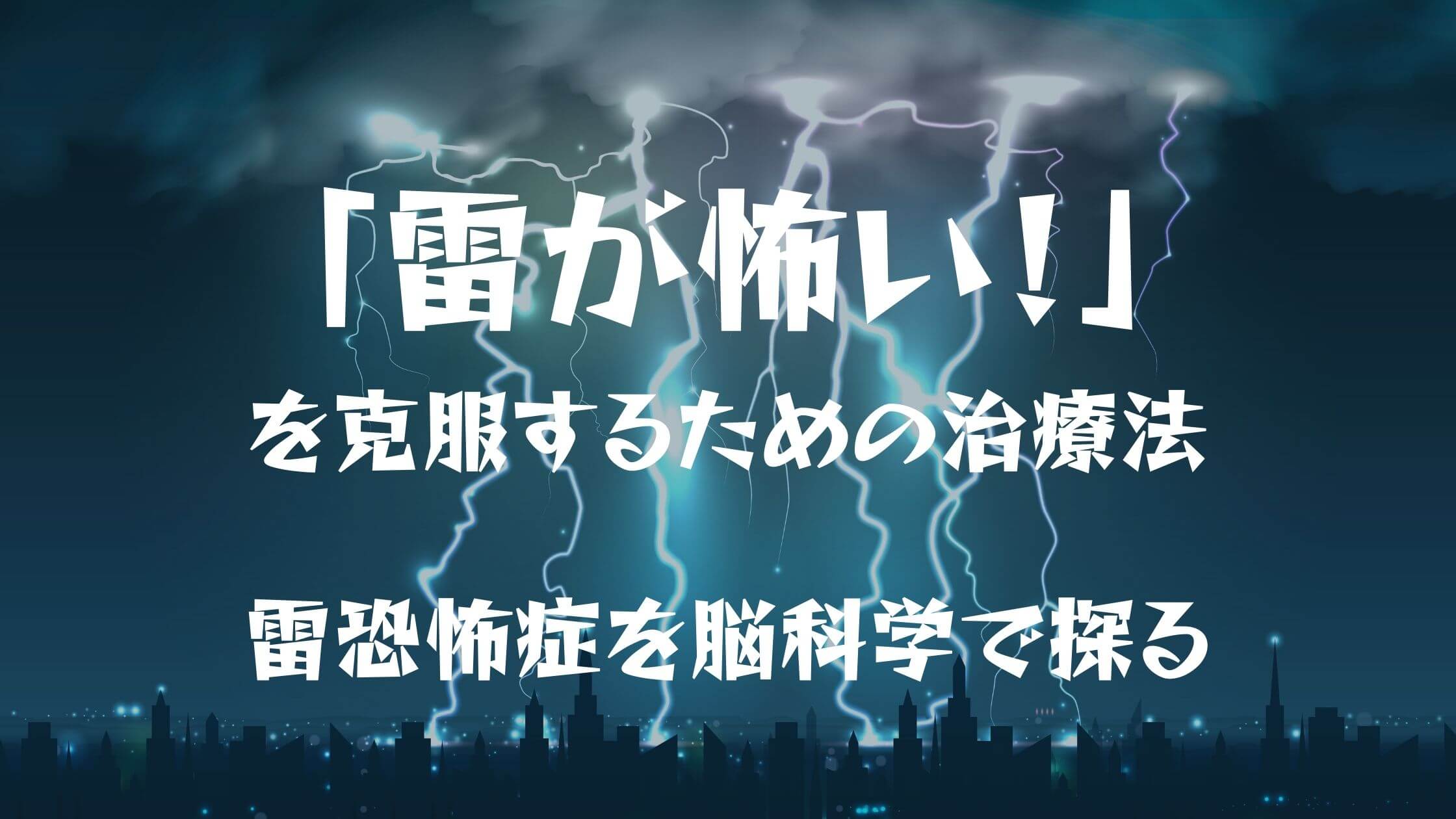独学ができない、続かない人のためのおすすめの勉強法ってありますか?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年…多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきますね。
この記事を読んでわかることはコレ!
- 独学の意味を脳科学で説き明かします。
独学のススメ
独学の脳科学
- 二宮金次郎の生涯はまさに独学の世界そのものです。
- 自分のできる限界を知ってその中で自分を磨き上げることが独学の基本です。
- 自分の感覚を研ぎ澄まして独学で得た知識は身に沁み込んで忘れないものです。
- 進化する文明社会の中にあって独学はある意味対峙する存在です。
- 人の真似をして自分のものとする、自分に嘘をつかず誠実に学ぶ、それこそが独学の真髄です。
多くの情報が簡単に手に入りやすくなった現代ではわざわざ高いお金を払って教えを乞うよりも独学で勉強することはそう難しいことではなくなりました。
しかし独学を始めてみたものの


このように独学に自信を持てずに勉強をしていたり途中で辞めてしまったり…なんて人は少なくないはずです。
“モチベーションの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
こちらもCHECK
-
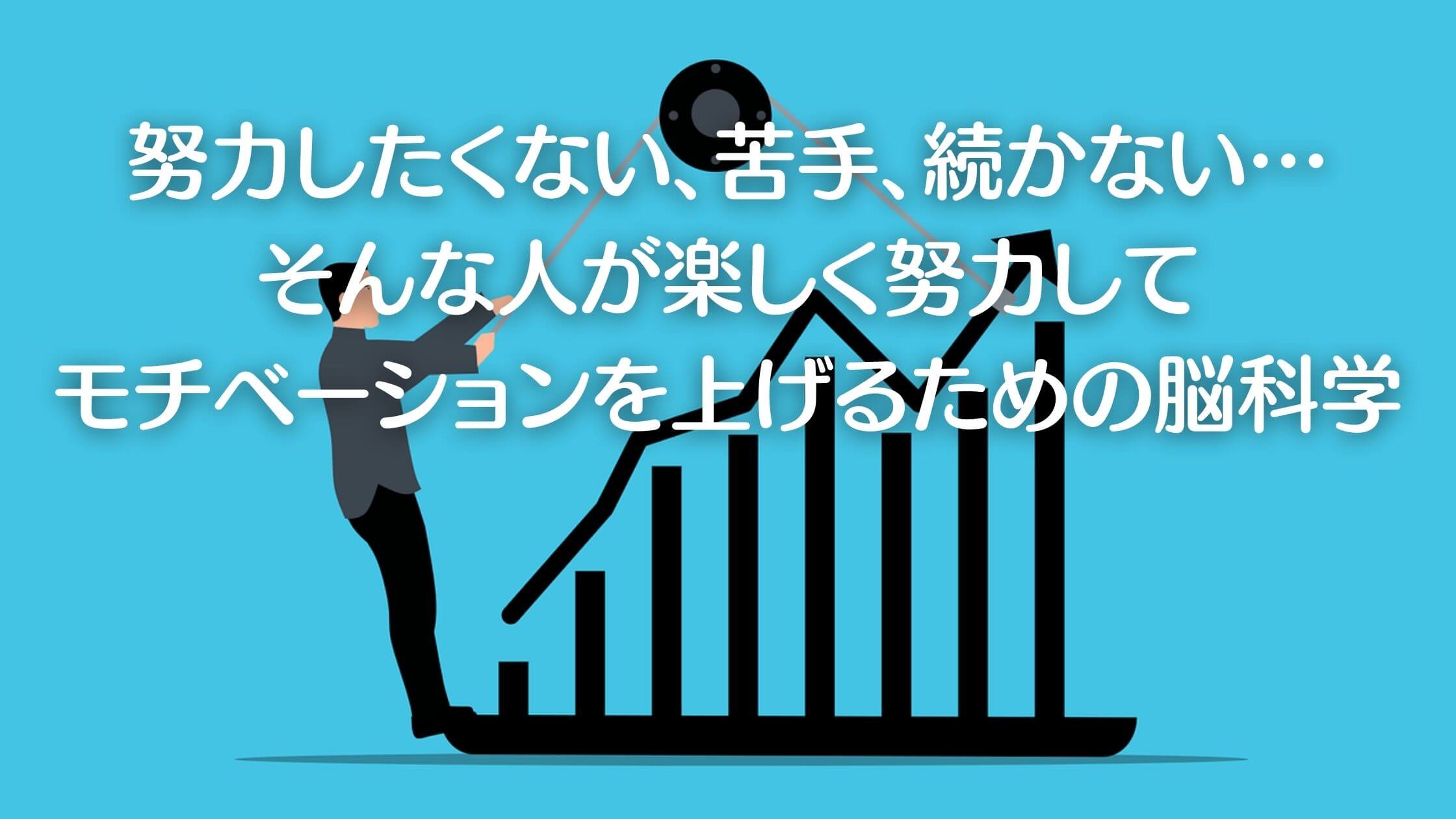
努力したくない、苦手、続かない…そんな人が楽しく努力してモチベーションを上げるための脳科学
努力したくない、苦手、続かない…そんな人でも努力できるようになりますか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20 ...
続きを見る
独学を効率的に進めるには受け身ではなく自主的に勉強をする必要があります。
「誰かに言われたから…」
「他の人がやっているから…」
そんな気持ちでは独学を続けることは難しいでしょう。

「独学」とは誰かに物事を教えてもらうのではなく自分の力で学問をして何かを得ることそして生み出すことです。
では独学するその心とはどのようなものなのでしょうか?
それを持つことによってどのような生き方が開けてくるのでしょうか?
それでは独学のおすすめの勉強法を脳科学で探っていきましょう。
二宮金次郎に学ぶ

学校でよく見かけるこの銅像は「二宮金次郎」で江戸時代の終わりころの農家の少年です。
勤勉で勉強熱心なこの少年こそ独学の象徴です。
二宮金次郎という名を聞いたことはあってもよく知らない…という人がほとんどではないでしょうか?
二宮金次郎には独学のおすすめの勉強法のヒントが散りばめられています。
そもそも彼が読んでいる本は何の本なのでしょう?
それは「大学」という中国の儒学の本です。
農家の少年がなぜそのような難しそうで堅苦しそうな本を読んでいるのでしょうか?
そもそもなぜ彼は全国の学校に銅像として立っているのでしょうか?
彼が銅像として全国の学校で見かけるのはおそらく
「学校に行って勉強できるのはありがたいことなのだから感謝して励みなさい。」
そんな思いがあったのでしょう。
金次郎は幼いころに両親を亡くし叔父の家に預けられました。
その叔父は良くある話ですがとても酷薄な人で金次郎につらく当たりました。
叔父にとって金次郎はタダで働かせられる労働者でしかなかったのです。
しかし金次郎の志はとても高く
「ただ訳も分からず働かされるだけの学問のない人間にはなりたくない」
と常々思っていました。
「大学」という本を手に入れると金次郎はそれを繰り返し読み返しました。
そんな金次郎に対して叔父は容赦ない言葉を浴びせます。
「本を読むための灯油などない。読書なんて役に立たないことはやめろ。」
しかしここでめげないのが金次郎のすごいところです。
めげるどころか反抗することさえもしません。
「ではどうすれば勉強を続けられるのだろうか?」
金次郎は空き地に油のもととなるアブラナを植えて仕事の合間に育て始めます。
1年後にはたくさんの菜種を収穫しそれを油屋に持っていき灯油と交換しました。
「これでまた勉強ができる。」
金次郎は喜びましたが叔父は喜ぶはずもありません。
「本なんて読むヒマがあるのならば夜は別の仕事をして働け!」
しかし金次郎は叔父を恨んだり自分の不幸を悩んだりはしません。
金次郎は人が見向きもしないような泥沼や山の斜面といった場所に目をつけそこに毎晩通っては少しずつ米を栽培し始めます。
1年後にはたくさんの米を収穫しそれをお金に換えました。
自分の力で米を作りその米を食べて一部をお金に換える。
金次郎は米俵を背負って叔父の家を出て独立して生活を始めます。
独立すると今まで以上に働き勉学に勤しみます。
誰も耕さなかった山の斜面や川岸を農地に変えみるみる豊かな農民になっていきます。
そうなると噂はあっという間に広まります。
領地の殿様から農地の再生の依頼が舞い込んできます。
仕事を引き受けた金次郎はひたすら農作業をします。
粗末な着物を着て徹底した粗食で睡眠時間は2時間ほど。
そんな金次郎を見て周りの農民たちも遊んでいるわけにはいかなくなります。
「自分たちも働くしかない…」
しかしそうやって働き出して成果が出ると働く喜びが湧いてくる。
金次郎のやり方に説教は不要でした。
共鳴を起こす行動力さえあればよかったのです。
一種の精神的な伝染が起こると農民たちの暮らしは見違えるように豊かになります。
彼は後の世では農政家と呼ばれましたがそんな器に納まりきらない偉大な人物です。
これが二宮金次郎という独学の象徴とされる人物です。

きっと金次郎のような生き方はできないと思うでしょう。
金次郎と同じ生き方をする必要はありません。
しかし金次郎から学ぶべきことは山のようにあるはずです。
自分の限界を知ってこそ独学がある

そもそも「独学」とは何なのでしょう?
学校に行かず家庭教師もつけず家にこもって1人で勉強をすることでしょうか?
決して1人で学ぶことだけが独学ではないはずです。
私たちは身体なしにして何か行動をすることはできません。
心も同じです。
私たちの心は身体のようにひとつきりであり当然限界があります。
ですから限界を超えて何かを考えるということはできません。
たとえば人の10倍働くという人がいたとします。
たとえば1日10冊の本を読むという人がいたとします。
しかしそんなことは身体も心もひとつしかない人間にできるはずがありません。

身体にも心にも限界があることは大切なこと、なくてはならないことです。
限界を超えて何かを成し遂げるなんてありえないことなのです。
超えることのできる限界なんてそもそも限界ではありません。
「独学する」ということはこの限界の中にあってしっかりと自分をとらえて生きる覚悟をするということです。
そんな気持ちで学ぶことは必ず独学になりますし独学にならざるを得ないはずです。
自分の限界すれすれまで自分を振り絞って学ぶことこそが独学なのです。

人から与えられてばかりでは自分の限界を知ることはできません。
独学する心を持った人はどこにいても何をしていても強い心を持っています。
愚痴を言ったり恨んだり不満を嘆いたりはしません。
金次郎の生きざまを見ればよく分かることです。
独学でしか学べないものがある

そんなことは今の時代許されないかもしれません。

“ハラスメントの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
こちらもCHECK
-
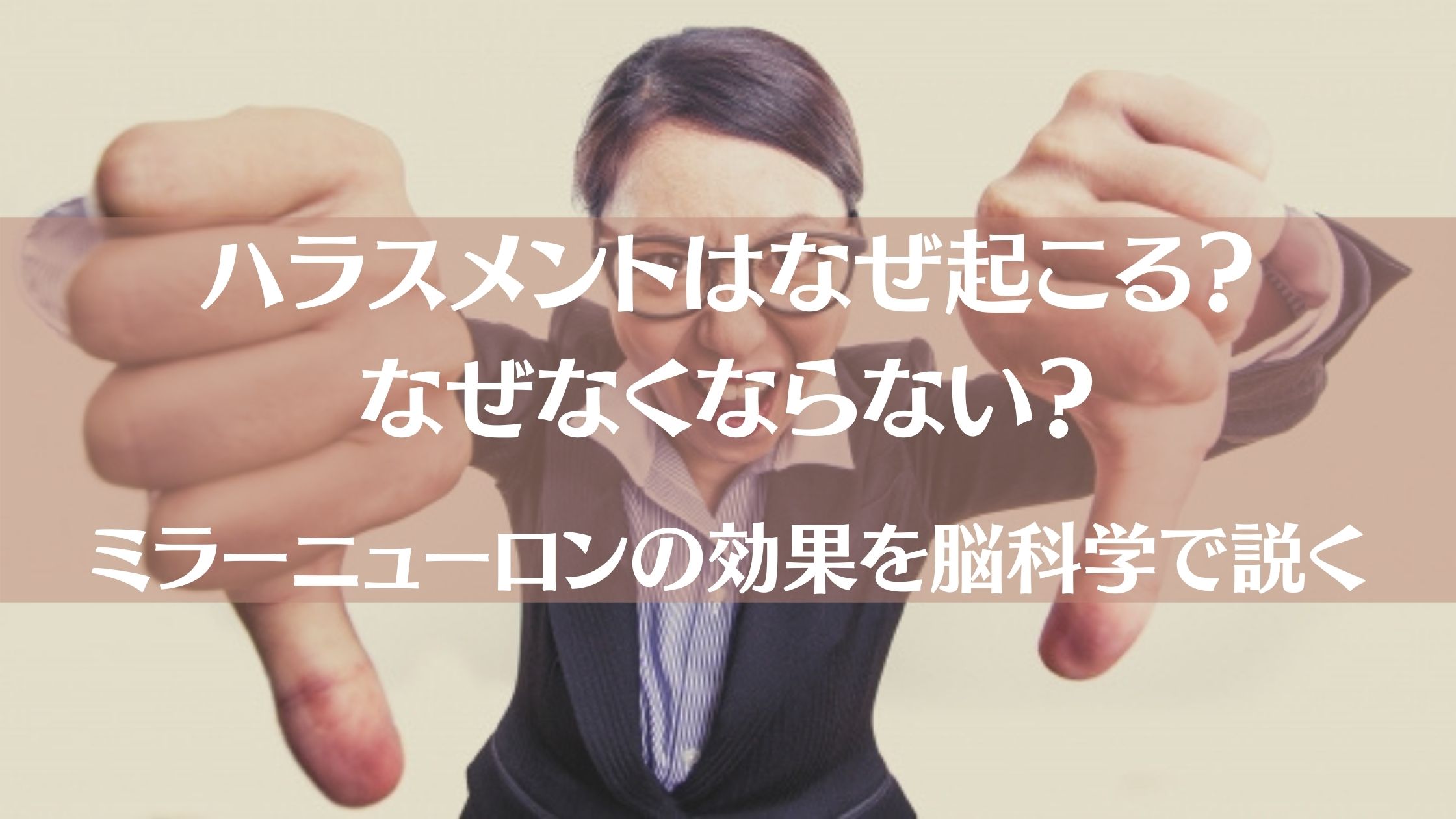
ハラスメントはなぜ起こる?なぜなくならない?ミラーニューロンの効果を脳科学で説く
ハラスメントはなぜ起こるのですか?なぜなくならないのですか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの ...
続きを見る
人から教わることで学ぶことができるものはたくさんあります。
しかし人から教わってもなかなか身につかないしできるようにならないものもたくさんあります。
そもそも言葉で教えられたものは忘れがちです。
それはあくまでもただの知識だからです。
自分の身を削って発見したものは早々忘れることはありません。
そういうものは知識ではなく身についた自分の技なのです。
“知識の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
こちらもCHECK
-
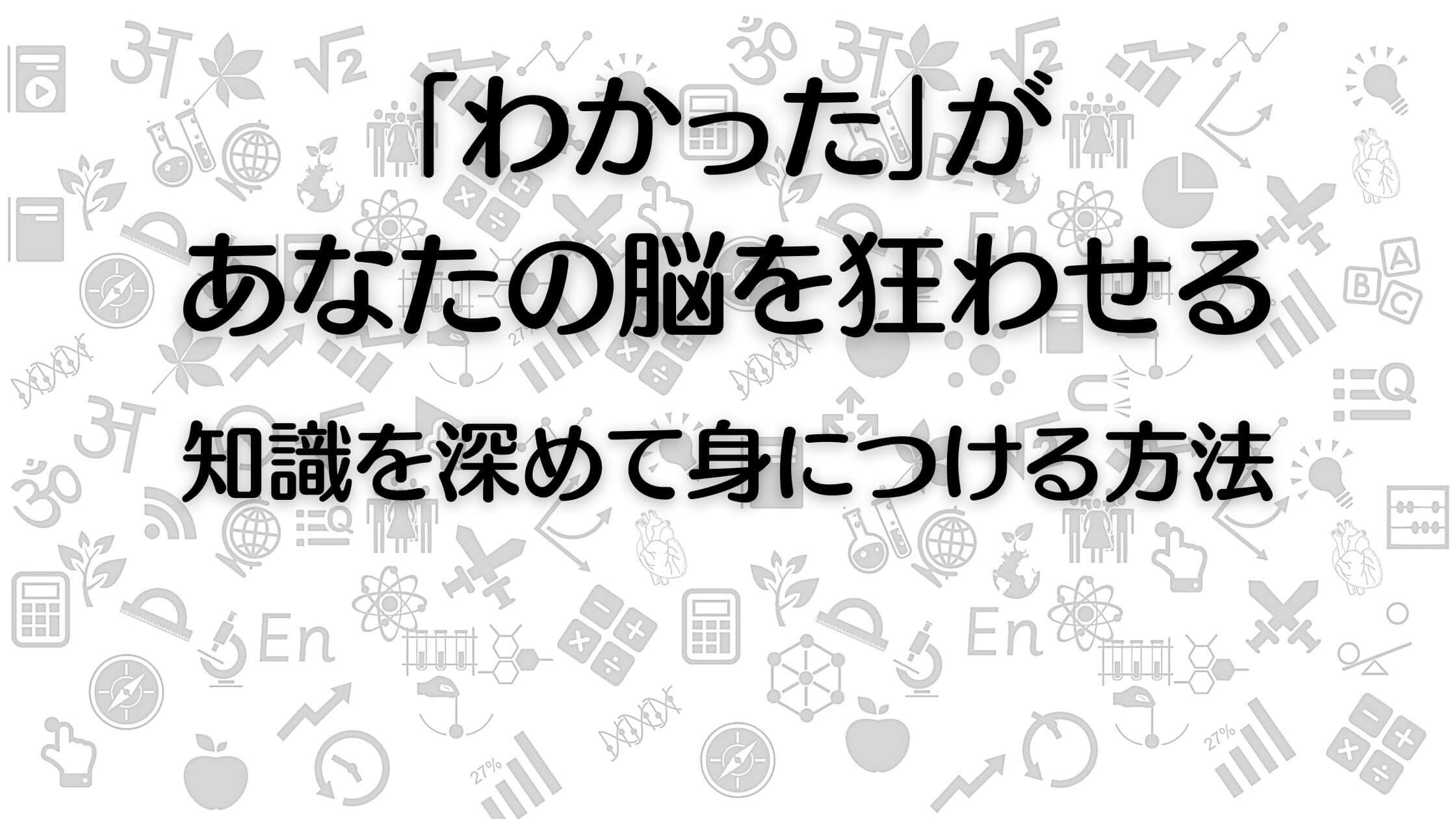
知識を深めて身につける方法~「わかった」があなたの脳を狂わせる
知識を深めて身につけるにはどうしたらいいの? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合 ...
続きを見る
こちらもCHECK
-
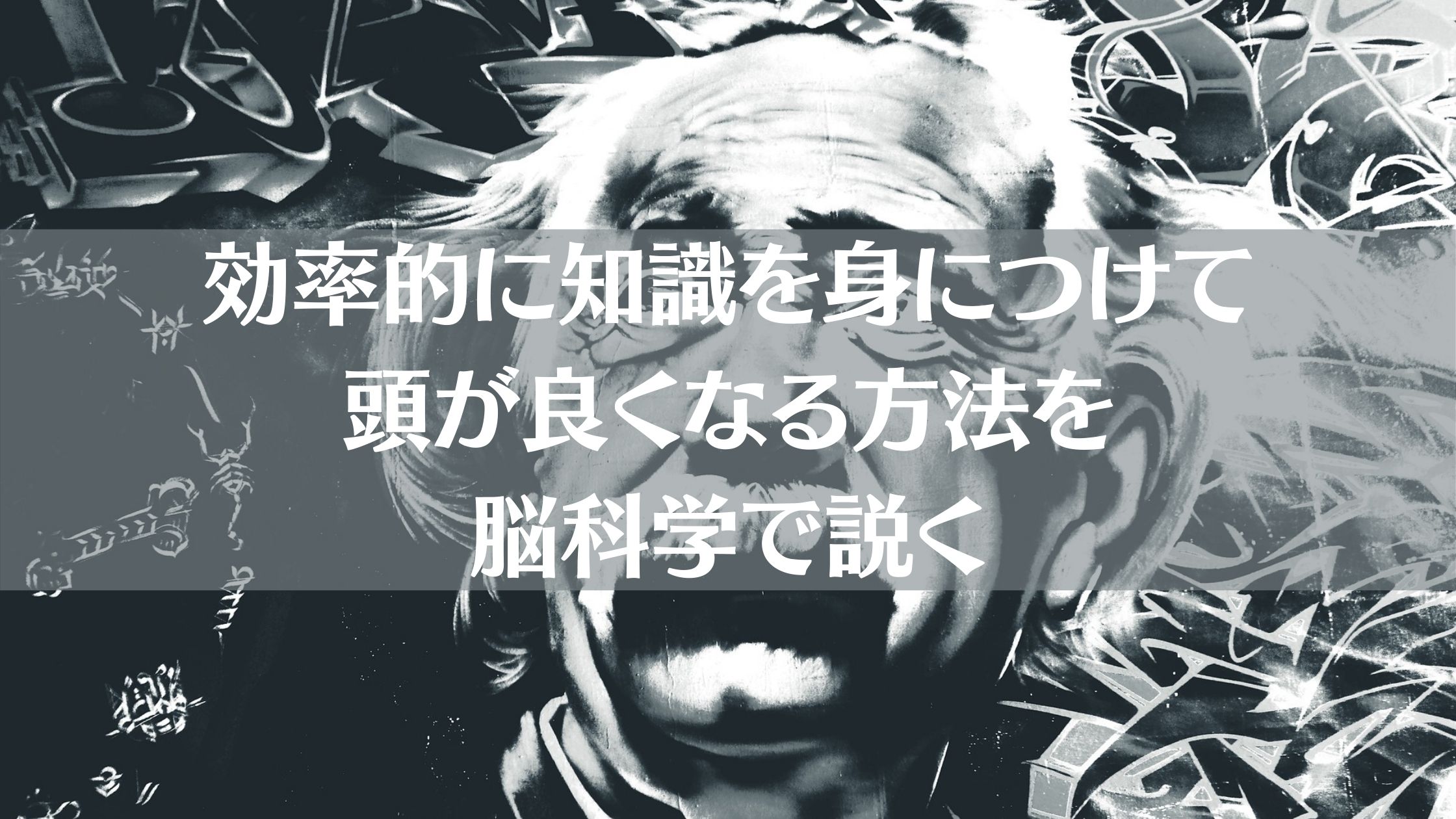
効率的に知識を身につけて頭が良くなる方法を脳科学で説く
効率的に知識を身につけて頭が良くなる方法って何かありますか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年…多くの脳 ...
続きを見る
人間の身体も心も1人ひとり全然違います。

ですからある程度の知識を教わることはあっても最終的には自分の力で身につける必要があります。
自分なりにあれこれと取り組んでみて理解する以外に方法はありません。
自分に合ったスタイルを見つけ出した時ほど強いものはないはずです。
しかし現代社会は独学で学ぶことが難しくなっています。
個性を打ち出すよりも大勢の中に馴染んで誰がやっても同じようにうまくいくことが求められています。
便利さに慣れきって身ひとつの「勘」でしか解決できない技は失われつつあります。

しかし独学でしか学べない自分だけの感覚は決してなくしてはいけないものなのではないでしょうか。
文明社会と対峙する独学の世界

「天」は言うならば神にあたります。
もっと深い意味では自然も天にあたるでしょう。
身ひとつで独学する心は自ずと「天」に通じています。
「天」が助けてくれなければ独学は実を結びません。
金次郎はこのことを「水車」に例えて語っています。
水車は水の流れに沿って回っています。
水車がうまく回るのは半分は水が落ちる力によるものです。
しかしあと半分は水を押し上げて上がってくる水車の働きによるものです。
まさに人が自然の助力を得て成し遂げる技こそが水車なのです。
文明社会は自分の都合に合わせて自然を利用してきました。
そしてあらゆるものを数字の関係に置き換えて有効に物に働きかけることで進化してきました。
たとえば建築においてはすでに工場で数学的に計算されつくした部品を組み立てるだけです。
それは確かに正確な作業ではありますが天に対する愛情や敬意は失われています。
しかし昔ながらの大工は生きた木と相談ずくしで仕事をしていきます。
木の命に入り込み木に協力してもらい建築は成り立っています。
対象への愛情がないところに建築は成り立たちません。
ですから一流の建築士と昔ながらの職人の大工では当然意見に食い違いが起こります。

先ほども述べましたが物事には限界が必ずあります。
できることとできないことが必ずあります。
たとえば水のないプールで泳ぐことはできません。
しかし文明社会ではそうは考えません。


多くの人がもしかしたらそう思っているかもしれません。
しかしこれでは人間として大事なことが何もわからなくなってしまいます。
できないこと、わからないことがあることは学問の可能性を高めるにはとても大切なことです。
しかしわが身を離れた空想ばかりしていても現実的ではありません。

しっかりとした対象を持ちその対象の性質にうまくそして深く入り込んでこそ学問は成り立ちます。
身ひとつ心ひとつで入り込みその中できることを理解しその限界の中で苦労してことを成し遂げる。
これこそが独学の真髄なのではないでしょうか。
文明社会の中で目覚ましく進歩する科学技術の発達にばかり目を奪われて昔ながらのごく当たり前の独学の心を多くの人が失いつつあるのではないでしょうか。
独学に必要な2つのこと
教える側は専門的な知識をたくさん持っています。

しかしその多くの知識はすぐに古くなっていきます。
ですから私たちが教えてもらうのは専門的な知識ではなく物事の考え方です。

学ぶ側がいかにうまく盗み取れるかが大切であり教わっていてもある意味独学でもあります。
学問とは目標とする人が身ひとつで取り組み考える姿を見てそれを真似することから始まります。
“真似の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
こちらもCHECK
-
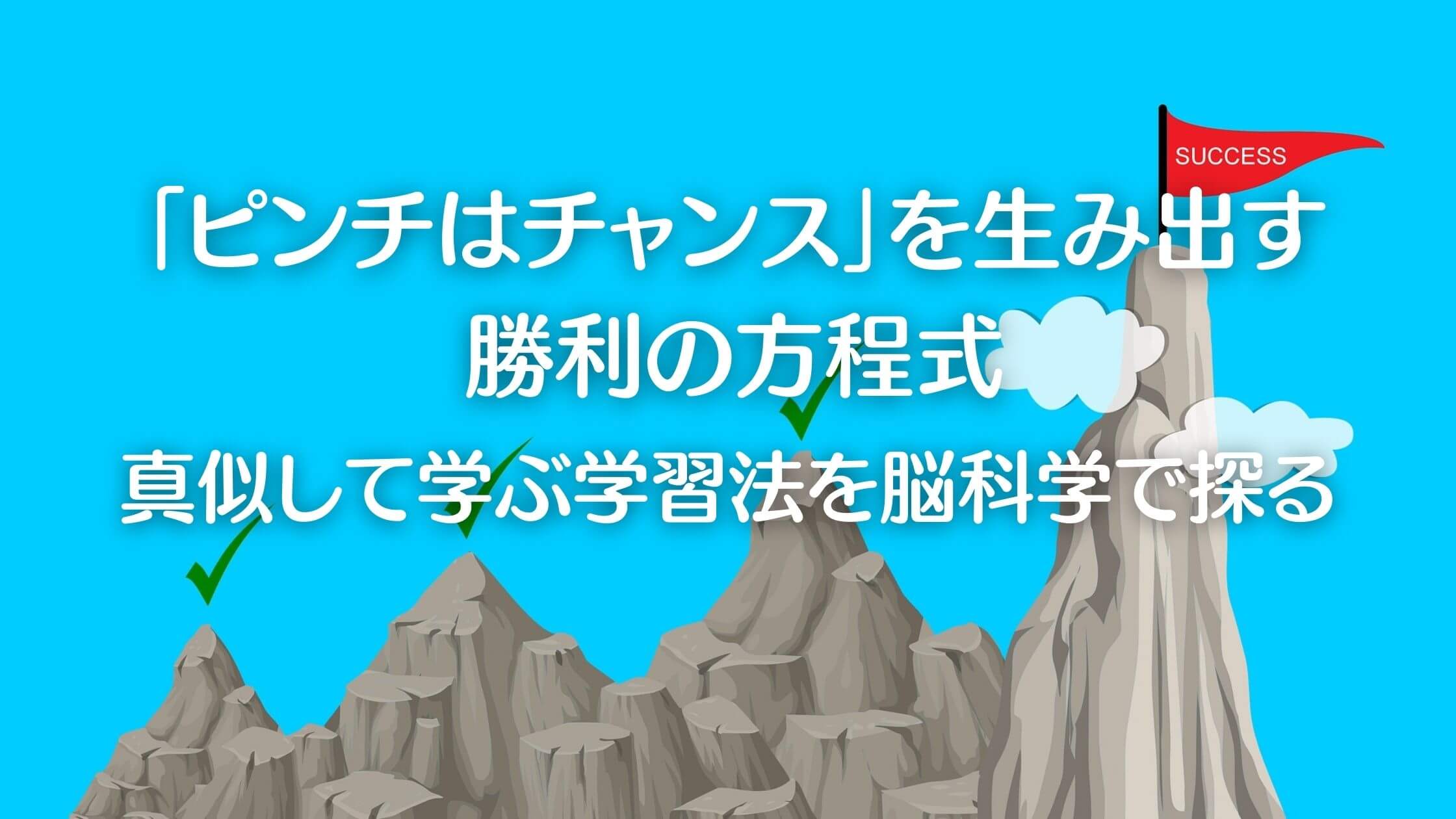
「ピンチはチャンス」を生み出す勝利の方程式~真似して学ぶ学習法を脳科学で探る
ピンチをチャンスに変えるにはどうしたらいいの? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き ...
続きを見る
真似して身につけた考え方はいずれ自分のものとなっていきます。
そしてそんな風にして身につけた考え方は決して古びたりしません。
なぜならその考え方を使うたびに深くなり活き活きとし自分を新しくしてくれるからです。

もう1つ独学に必要なことは自分を偽(いつわ)らず自分に嘘をつかないことです。
“嘘つきの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
こちらもCHECK
-
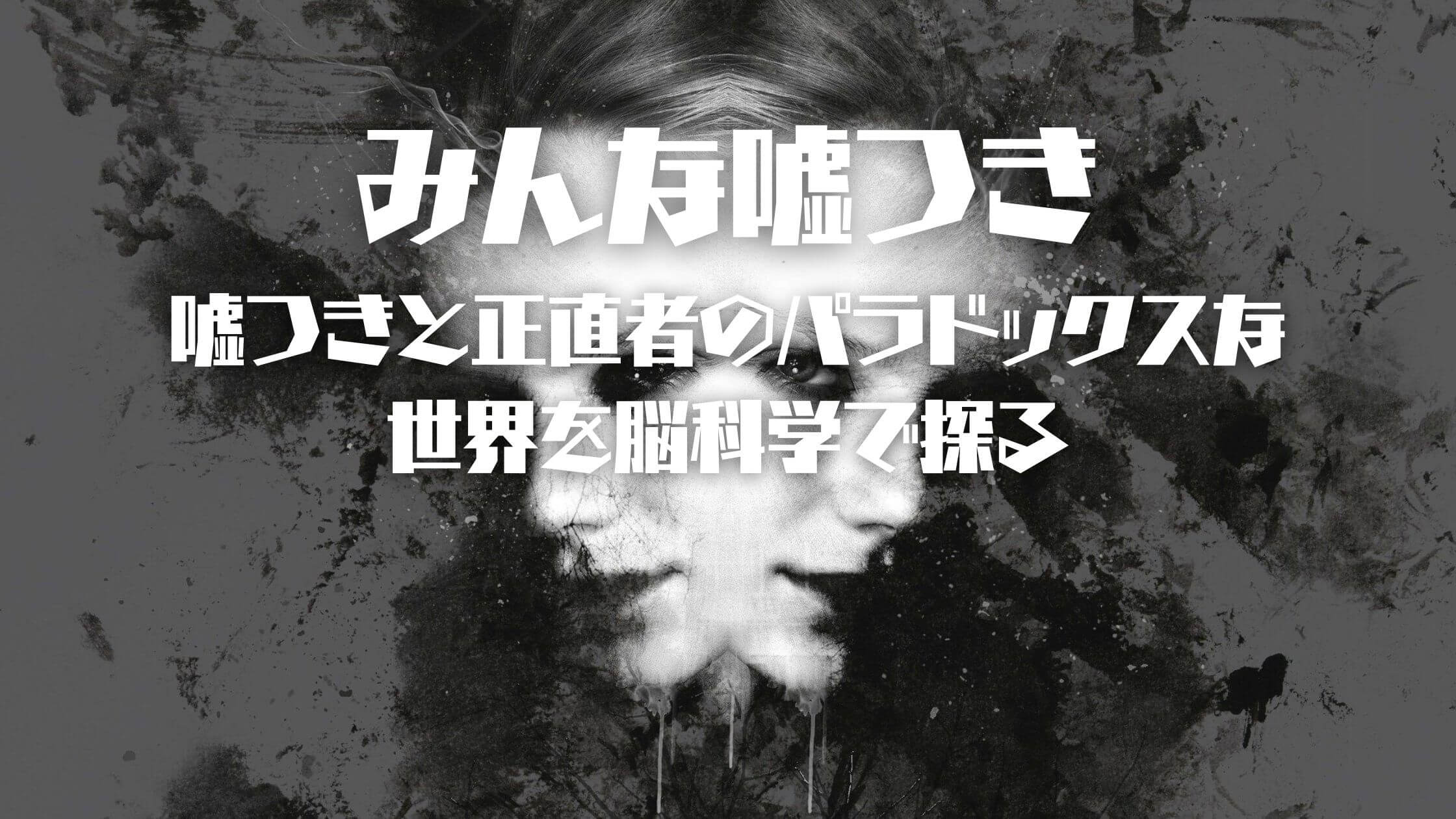
みんな嘘つき~嘘つきと正直者のパラドックスな世界を脳科学で探る
嘘つきと正直者ってどう違うの? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として ...
続きを見る
こちらもCHECK
-
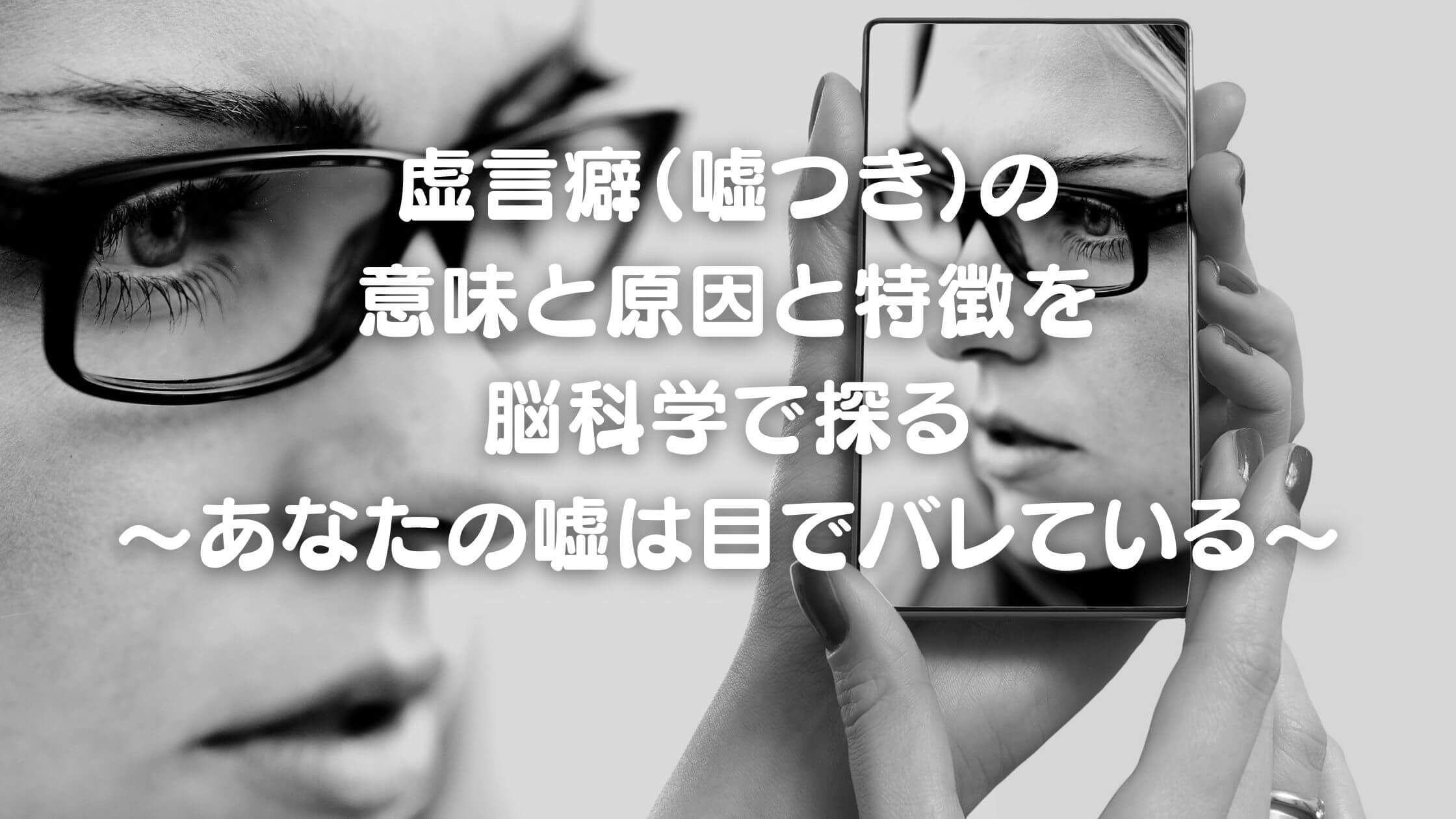
虚言癖(嘘つき)の意味と原因と特徴を脳科学で探る~あなたの嘘は目でバレている
虚言癖(嘘つき)は治らないの? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い中心に勤務医 ...
続きを見る
中国の書物で孔子の教えを記録した「論語」という本があります。
そこにはこんな話がのっています。
ある時弟子が孔子に問います。
「君子の持つべき心境とはどのようなものでしょうか?」
君子とは知恵のある正々堂々とした人のことです。
すると孔子はこう答えます。
「君子は憂(うれ)えず懼(おそ)れず」
弟子にとっては意外な答えでした。
「憂(うれ)う」とは思い悩んだり心配したりすること。
「懼(おそ)れる」とは恐れたり不安になったりすること。
つまり悩んだり心配したり恐れたり不安になったりしない人が立派な人…ということになります。
そう聞くとなんとものんきで平和な人だなあ…と思うかもしれません。
しかしその言葉の本質はそのようなことを言っているわけではありません。
「身に省(かえり)みて恥じることなくば、何をか憂(うれ)えん、何をか懼(おそ)れん」
つまり自分を振り返ってみて恥じることがなければ何も悩んだり心配したり恐れたり不安になったりする必要などないのです。
自分を恥じるのは自分の力を偽っているからです。
分かりもしないことを分かったように見せかけしたりするといろんなことが心配で怖くてたまらなくなります。
そして嘘をどんどん重ねていくことになります。
「身を省(かえり)みる」とは身ひとつの自分にいつも誠実に素直に帰ってみるということです。
自分に振り返って誇りを持てるような生き方を学ぶことこそが独学です。
ですから君子の学問はいつでも独学なのです。
なにも君子になれとは言いません。
しかし君子たる生き方をつねに目指していればあなたなりの独学の勉強法を見つけ出すことができるのではないでしょうか。
“独学の脳科学”のまとめ
独学ができない、続かない人のための独学の意味を脳科学で説き明かしてみました。
今回のまとめ
- 二宮金次郎の生涯はまさに独学の世界そのものです。
- 自分のできる限界を知ってその中で自分を磨き上げることが独学の基本です。
- 自分の感覚を研ぎ澄まして独学で得た知識は身に沁み込んで忘れないものです。
- 進化する文明社会の中にあって独学はある意味対峙する存在です。
- 人の真似をして自分のものとする、自分に嘘をつかず誠実に学ぶ、それこそが独学の真髄です。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわりのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
最後にポチっとよろしくお願いします。