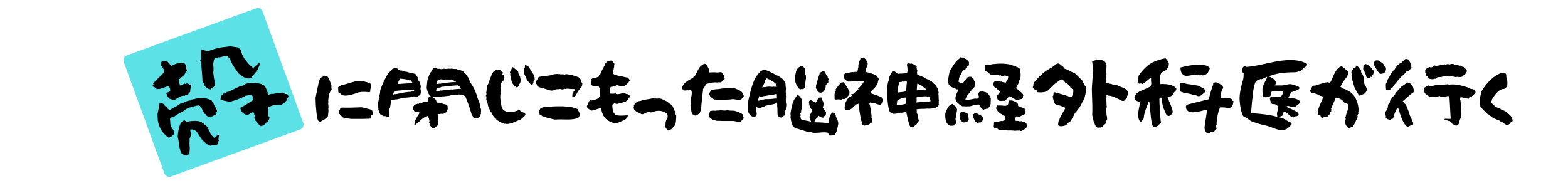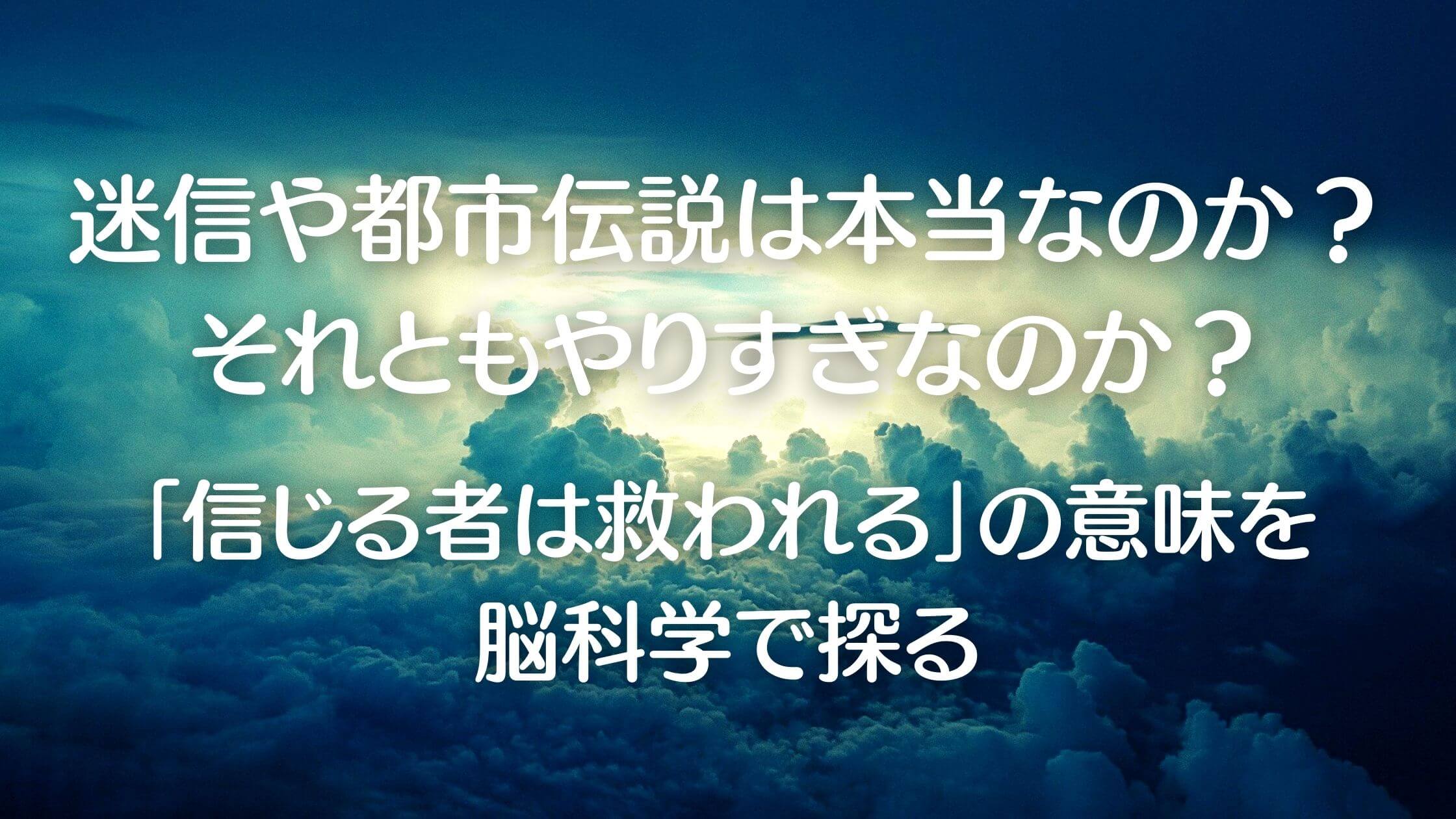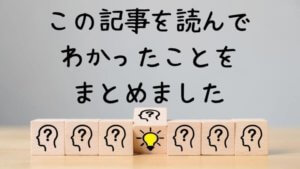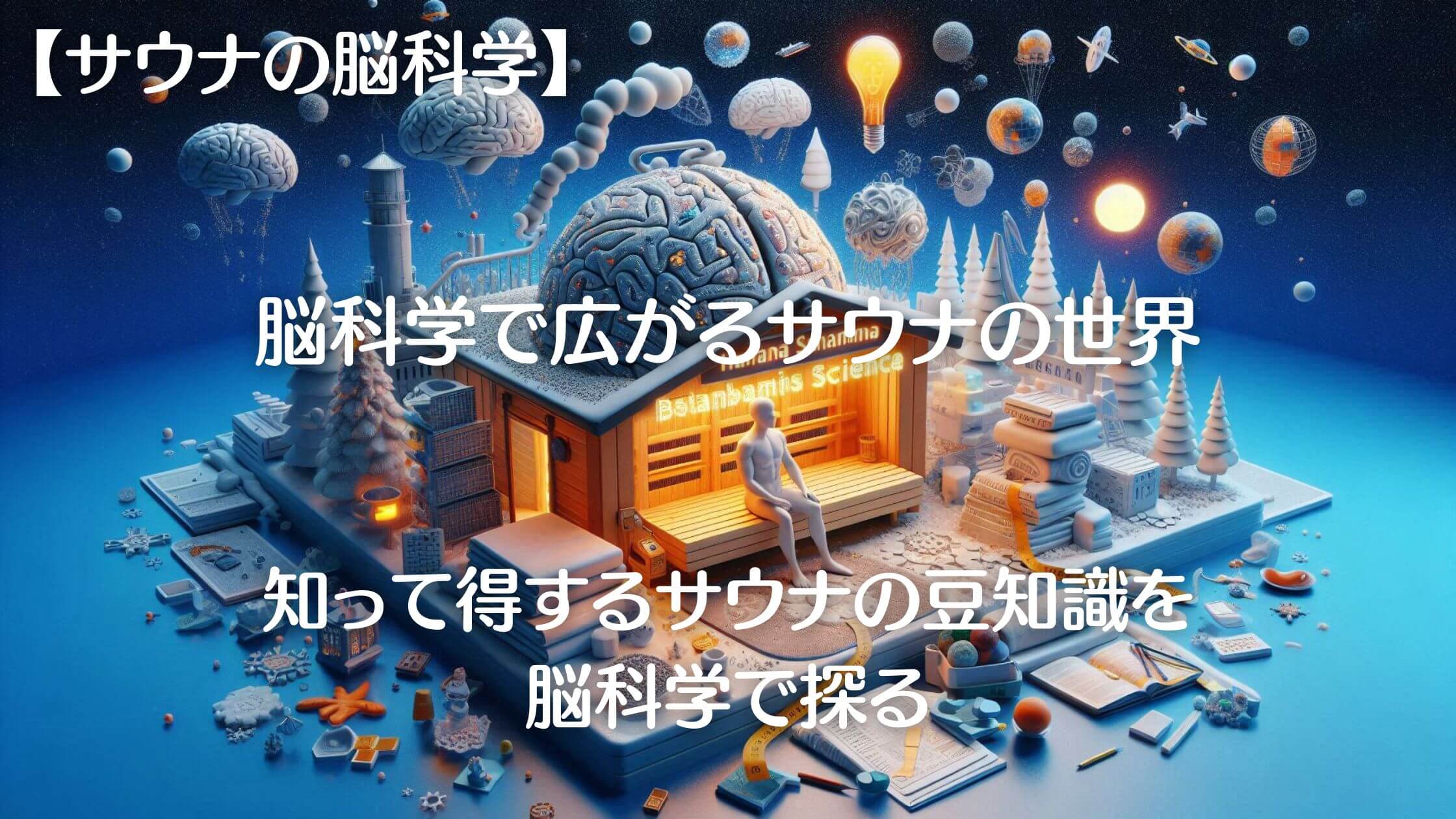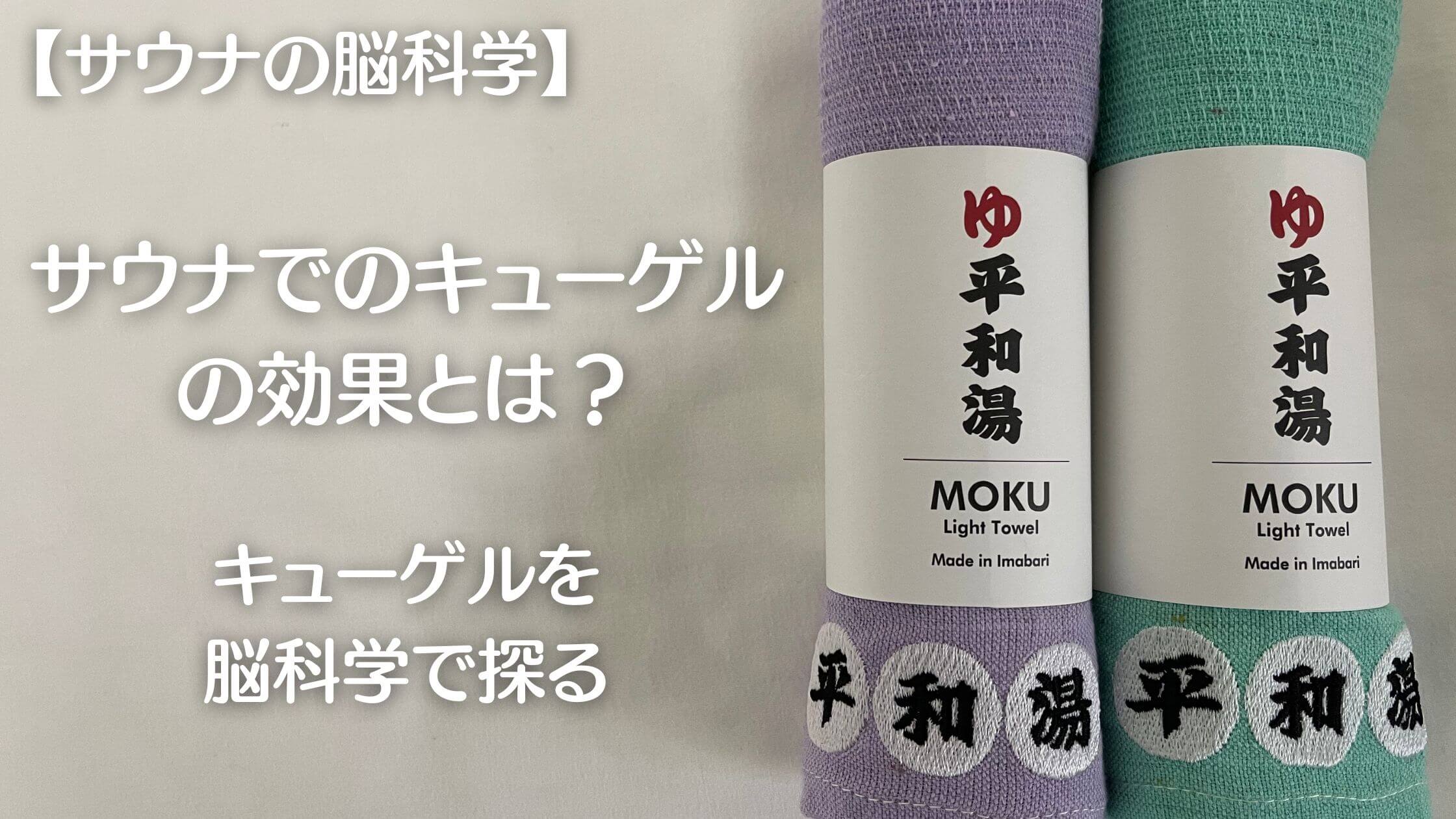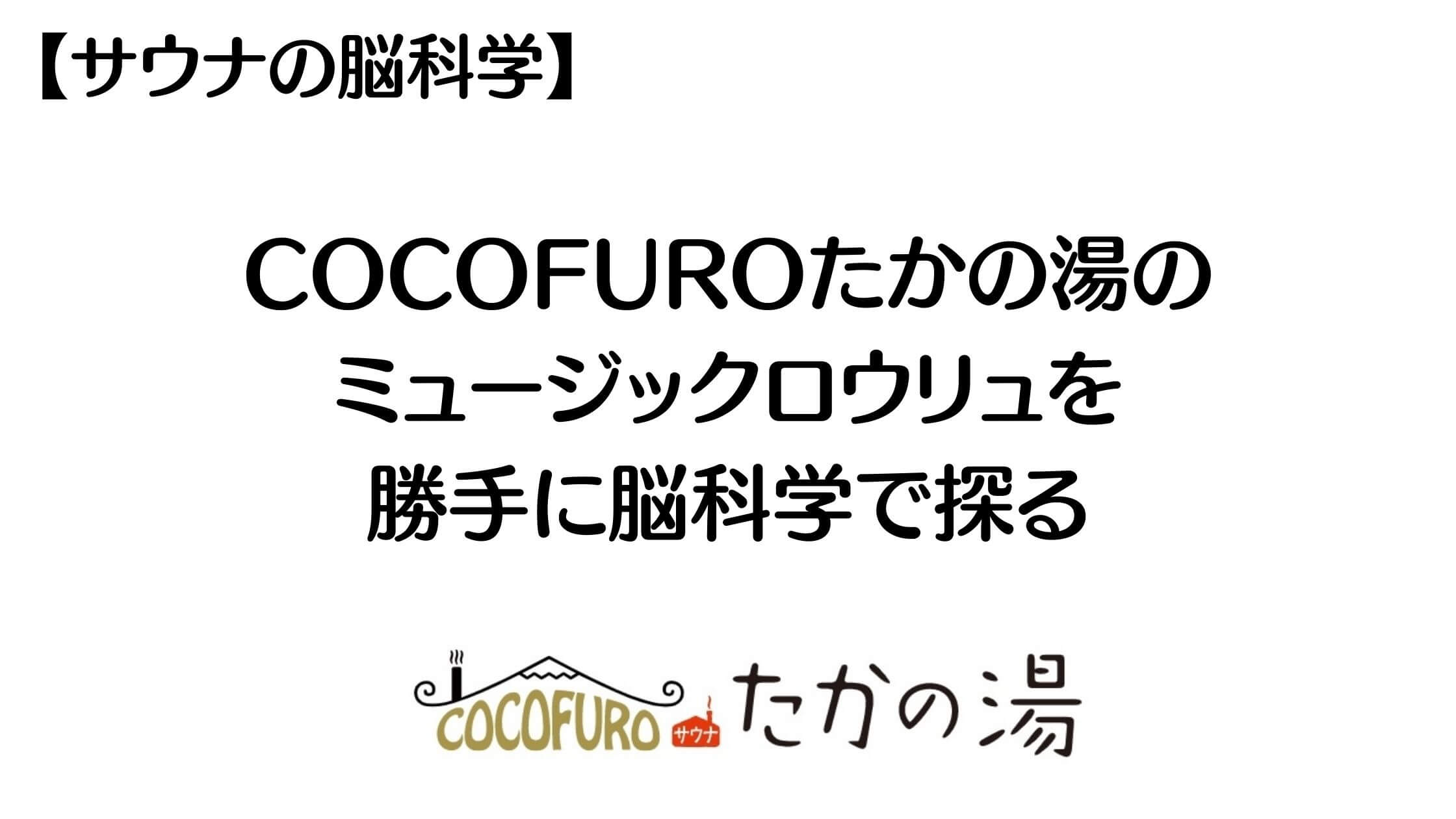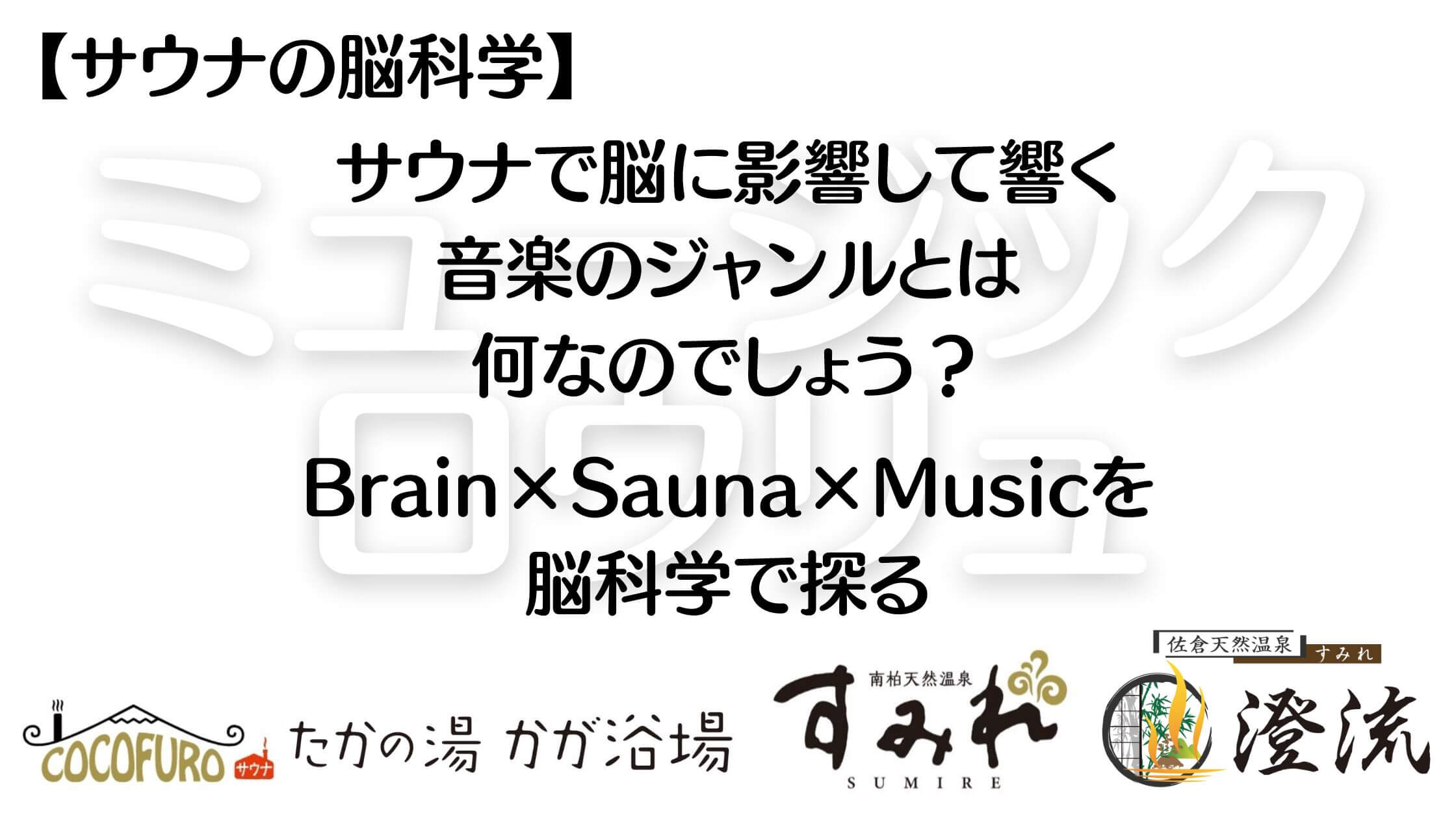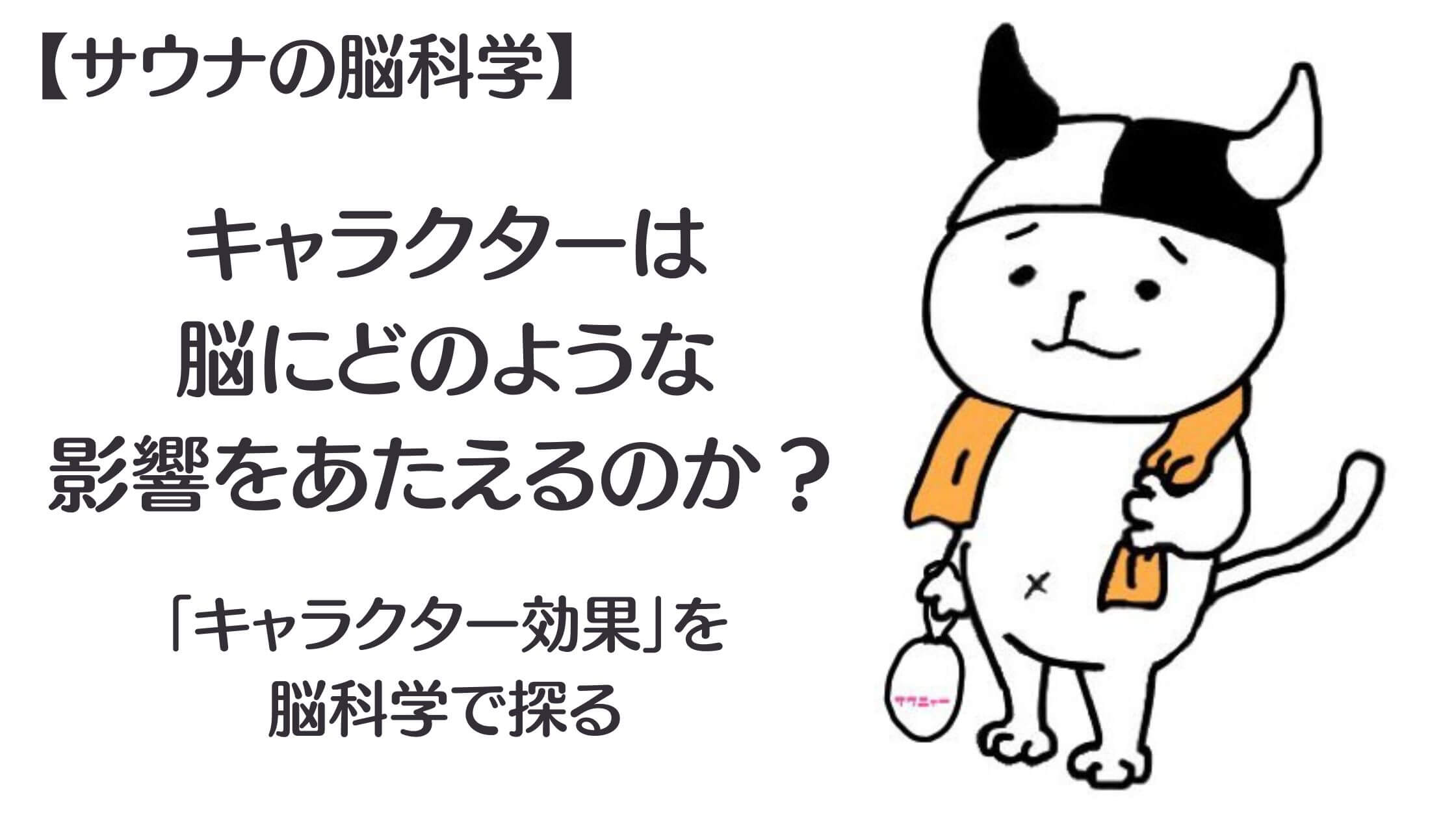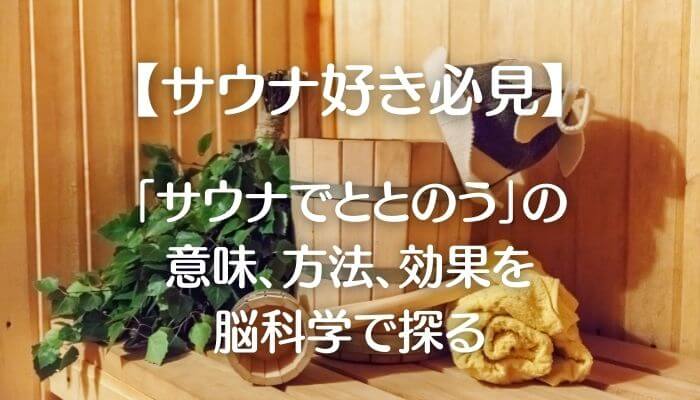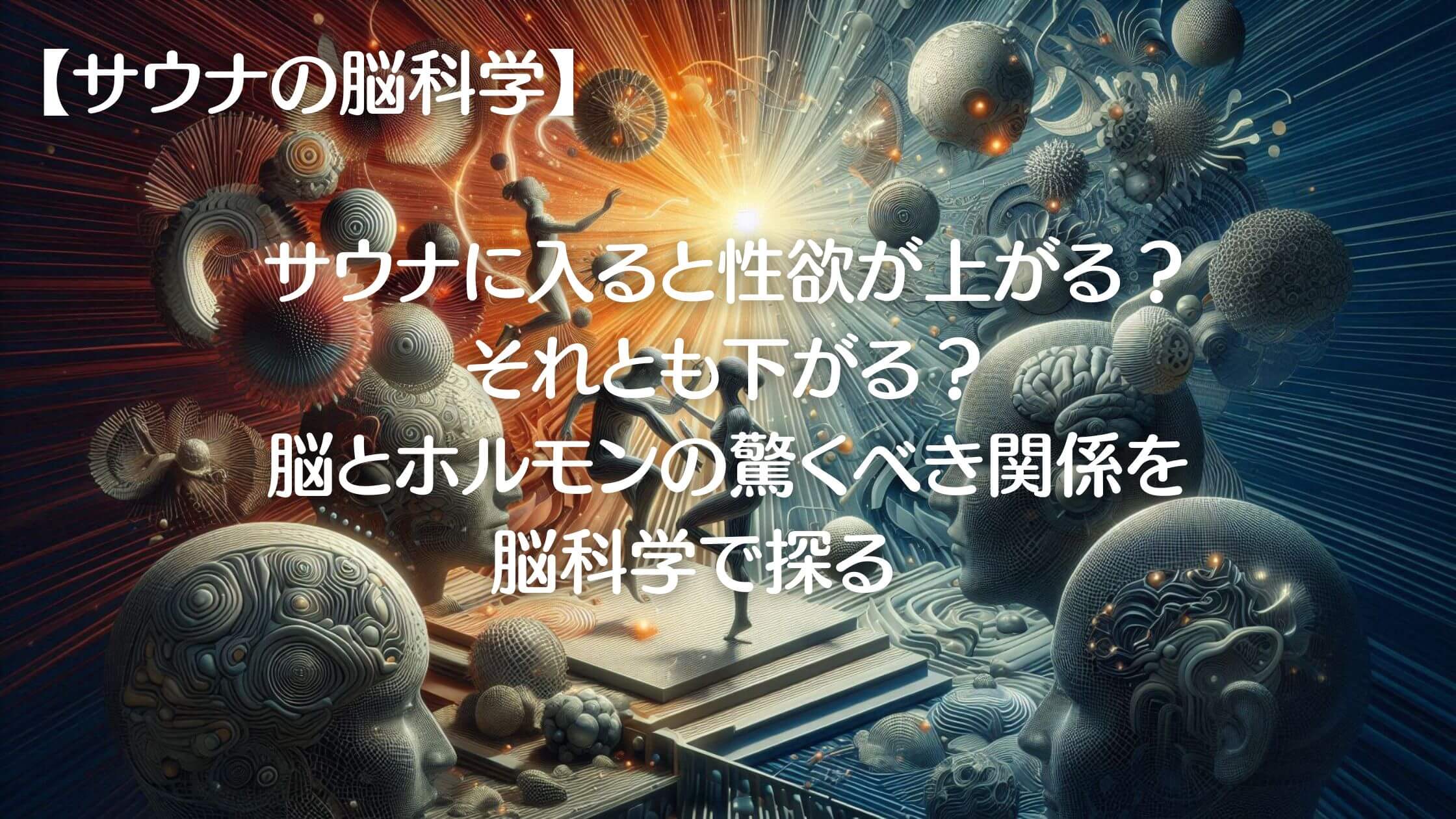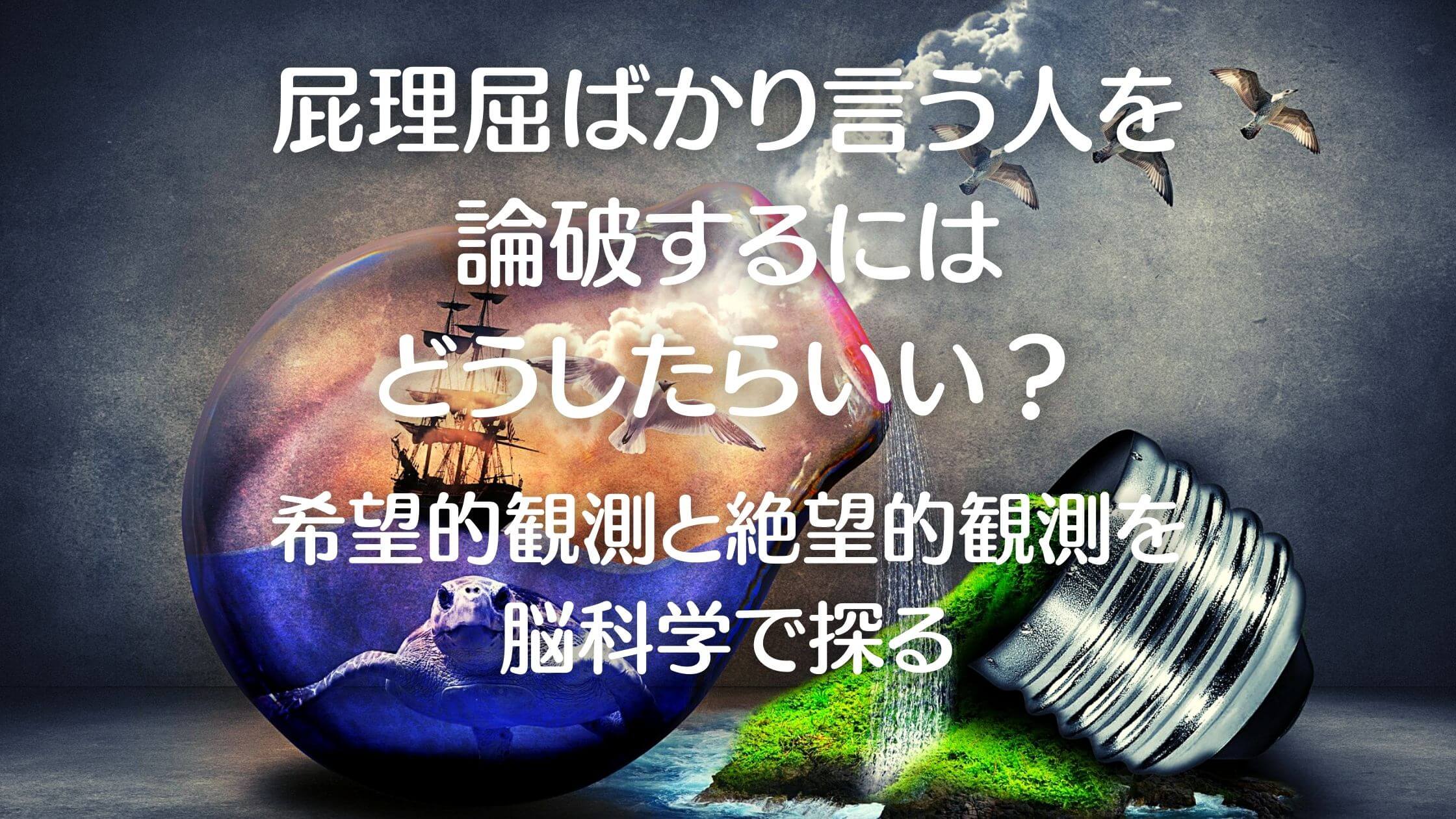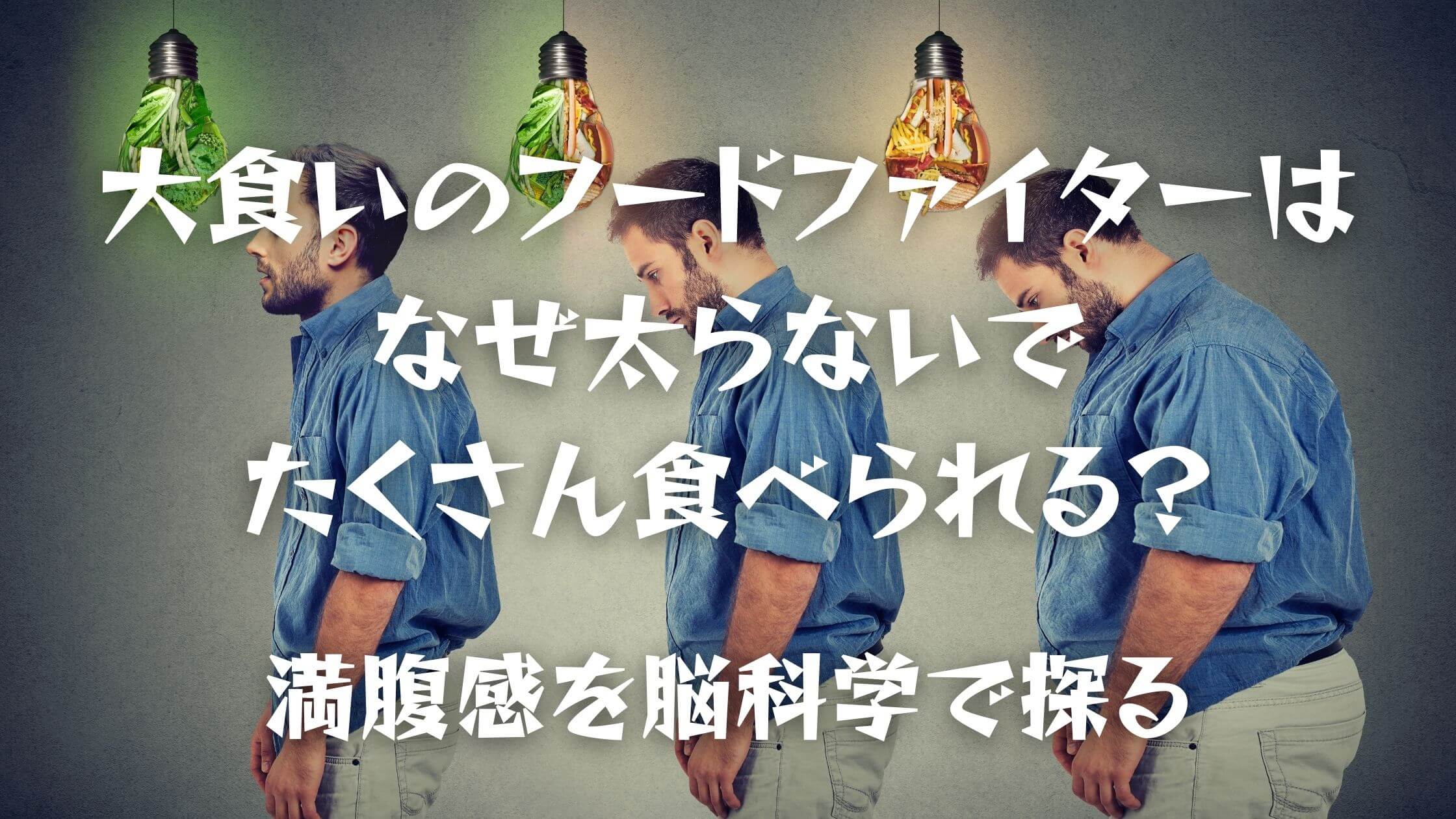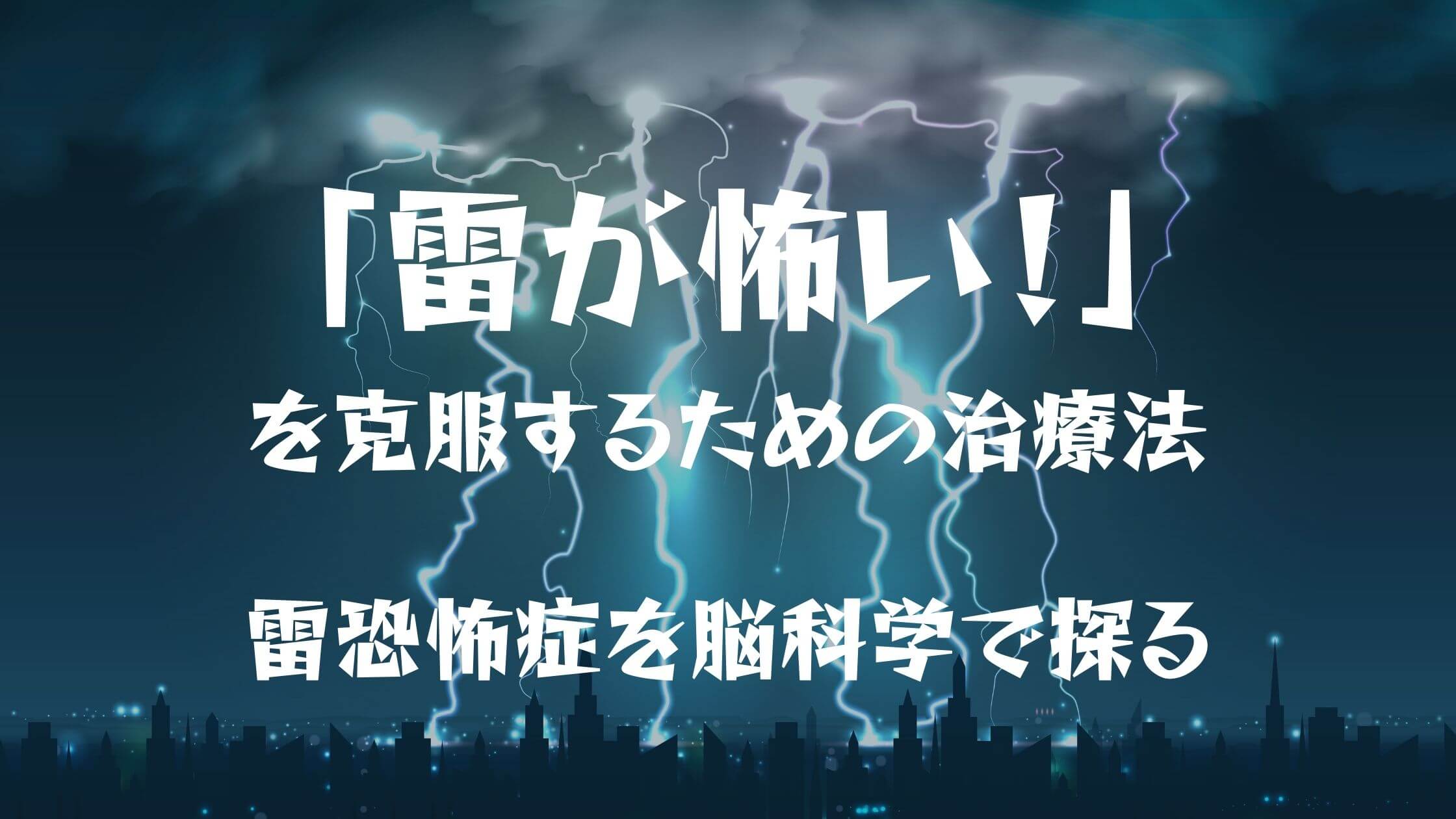迷信や都市伝説は本当なのでしょうか?
それともやりすぎなのでしょうか?
そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。
このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気と向き合い勤務医として働いてきた視点から、日常の様々なことを脳科学で解き明かし解説していきます。
基本的な知識についてはネット検索すれば数多く見つかると思いますので、ここでは自分の実際の経験をもとになるべく簡単な言葉で説明していきます。
この記事を読んでわかることはコレ!
- 「信じる者は救われる」の意味をわかりやすく脳科学で説き明かします。
信じる者は救われるのか?
「信じる者は救われる」の脳科学
- 「信じる者は救われる」はそもそもスピリチュアルの世界観から生まれた言葉です。
- 脳が科学的根拠のない迷信や都市伝説を信じてそこに「信じる者は救われる」を見出そうとする「迷信行動」を好みます。
- 直接的に関連がない2つの事象に因果関係を見出そうとする「疑似相関」も「信じる者は救われる」を導き出す脳の働きです。
- 「過去は未来に影響を与えない」ことをうまく理解できていないと誤謬(ごびゅう)を生み出しそこから「信じる者は救われる」が導き出されます。
- 結局「信じる者は救われる」の真意はあなたが何をどう信じているのかにかかっているのです。


「信じる者は救われる」の語源はイエスを神とする聖書からきていると言われています。
信じる対象はイエスでありイエスを自分の個人的な救い主として心の底から信頼すると救われる…これが本来の「信じる者は救われる」の意味です。
いわばスピリチュアルの世界観から生まれた言葉と言ってよいでしょう。
“スピリチュアルの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-

参考お盆と霊を科学する~スピリチュアルの意味を脳科学で説く
「お盆には祖先の霊が私たちのところに訪ねて来る」って言いますが、それってどういうことなのでしょう? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログ ...
続きを見る
スピリチュアル自体には科学的根拠はありません。
しかしスピリチュアルは信じることによって何かしらの心理的な効果を得られるは確かです。

何をどのように信じるかは人それぞれです。
決してイエスでなくてもよいわけです。
そして信じる対象を信じ抜くことで自分が救われるわけです。

信じている対象が結果的に自分に良い影響をもたらしてくれるものであれば何も問題はありません。
しかし不用意に信じることで知らぬ間に相手に裏切られ策略にはめられてしまうことだってあります。
つまり信じることで相手に自分を乗っ取られてしまうわけです。
ですから現代の「信じる者は救われる」は決して本当とは言い難いのかもしれません。

迷信を脳科学で探る
現代において「信じる者は救われる」を実行するには何か心のよりどころが必要となります。

科学的にちゃんと証明された根拠をもっているものであれば何も問題はありません。
しかし世の中には科学的な根拠がなくてもなぜか多くの人に信じられているものがたくさんあります。

それでは迷信とはどう意味でしょう?
迷信と都市伝説は本当なのか?それともやりすぎなのか?

有名な迷信はたくさんあります。
夜に爪を切ると親の死に目に会えない
靴下を履いたまま寝ると親の死に目に会えない
霊柩車(れいきゅうしゃ)を見かけたら親指を隠さないと死んだ人の霊が乗り移ってくる
100回しゃっくりをすると死ぬ
北枕で寝ると死人を再現することになり縁起が悪い
などなどいくらでもあります。
多くの人に知られているような有名な迷信でなくても自分だけの個人的な迷信もあります。
赤い靴下を履いて試験を受けると点数がいい
暑い日はスマホの電池の減りが速い
スマホの待ち受けをお気に入りの芸能人の写真にしたら運が良くなる
1つや2つは個人的な迷信をもっているでしょう。

都市伝説もたくさんあります。
東京の井之頭恩賜公園のボートにカップルで乗ると別れる
京都嵐山の渡月橋をカップルで渡っている時に振り返ると別れる
福井県雄島を反時計回りすると死の世界に引き込まれる
藤野青木ヶ原樹海の積み石を崩すと不幸が起きる
群馬県赤城山には徳川埋蔵金が眠っている
こう見ていくと都市伝説も一種の迷信と言えるでしょう。
多くの人は科学的根拠がないとわかっていても迷信や都市伝説をつい信じてしまいます。
そして迷信や都市伝説を信じることで救いを求めます。
ですから迷信や都市伝説は決してやりすぎではないのです。

迷信のメカニズム

流れ星に願い事をして一度でも叶ったことがある人ならばそれ以降流れ星を見かけるたびにきっと願をかけることになるでしょう。
流れ星以外にも脳はさまざまな出来事のあいだに因果関係を日々認識しています。
つまり脳は偶然起きた2つの別々の出来事を因果関係があるかのようにとらえることを好みます。
この傾向のことを「迷信行動」と言います。
迷信行動はなにも人間に限った話ではありません。
たとえばネズミにエサを与える状況を想像してみてください。
ネズミは檻(おり)の落ち着きなくさまざまな行動をとって動き回っています。
そんな中ネズミが反時計回りに回っている時にエサを与えるようにします。
そのネズミはエサを食べた後はまた元のようにいろいろな行動をとります。
しかし「反時計回りに回る」という行動を先ほどよりも多くとるようになります。
そうすることでエサをもらえる回数が増えることを学ぶわけです。
このように動物でも人間でも何らかの行動に対してご褒美が与えられるとそれ以降その行動がよく観察されるようになります。
脳はご褒美=報酬が大好きです。
“報酬系回路の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
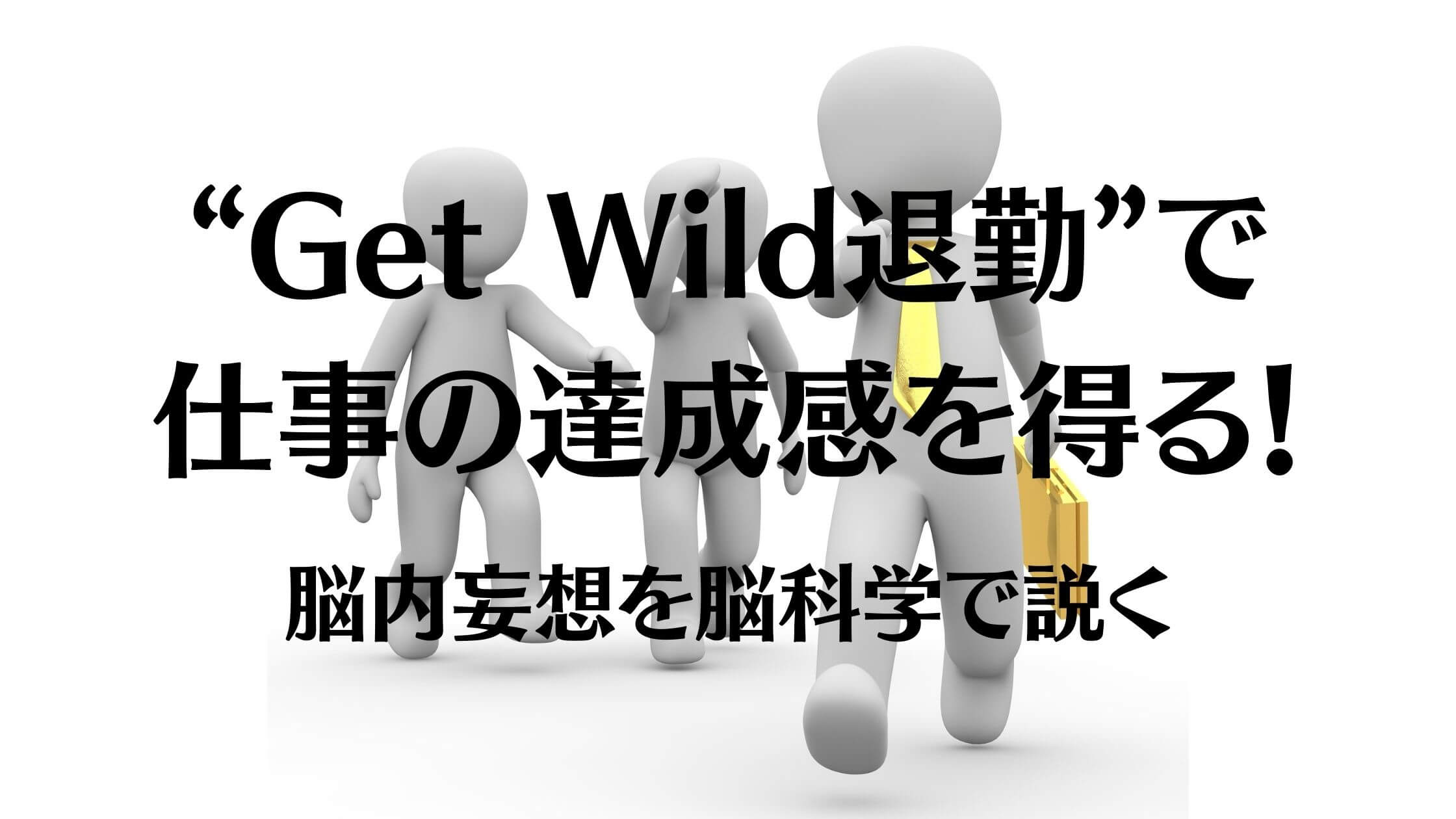
参考“Get Wild退勤”で仕事の達成感を得る!脳内妄想を脳科学で説く
「”Get Wild退勤”で仕事の達成感を得る」とはどういうことなのでしょうか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医と ...
続きを見る
これが迷信行動のメカニズムです。
迷信行動は誰の脳にも備わっている機能です。
ほとんどの人は大なり小なりさまざまな迷信に縛られて生きています。
そして毎日のように同じ「儀式」を繰り返しているのです。
ちなみにとりわけ迷信行動を起こしやすい人がいます。
それは運動選手、ギャンブラー、試験を受ける学生です。
このような人々はゲン担ぎやルーティンを大切にし自分なりのジンクスに頼りがちですよね。

迷信から抜け出す方法
迷信を信じてある行動パターンが作られてしまうとなかなかそこから抜け出せなくなります。
つまり「信じない者は救われない」と信じているからです。
しかし一度作られた行動パターンを打ち消してそこから抜け出す方法はちゃんとあります。

先ほどの流れ星の話であれば「流れ星に願いをかけたのに叶わない」という経験を繰り返すのです。
すると「流れ星に願いをかける」→「願いが叶う」という関係は消去されます。
ただし迷信行動において消去の作業をすることはそう簡単ではありません。
そもそも流れ星のように珍しい出来事を対象としている場合にはそもそも消去を行うチャンスがなかなかやってきません。
またたとえ消去の作業を何度も繰り返せたとしても「願掛けがなぜうまくいかなかったのか?」の理由を考え出そうとしがちになります。
迷信行動によって安心感が得られたり物事に対して前向きになれたりするのであれば消去がうまく出来なくても問題はないでしょう。
しかし科学的根拠のない迷信行動にすがり本来すべき努力を放棄してしまったり冷静な判断ができない状態に陥ってしったりする場合は問題です。
たとえば2つのAとBという別々の事柄に関して見せかけの根拠のない因果関係を見出してしまったとしましょう。
すると
「Aを行えば必ずBという結果になる」
そんな風にまるで自分が結果をコントロールできるように勘違いしてしまいがちです。
本来は自分では制御できないはずの事柄に対して「自分の行動が結果に影響を与えている」と考えてしまうことをコントロール幻想と言います。
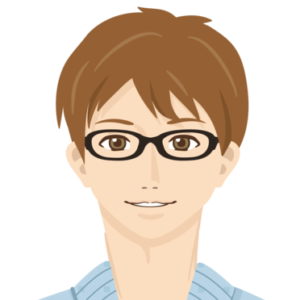
今ツキが来ている!
運が向いている!
そんな実態のない言葉をよく使う人は要注意でしょう。
“運気の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
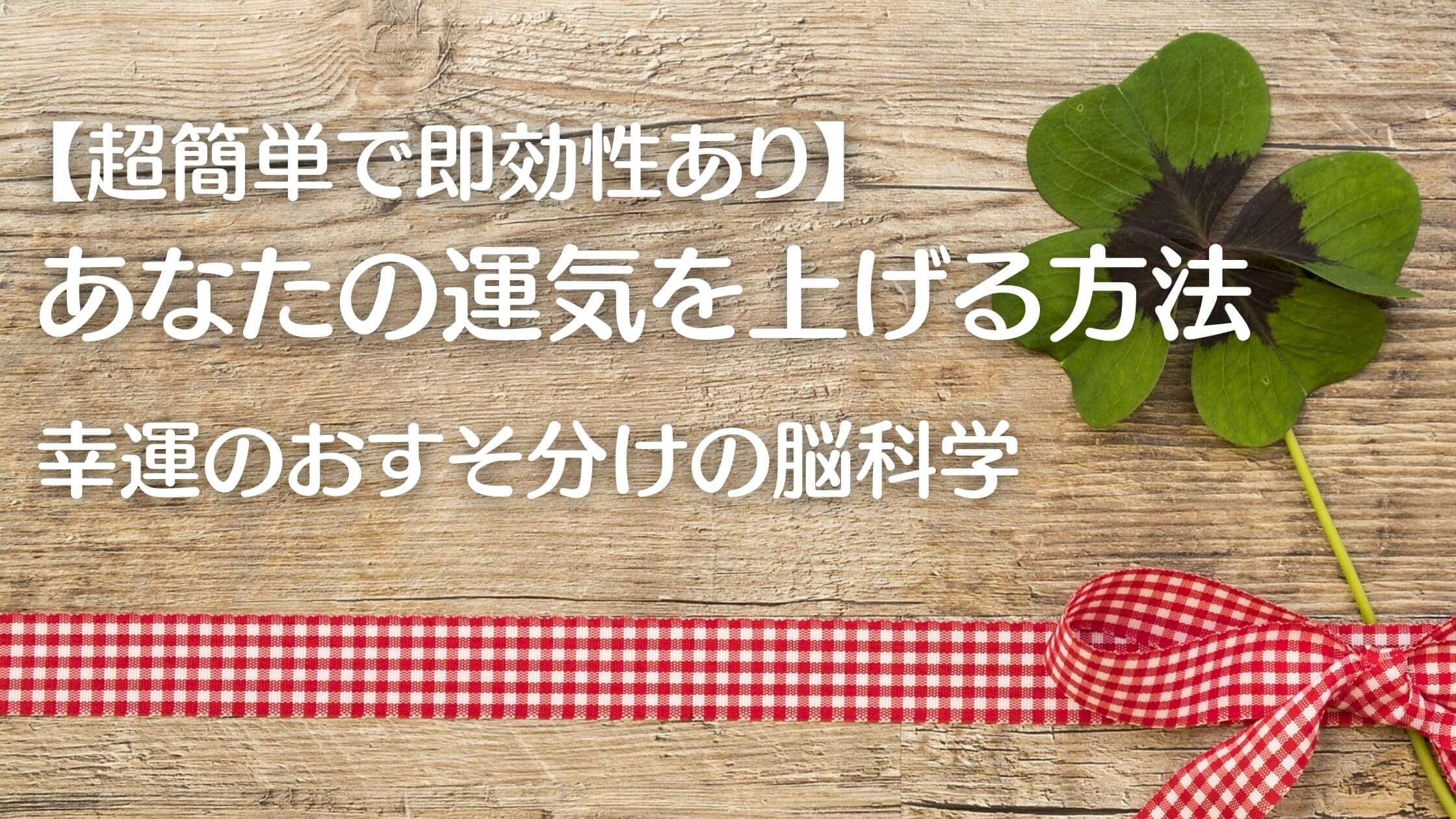
参考【超簡単で即効性あり】『2022年』あなたの運気を上げる方法~幸運のおすそ分けの脳科学
超簡単で即効性のある運気を上げる方法ってありますか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病気 ...
続きを見る
ランダムな事柄は過去の事象からは決して影響を受けることはありません。
「信じる者は救われる」は決して間違いではありません。
しかしそれにすがりすぎるのも問題であることを知っておく必要があります。
疑似相関を脳科学で探る
ここまで脳の迷信行動について説明してきました。
続いては迷信行動と似たような脳の働きである「疑似相関」について脳科学で探っていきましょう。
疑似相関とは?
たとえば「アイスクリームの売り上げが上がるとプールでの水難事故の件数が増える」というデータがあったとしましょう。
このデータをあなたならどのように解釈しますか?
「アイスクリームを食べると溺れやすくなる?」
それとも
「溺れて救助された人はその後アイスクリームが食べたくなる?」
これは2つの事象である
① アイスクリームの売り上げが上がる
② プールでの水難事故の件数が増える
という直接的に関連がない2つの事象のあいだにあたかも因果関係があるかのように解釈しているだけです。
しかし①と②が同時に起きているからといって必ずしも因果関係があるわけではありません。
このように直接的に関連がない2つの事象を科学的根拠のないこじつけの因果関係で結びつけて誤った情報を生み出す現象を「疑似相関」と言います。
疑似相関のワナ
では「疑似相関」はなぜ起こるのでしょう?
疑似相関において2つの事象のあいだいに因果関係があるかのように解釈してしまうのにはそれぞれの事象に関連する第3の事象があるからです。
しかし第3の事象に誰も気づいていないので誤解が生じてしまうのです。
先ほどの例で考えてみましょう。
① アイスクリームの売り上げが上がる
② プールでの水難事故の件数が増える
この2つの事象以外の第3の事象に目を向けなければ問題は解決しません。
では第3の①と②それぞれに影響を与えている隠された第3の事象は何でしょう?


気温が高くなるとアイスクリームはよく売れます。
気温が高くなるとプールに出かける人が増えその結果として水難事故の件数が増えます。
気がついてしまえば単純な話ですがアイスクリームの売り上げと水難事故の件数ばかりに目を奪われていると2つの事象の間に相関関係があるように見えてしまいます。
疑似相関を生み出さないためには2つの事象の関連性を考える時に常に「気温」のような3つ目の事象が存在していないかを考えなければなりません。
ちなみに第3の事象を「潜伏変数(または第3の変数、交絡変数)」と言います。
潜伏変数の脅威
疑似相関が起きていることに気づかないでいると
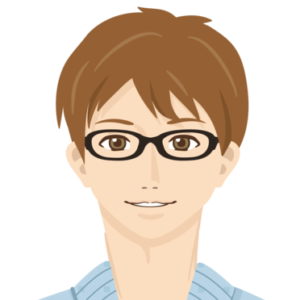
そんな誤った情報が出回ることになります。
ですから第3の事象である潜伏変数を常に意識している必要があります。


① 割引は購買意欲の向上につながるのでしょうか?
新しい機能が注目されているある家電が発売されました。
発売を記念してある店でその商品以外にも全品で10%割引キャンペーンを実施しました。
するとその家電以外にもさまざまな商品が普段以上に売れて割引以上に儲(もう)かりました。
② 牛乳を飲むとがんになりやすいのでしょうか?
牛乳をよく消費しているアメリカやスイスなどの国は牛乳の消費が少ない国と比べてがんになる人が何倍も多い結果でした。

①の潜伏変数は「時期」です。
企業が力を入れ入ている家電はそもそもよく売れる時期…たとえば季節の変わり目やクリスマスなどのイベント時期をねらって発売されます。
ですから割引の効果もあったかもしれませんがそもそも全体的に購買意欲が高まっていて家電がよく売れる時期だったということです。
②の潜伏変数は「寿命の長さ」です。
ここで挙げられているアメリカやスイスはそもそも平均寿命が長い国です。
がんは中年以降に罹(かか)りやすい病気ですので寿命が長くなるとがんになる人は必然的に増えるのです。
脳は多くの情報に振り回され惑わされます。
さまざまなメディアや本や広告の中にはよく「統計によれば…」という文句を見かけます。
そのような文章を見るとついついその情報を信じてしまいがちです。
しかしそれがどのようなデータにも続いてどのように解釈されたものなのかに注意を払う必要があります。
同一のデータから全く異なる解釈を導き出すことだって可能です。

「アイスクリームの売り上げが上がるとプールでの水難事故の件数が増える」
ただ情報に振り回されるのではなく潜伏変数が「気温」ということに気づきさえすれば気温が高い日はアイスクリームの仕入れの数を増やしつつ水難事故を防止するために監視員の数を増やすなどの対策をすることができます。
このような例ではあまり深く考えなくともこのような対策は簡単にできるでしょう。
しかしもっと複雑な事例であれば潜伏変数はいくつも潜んでいる場合もあります。
潜伏変数に振り回されるのではなく潜伏変数を確実にとらえ疑似相関をうまく使いこなしてください。
ちなみに迷信や都市伝説の中には疑似相関をうまく利用したものがたくさんあります。
迷信や都市伝説の裏に隠された潜伏変数に気づきさえすればそれが正しい情報なのか誤った情報なのかを見極められるはずです。
「信じる者は救われる」…何を信じるのかで救われるのか救われないのかが決まるのです。
ギャンブラーの誤謬を脳科学で探る
最後は「ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)」を脳科学で探ります。
「誤謬」とは自分が意図しない間違いや誤解です。
“誤謬の脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-

参考誤謬(ごびゅう)を犯さないために「三段論法」の意味を脳科学で探る
相手に誤解されやすい、理解してもらえない、分かってもらえないのはなぜなのでしょう? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医 ...
続きを見る
ではギャンブラーの誤謬について探っていきましょう。
ギャンブラーの誤謬とは?

“一か八かの賭けの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
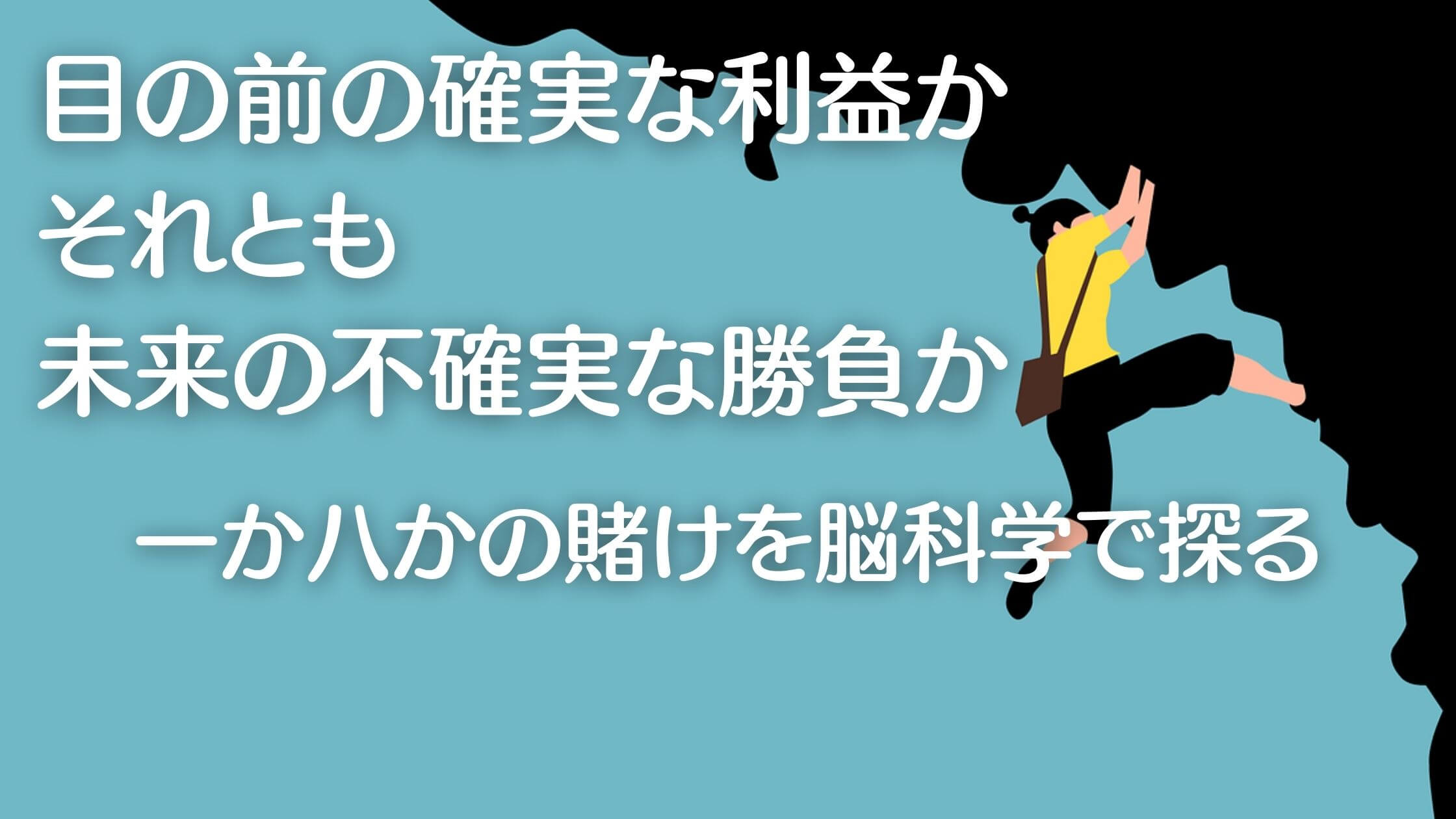
参考目の前の確実な利益かそれとも未来の不確実な勝負か~一か八かの賭けを脳科学で探る
あなたは目の前の確実な利益を選びますか?それとも未来の不確実な勝負を選びますか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医と ...
続きを見る
パチンコやスロットなどのギャンブルにはまっている人の多くが共通しておちいる思考回路があります。
何度も外し続けても
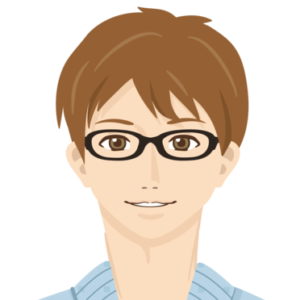
そんな考えでどんどん深みにはまっていくのです。
もちろんそのあと大当たりが出る保証などありませんし投入した金額が大きければ大きいほど脳は熱くなり冷静な判断ができなくなっていきます。
このような脳の思考回路を「ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)」と言います。
連続して同じ結果が出ていると次はきっと違う結果になるのではないかという心理が働くのが「ギャンブラーの誤謬」です。
ではなぜ脳はギャンブラーの誤謬を起こすのでしょう?
ギャンブラーの誤謬のワナ
トランプゲームを思い浮かべてみてください。
裏にしたトランプカードをめくって赤か黒かを当てるゲームをします。
赤の出る確率と黒の出る確率は当然それぞれ1/2です。
たとえばここまで黒が4回連続で出ているとします。
これに続いて引き続き5回連続で黒が出る確率はどうなるでしょう?
1/2×1/2×1/2×1/2×1/2=1/32=0.03125

このように考えると5回連続で黒が出る確率はかなり低いと考えられるので脳は
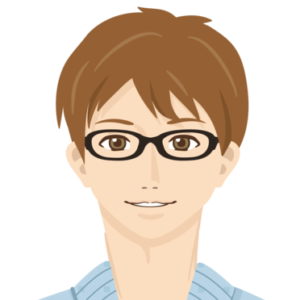
そんなふうに考えるのです。
確かにこのように考えれば確率的に黒がこれ以上連続で出ることはなさそうに思えてしまいます。
「次はきっと赤が出る」と思い込んでしまうのも無理はないかもしれません。
“思い込みの脳科学”についてはこちらの記事もご参照ください。
-
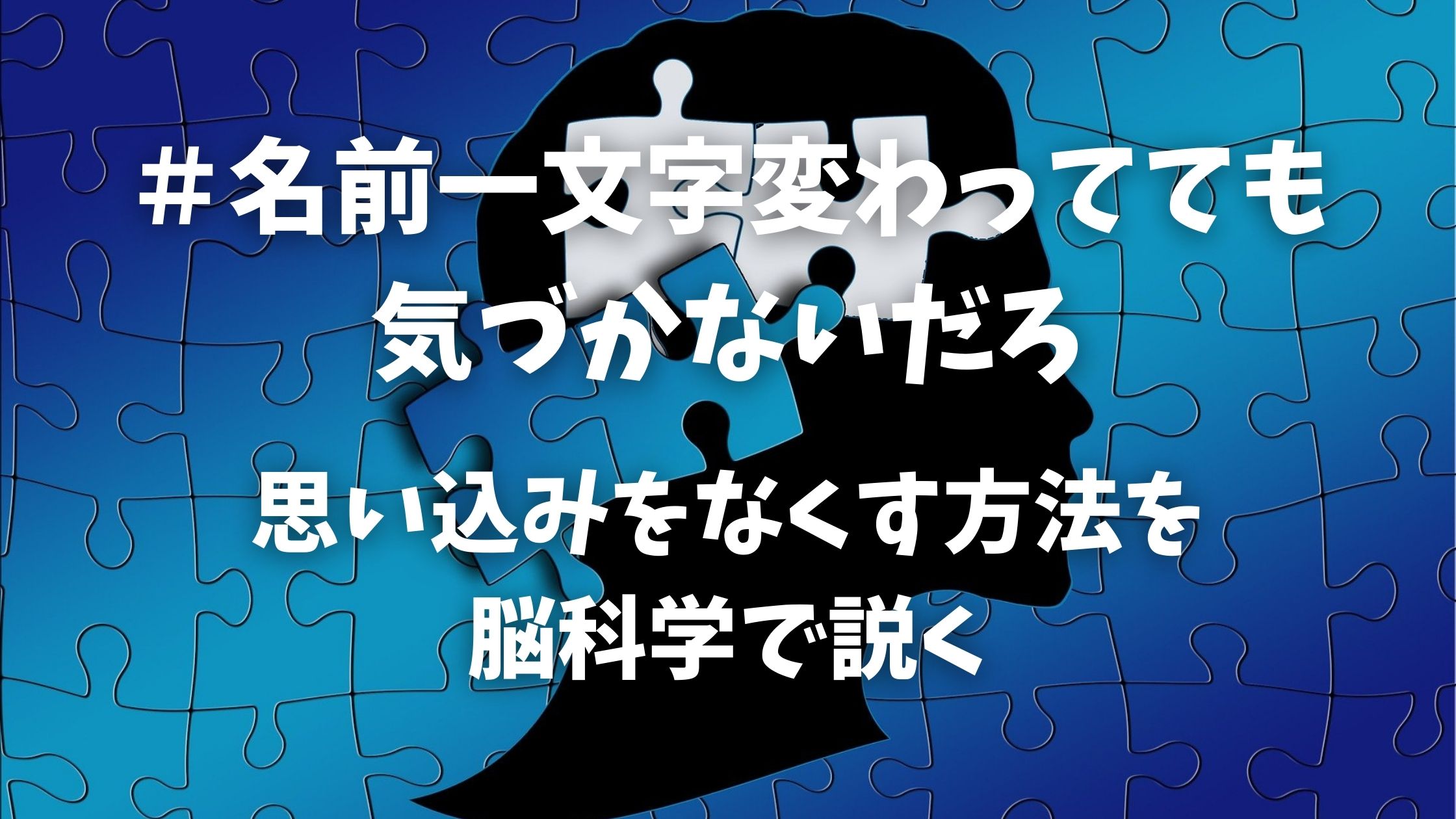
参考#名前一文字変わってても気づかないだろ~思い込みをなくす方法を脳科学で説く
#名前一文字変わってても気づかないだろ”って何ですか? そのような疑問に脳神経外科専門医であるへなおがお答えします。 このブログでは脳神経外科医として20年以上多くの脳の病 ...
続きを見る
しかし実際は5回目の黒が出る確率は1/2で50%なのです。
どうしてなのでしょう?
冷静になって考えてみればわかるはずです。
「5回連続で黒が出る」確率は3.125%です。
しかしそれは結果的に見て5回連続で黒が出た場合です。
たとえ何回連続で黒が出ていたとしても「次のトランプカードが黒である」確率はあくまでも1/2なのです。
気づくべきことはあくまでも「1回ごと」に赤と黒が出るそれぞれの確率はいつでも1/2であるということです。
これは何度トランプかーそをめくったとしても変わることはありません。
確かに黒が5回連続で出る確率は3.125%であり直感的には次も続けて黒が出るとは思えません。
しかしこの考え方には誤謬(ごびゅう)が含まれています。
「次に何色が出るかについての確率はそれまでに何色が何回出たかという結果から影響は受けない」ということが見落とされてしまっているのです。
赤が出るか黒が出るかの確率は1回ごとに予測をする必要があるということを意識していなければならないのです。
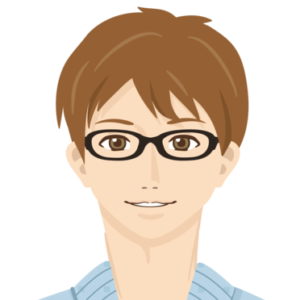
そんなギャンブラーの誤謬が脳をバグらせるのです。
ギャンブラーの誤謬から学ぶべきこと
ギャンブラーの誤謬はギャンブルにはまる人の脳で起きているバグです。
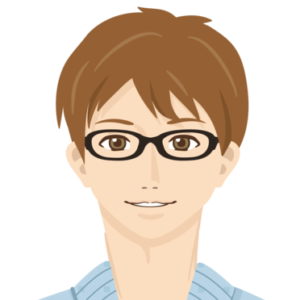
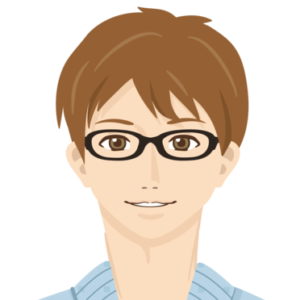
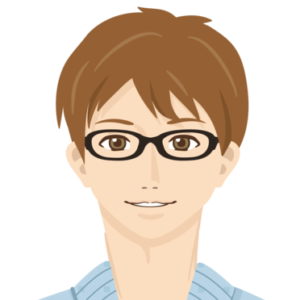
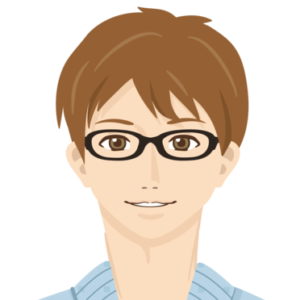
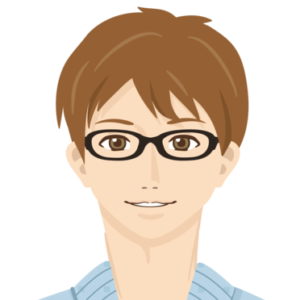
ここまで来てしまうとも脳は興奮状態であり冷静な判断などできるわけがありません。
ギャンブラーの誤謬から学ぶべきことは「過去は未来に影響を与えない」ということです。
もちろん人生において過去と未来はつながっていて断絶されることはありません。
しかしいつまでも悪いことばかり起き続けることはそうあるわけではありません。
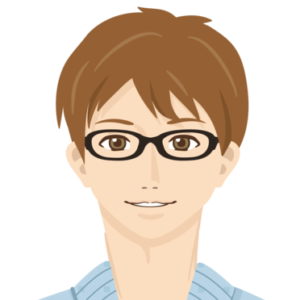
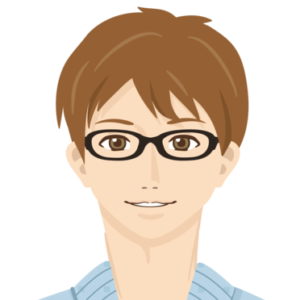
このように前向きに考えることもあながち気休めとは言えないはずです。
これも「信じる者は救われる」のひとつでしょう。
迷信や都市伝説は過去からの言い伝えです。
「過去を信じて救われるのかあるいは過去は信じず自分の未来を信じて救われるのか…」
それはまさにあなた次第なのです。
「信じる者は救われる」が本当かどうかはあなたが何を信じるかにゆだねられているのです。
“「信じる者は救われる」の脳科学”のまとめ
「信じる者は救われる」の意味をわかりやすく脳科学で説き明かしてみました。
今回のまとめ
- 「信じる者は救われる」はそもそもスピリチュアルの世界観から生まれた言葉です。
- 脳が科学的根拠のない迷信や都市伝説を信じてそこに「信じる者は救われる」を見出そうとする「迷信行動」を好みます。
- 直接的に関連がない2つの事象に因果関係を見出そうとする「疑似相関」も「信じる者は救われる」を導き出す脳の働きです。
- 「過去は未来に影響を与えない」ことをうまく理解できていないと誤謬(ごびゅう)を生み出しそこから「信じる者は救われる」が導き出されます。
- 結局「信じる者は救われる」の真意はあなたが何をどう信じているのかにかかっているのです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今後も長年勤めてきた脳神経外科医の視点からあなたのまわりのありふれた日常を脳科学で探り皆さんに情報を提供していきます。
最後にポチっとよろしくお願いします。